麒麟がくるにおける「ここまでの織田信長」を考えると、「史実とのかねあい」で言うなら28年前の「信長KING OF ZIPANGU」より「むしろ後退した」と言えます。そもそも美濃攻めも描きませんでしたし、ほとんど何も描いてはいません。三好や松永、足利義輝といった「畿内の情勢」に時間をとるので、信長を描いている時間はないとも言えそうです。
NHKは最新研究に基づき「保守的側面も」描くと言っていました。「も」です。「保守的側面を」ではないのです。どこが保守的なのか。1、旧権威に対する言葉遣いは丁寧である。頭ごなしに将軍を否定することも、天皇を否定することもない。2、親父から多くのことを学んだ。3、初めから天下を取ろうとなんてしていない。ぐらいでしょうか。親父から学ぶことは別に保守的側面ではないと思いますが、去年の段階からNHKは「父から学ぶなど保守的側面」という言い方をしていました。
あくまで「も」描くなんですね。だからここにきて信長は改革者としての一面を強く印象づける人間になっています。上洛については十兵衛が主導した感じになっていますが、その割には藤吉郎を送り込むなど、十兵衛の知らないところで着々と手を打っている感じです。
信長が「保守的」とか「定説は違っていた」とか「普通の武将だった」とか言われる場合、以下のようなことがよく指摘されます。それは「ドラマ上は」どうなっているでしょうか。
・初めから天下を狙ってなどいない。→これは狙っていない。前半では天下という言葉すら登場しない。「大きな国」である。今は「大きな世」に変わっている。
・旧守護をそれなりに尊重する→わからない。結局守護斯波の息子はどうなったのか?
・政治的システム的には室町幕府のシステムを超えるものではなかった。→わからない。描かれていない。
・室町幕府の存続を考えていた。→今はそうかも。ただし今までの大河でもそうだった。
・特に土地制度については先進的とは言い難い→描かれない。
・反抗しない限り、宗教も保護した。→わからない。まだ描かれていない。熱田神宮はそんなに信奉していない。「熱田に行って、神にでも拝むのか」というセリフがあった。
・朝廷を尊重した。または利用した。天皇を超えようなんて考えはなかった。→正親町帝とは「そりが合わなく」なるらしい。
・楽市楽座も不徹底であり、座を保護することも多かった。→わからない。ただし織田家は金持ちである。津島を押さえているためらしい。
・宗教心を持っていたのではないか。→石仏を「ぺんぺん」していた。あまり持っている感じはしない。
・常識的な人間だった→承認欲求が強すぎて、情緒不安定で、常識的な普通の人間という感じはしない。
つまり「新説の信長」(私は新説に懐疑的ですが)はほとんど描かれていないのです。ただし「天下という用語を避けた」のは新説への配慮でありましょう。そこは「大きな変更」なので、新しく見えることは確かです。
一方で信長は「それでも信長だ」「やっぱり普通の武将とか常識的人間は言い過ぎでしょ」「改革者の側面の方が強い」と言われる場合、以下のことが指摘されます。「ドラマ上」はどうでしょうか。
・臨機応変な思考、合理的判断→あまり鋭い感じはしない。が後編になってやけに「戦略的」になって鋭くなり「いつもの信長」に近くなっている。池に潜ったのは合理性の表現か?
・居城の敵地接近移転→描かれない。小牧山城は出てこなかったと思う。細かくみると出てきているのかも知れない。
・新兵器の活用→「鉄砲の話」がどっかに行ってしまった。十兵衛も信長も話題にしなくなった。長槍の話も全くない。ただし今井宗久が出たので「鉄砲復活」であろう。
・軍事組織のスケールの大きさ→わからない。描かれない。
・強い配下武将支配・重臣の合議制ではない意志決定→決定権は信長にあるようである。配下武将を怒鳴り飛ばしたり蹴飛ばしたりすることはない。実力主義はとっているようでもある。柴田と佐久間ぐらいしか重臣が出ない。幕臣の摂津晴門は散々怒鳴られて復讐を誓っていた。
・関所の廃止、ある程度成功→強くは描かれない。光秀が関所を疑問に思うシーンは1話にあったし、菊丸と関所を通りぬけるシーンもあった。
・伝統権威でも逆らえばつぶす方向で「慎重に」行動する、比叡山→そうなるらしい。
・室町幕府の存続を本心で望んでいたかは不明だが、結局は交渉決裂。義昭の子を将軍としてたてることはなかった。→どう描かれるか分からない。
・官位をもらうこともあるが、すぐ辞任してしまう。執着はない。官位を辞して後、死ぬまで官職はなかった。→官位への執着はなさそうで、義輝と対面した時、官位を断ったらしい。ドラマ上は官位が描かれる。しかし義昭は最初は「尾張守」と呼んでいたが、今は「織田殿」と呼んでいる。官位で呼ぶということもなさそうである。
・ある程度の検地→検地は描かれない。
・兵農分離もそこそこ成功・専業武士団の創設→描かれない。前田と佐々が出てきた場面、あれは専業武士団なのか?十兵衛は田を耕してはいた。
・反抗する宗教勢力・自治都市などには容赦なかった。ただし自治都市はさほど反抗しなかった。→描かれない、比叡山は描かれるが、本願寺は分からない。というより堺への信長の「攻撃」などは「なかったこと」にされるようである。
・座の保護も含めた、商業政策の重視→商業政策は重視しているらしい。ただし「座」は全く描かれない。
ほとんど「描かれない」わけです。これは「信長が主人公ではないから当然」でもありますが、堺の件のように「あえて嘘を描く=フィクションにする」ことも多いような気がします。
で、今のところの私の結論なんですが「大河新時代というのは、どうやら史実にこだわらず、フィクション性を高める。あと画像を美しくする。」ということみたいだ、となります。後半を見ないと断定はできませんが、「フィクション性を高める。エンタメ度を高める。その為に時代考証より文化風俗考証に力を入れる。新鮮味を演出する」というのが「大河新時代の中身」になっていく気がします。もっとも風俗考証がどこまで正確かは私の力量では分かりません。「青天を衝け」でも「鎌倉殿の13人」でも絵を美しくするため文化風俗は詳しく描かれる「予感」がします。ただ「青天を衝け」は「近代」なので戦国ものよりは史実にこだわるだろうし、近代はこだわってもらわないと困ります。私は大河はフィクションでいいと思いますが、近代は別です。だから「近代は扱わないほうがいいかも」とも思っています。
NHKは最新研究に基づき「保守的側面も」描くと言っていました。「も」です。「保守的側面を」ではないのです。どこが保守的なのか。1、旧権威に対する言葉遣いは丁寧である。頭ごなしに将軍を否定することも、天皇を否定することもない。2、親父から多くのことを学んだ。3、初めから天下を取ろうとなんてしていない。ぐらいでしょうか。親父から学ぶことは別に保守的側面ではないと思いますが、去年の段階からNHKは「父から学ぶなど保守的側面」という言い方をしていました。
あくまで「も」描くなんですね。だからここにきて信長は改革者としての一面を強く印象づける人間になっています。上洛については十兵衛が主導した感じになっていますが、その割には藤吉郎を送り込むなど、十兵衛の知らないところで着々と手を打っている感じです。
信長が「保守的」とか「定説は違っていた」とか「普通の武将だった」とか言われる場合、以下のようなことがよく指摘されます。それは「ドラマ上は」どうなっているでしょうか。
・初めから天下を狙ってなどいない。→これは狙っていない。前半では天下という言葉すら登場しない。「大きな国」である。今は「大きな世」に変わっている。
・旧守護をそれなりに尊重する→わからない。結局守護斯波の息子はどうなったのか?
・政治的システム的には室町幕府のシステムを超えるものではなかった。→わからない。描かれていない。
・室町幕府の存続を考えていた。→今はそうかも。ただし今までの大河でもそうだった。
・特に土地制度については先進的とは言い難い→描かれない。
・反抗しない限り、宗教も保護した。→わからない。まだ描かれていない。熱田神宮はそんなに信奉していない。「熱田に行って、神にでも拝むのか」というセリフがあった。
・朝廷を尊重した。または利用した。天皇を超えようなんて考えはなかった。→正親町帝とは「そりが合わなく」なるらしい。
・楽市楽座も不徹底であり、座を保護することも多かった。→わからない。ただし織田家は金持ちである。津島を押さえているためらしい。
・宗教心を持っていたのではないか。→石仏を「ぺんぺん」していた。あまり持っている感じはしない。
・常識的な人間だった→承認欲求が強すぎて、情緒不安定で、常識的な普通の人間という感じはしない。
つまり「新説の信長」(私は新説に懐疑的ですが)はほとんど描かれていないのです。ただし「天下という用語を避けた」のは新説への配慮でありましょう。そこは「大きな変更」なので、新しく見えることは確かです。
一方で信長は「それでも信長だ」「やっぱり普通の武将とか常識的人間は言い過ぎでしょ」「改革者の側面の方が強い」と言われる場合、以下のことが指摘されます。「ドラマ上」はどうでしょうか。
・臨機応変な思考、合理的判断→あまり鋭い感じはしない。が後編になってやけに「戦略的」になって鋭くなり「いつもの信長」に近くなっている。池に潜ったのは合理性の表現か?
・居城の敵地接近移転→描かれない。小牧山城は出てこなかったと思う。細かくみると出てきているのかも知れない。
・新兵器の活用→「鉄砲の話」がどっかに行ってしまった。十兵衛も信長も話題にしなくなった。長槍の話も全くない。ただし今井宗久が出たので「鉄砲復活」であろう。
・軍事組織のスケールの大きさ→わからない。描かれない。
・強い配下武将支配・重臣の合議制ではない意志決定→決定権は信長にあるようである。配下武将を怒鳴り飛ばしたり蹴飛ばしたりすることはない。実力主義はとっているようでもある。柴田と佐久間ぐらいしか重臣が出ない。幕臣の摂津晴門は散々怒鳴られて復讐を誓っていた。
・関所の廃止、ある程度成功→強くは描かれない。光秀が関所を疑問に思うシーンは1話にあったし、菊丸と関所を通りぬけるシーンもあった。
・伝統権威でも逆らえばつぶす方向で「慎重に」行動する、比叡山→そうなるらしい。
・室町幕府の存続を本心で望んでいたかは不明だが、結局は交渉決裂。義昭の子を将軍としてたてることはなかった。→どう描かれるか分からない。
・官位をもらうこともあるが、すぐ辞任してしまう。執着はない。官位を辞して後、死ぬまで官職はなかった。→官位への執着はなさそうで、義輝と対面した時、官位を断ったらしい。ドラマ上は官位が描かれる。しかし義昭は最初は「尾張守」と呼んでいたが、今は「織田殿」と呼んでいる。官位で呼ぶということもなさそうである。
・ある程度の検地→検地は描かれない。
・兵農分離もそこそこ成功・専業武士団の創設→描かれない。前田と佐々が出てきた場面、あれは専業武士団なのか?十兵衛は田を耕してはいた。
・反抗する宗教勢力・自治都市などには容赦なかった。ただし自治都市はさほど反抗しなかった。→描かれない、比叡山は描かれるが、本願寺は分からない。というより堺への信長の「攻撃」などは「なかったこと」にされるようである。
・座の保護も含めた、商業政策の重視→商業政策は重視しているらしい。ただし「座」は全く描かれない。
ほとんど「描かれない」わけです。これは「信長が主人公ではないから当然」でもありますが、堺の件のように「あえて嘘を描く=フィクションにする」ことも多いような気がします。
で、今のところの私の結論なんですが「大河新時代というのは、どうやら史実にこだわらず、フィクション性を高める。あと画像を美しくする。」ということみたいだ、となります。後半を見ないと断定はできませんが、「フィクション性を高める。エンタメ度を高める。その為に時代考証より文化風俗考証に力を入れる。新鮮味を演出する」というのが「大河新時代の中身」になっていく気がします。もっとも風俗考証がどこまで正確かは私の力量では分かりません。「青天を衝け」でも「鎌倉殿の13人」でも絵を美しくするため文化風俗は詳しく描かれる「予感」がします。ただ「青天を衝け」は「近代」なので戦国ものよりは史実にこだわるだろうし、近代はこだわってもらわないと困ります。私は大河はフィクションでいいと思いますが、近代は別です。だから「近代は扱わないほうがいいかも」とも思っています。











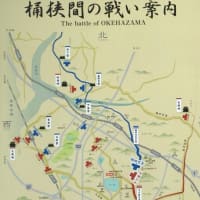


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます