最近は「戦国足利将軍はカイライではなかった」という学者さんの本が多くあります。別に「カイライであってほしい」とも思ってないし、足利義昭は傀儡じゃなかったから信長によって追放されるわけです。だからそれはいいというか、ここで反論する気はないのです。カイライか否か、それそのものは答えを出すほど重要な問題じゃないような気もします。
昨日、足利義輝さんに関する本を読んだのです。するとそこに義輝さんが、軍事的にも経済的にもそこそこ潤っていた。義輝の二条城なんてそりゃ立派なもんなんだという記述があったのです。
そこで「うん?」と思ったのですね。義輝さんがそういうご身分なら、どうして朝廷を援助しないのだろうと。そりゃ信長のように大金はたくのは無理としても、ちょっとは朝廷の権威回復に動いてもいい。
「嘘も多い」Wikipediaにこうあります。
諸大名の任官斡旋には力を尽くしたものの、義輝自身は将軍就任翌年に従四位下参議・左近衛権中将に任ぜられてから18年間にわたって昇進をせず、また内裏への参内も記録に残るのはわずか5回である。
これは事実なんでしょうか。こういうことになるとさっと訂正がはいるわけで、訂正されてないところを見ると、まんざら嘘でもないのでしょう。
信長は有名な「異見17条」の1条で「義輝は参内しなかったからあんな悲惨な最期を迎えたのだ。義昭さん、参内しなさい」と書いています。
☆義輝・義昭の二代に渡って、参内を怠っていたらしい。そこにどんな理由があるのだろう。信長が朝廷を尊重しても、肝心の義昭さんがそれをしなかったとすると、それは何故?という疑問が湧くわけです。
一方で織田信長は内裏の修理に「一万貫文」、約十億円を使ったと言われています。全部自腹ではないでしょうが。
信長以前には「最初の天下人とも言われることのある三好長慶」「その家臣である松永久秀」「そして将軍足利義輝」が京都にいたわけです。にもかかわらず、リフォームに十億もかかる状態になっても、内裏はいわば打ち捨てられた状態にあったことになる可能性があります。
信長の「中世的側面」を強調する場合「将軍家と天皇家を尊重した」とよく言われます。実際信長は尊重しています。しかし肝心の「中世的権威の親玉」である「将軍家」はさほど朝廷を尊重しているようには見えないわけです。義輝・義昭と。
これはどういうことなんだろう?信長は中世的だが、将軍家は中世を突き抜けていたということだろうか。
そして信長にしてからが、官位には興味がないようで上洛期の1568年から1574(または1575)年まで「ずっと弾正忠」のままです。その後右大臣になりますが、すぐ辞任で、本能寺段階では「さきの右大臣」のままです。
将軍家は朝廷に利用価値があるとは思っていなかったのかも知れません。しかし信長は朝廷には十分な利用価値があると考えた。そこでまず朝廷を復興した。しかし朝廷システムの中に入っていくことには非常に慎重であった。この朝廷の利用の仕方は、信長の画期的政策と言えるのかも知れません。
昨日、足利義輝さんに関する本を読んだのです。するとそこに義輝さんが、軍事的にも経済的にもそこそこ潤っていた。義輝の二条城なんてそりゃ立派なもんなんだという記述があったのです。
そこで「うん?」と思ったのですね。義輝さんがそういうご身分なら、どうして朝廷を援助しないのだろうと。そりゃ信長のように大金はたくのは無理としても、ちょっとは朝廷の権威回復に動いてもいい。
「嘘も多い」Wikipediaにこうあります。
諸大名の任官斡旋には力を尽くしたものの、義輝自身は将軍就任翌年に従四位下参議・左近衛権中将に任ぜられてから18年間にわたって昇進をせず、また内裏への参内も記録に残るのはわずか5回である。
これは事実なんでしょうか。こういうことになるとさっと訂正がはいるわけで、訂正されてないところを見ると、まんざら嘘でもないのでしょう。
信長は有名な「異見17条」の1条で「義輝は参内しなかったからあんな悲惨な最期を迎えたのだ。義昭さん、参内しなさい」と書いています。
☆義輝・義昭の二代に渡って、参内を怠っていたらしい。そこにどんな理由があるのだろう。信長が朝廷を尊重しても、肝心の義昭さんがそれをしなかったとすると、それは何故?という疑問が湧くわけです。
一方で織田信長は内裏の修理に「一万貫文」、約十億円を使ったと言われています。全部自腹ではないでしょうが。
信長以前には「最初の天下人とも言われることのある三好長慶」「その家臣である松永久秀」「そして将軍足利義輝」が京都にいたわけです。にもかかわらず、リフォームに十億もかかる状態になっても、内裏はいわば打ち捨てられた状態にあったことになる可能性があります。
信長の「中世的側面」を強調する場合「将軍家と天皇家を尊重した」とよく言われます。実際信長は尊重しています。しかし肝心の「中世的権威の親玉」である「将軍家」はさほど朝廷を尊重しているようには見えないわけです。義輝・義昭と。
これはどういうことなんだろう?信長は中世的だが、将軍家は中世を突き抜けていたということだろうか。
そして信長にしてからが、官位には興味がないようで上洛期の1568年から1574(または1575)年まで「ずっと弾正忠」のままです。その後右大臣になりますが、すぐ辞任で、本能寺段階では「さきの右大臣」のままです。
将軍家は朝廷に利用価値があるとは思っていなかったのかも知れません。しかし信長は朝廷には十分な利用価値があると考えた。そこでまず朝廷を復興した。しかし朝廷システムの中に入っていくことには非常に慎重であった。この朝廷の利用の仕方は、信長の画期的政策と言えるのかも知れません。











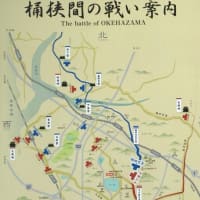


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます