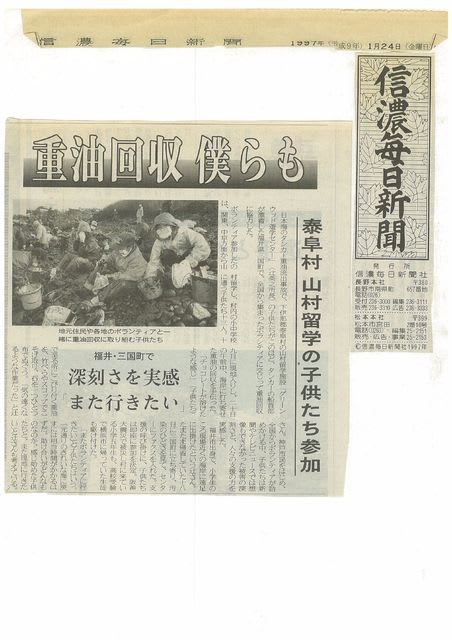ウワサの天草エアラインの飛行機に乗った。
倒産寸前の小さな航空会社が奇跡のV字復活、と、テレビだかなんだかでやっていた気がする。
これがそうなんだろう。
ずいぶんとカワイイ機体だ。

この機体が降り立ったのは、熊本空港。
被災地に足を運ぶのは、今年度5回目である。
これまでの4回は、こどものためだった。
NPOグリーンウッドが主催する信州こども山賊キャンプに、被災したこどもたちを招待して2年。
呼びかけにきたり、打ち合わせに来たり、説明会に来たり、報告会に来たり。
今回は、こどものためだけではない。
被災地の復興を目指すひとびとから、講演に呼ばれた。
被災地のど真ん中、震源地の益城町。
衝撃的な光景が広がったこの地も、見た目はすっかり片付いている。
しかしこの地はこれからだ。
そんなことを想うひとびとが、益城町だけではなく広く被災地全体から集まった。
定員をうわまわる参加をいただたというから来た甲斐がある。
主催者は、RQ災害教育センター。
東日本大震災を機に、全国の自然学校といわれる運動体が束になって作った機関である。
自然学校という手法を用いて被災地を復興できないか。
このような趣旨だ。
被災者にとっては自然学校などどうでもよいことだろう。
私もそう想う。
私は泰阜村とNPOグリーンウッドの30年の実践を語った。
そして、今後の夢も。

泰阜村もまた被災地だ。
あらゆる国策に翻弄され続けてきた、いや、これでもかというほど痛めつけられてきた、弱き僻地山村である。
そう、泰阜村は国策被災地なのだ。
そんな国策被災地が今、教育立村に向けて歩みを始めようとしている。
そんな話をした。
短い時間だったが、参加者の強い想いが渦巻いた。
私は、支え合いの縁を豊かに紡いでいくことを「支縁」と呼んでいる。
支援が支縁になっていく。
代表 辻だいち
倒産寸前の小さな航空会社が奇跡のV字復活、と、テレビだかなんだかでやっていた気がする。
これがそうなんだろう。
ずいぶんとカワイイ機体だ。

この機体が降り立ったのは、熊本空港。
被災地に足を運ぶのは、今年度5回目である。
これまでの4回は、こどものためだった。
NPOグリーンウッドが主催する信州こども山賊キャンプに、被災したこどもたちを招待して2年。
呼びかけにきたり、打ち合わせに来たり、説明会に来たり、報告会に来たり。
今回は、こどものためだけではない。
被災地の復興を目指すひとびとから、講演に呼ばれた。
被災地のど真ん中、震源地の益城町。
衝撃的な光景が広がったこの地も、見た目はすっかり片付いている。
しかしこの地はこれからだ。
そんなことを想うひとびとが、益城町だけではなく広く被災地全体から集まった。
定員をうわまわる参加をいただたというから来た甲斐がある。
主催者は、RQ災害教育センター。
東日本大震災を機に、全国の自然学校といわれる運動体が束になって作った機関である。
自然学校という手法を用いて被災地を復興できないか。
このような趣旨だ。
被災者にとっては自然学校などどうでもよいことだろう。
私もそう想う。
私は泰阜村とNPOグリーンウッドの30年の実践を語った。
そして、今後の夢も。

泰阜村もまた被災地だ。
あらゆる国策に翻弄され続けてきた、いや、これでもかというほど痛めつけられてきた、弱き僻地山村である。
そう、泰阜村は国策被災地なのだ。
そんな国策被災地が今、教育立村に向けて歩みを始めようとしている。
そんな話をした。
短い時間だったが、参加者の強い想いが渦巻いた。
私は、支え合いの縁を豊かに紡いでいくことを「支縁」と呼んでいる。
支援が支縁になっていく。
代表 辻だいち