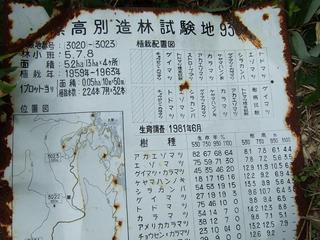・惜しいところで芦別岳の山頂は雲に隠れているが,朝から晴天である。今回はエゾマツ播種実験の実生発生調査の第一回目ということで,当方を含めた教員4名,久しぶりに再会したTさん,樹木園のOさんにも同行してもらって,12林班の試験地へ行く。富良野の新緑の清清しさは例えようがないほどである。そういえば,本州から来た人達を案内するたびにみんなが感動していたのを思い出した。この時期ならではの醍醐味である。
・現地到着。まだ虫も少なく,快適である。最初のプロット高標高の地がき地(HS-1)を調べる。いきなり鹿がピート板に足跡をつけている。ふーむ,まるで実生らしきものは見えず,草本の芽生えがちらほらとあるだけである。こいつは試験そのものが成り立っていないのでは,という恐ろしい疑念が生じてくる。

・次のプロットに行くと,今度はピートブロックを見ていたSさんが何やら忙しそうにしている。もしかしてと思ったら,なるほど数本のエゾマツ実生が頭をもたげている。などといっていたら,本当は出てこないはずの直播で実生がぞくぞくと発見されたり・・・。やはり実生が見つかると騒がしくなってくる。どのように記録するかについて,作業を続けつつあーでもないこーでもないと議論。結局,発見された実生の全数をカウントし,そのうちの被害を内数としてカウントすることに決定。
・被害は,上部を切り取られるもの(虫・鳥・動物??),根ごと浮き上がるもの(抜け),立枯れ病,くらいに分類されそうである。とりあえず,なるべく詳細に記載することに決定。全体として,直播(秋)が結構発芽している。また,見てくれは決して良くない(失礼・・・)ピートブロックが意外と健闘している。凹凸のある形状が発芽実生まわりの超微気象をマイルドにしているのであろうか・・・。
・天然林になると,日当たりが悪いせいか,実生の発生数がさらに少なくなり,調査も淡々と進む・・・。といいたいところだが,面子が面子だけに終始にぎやかである。当方提案のピート板は、地がき地よりも天然林内の方が成績がよい(フラットな地形が影響しているのか??)。地がき地では、枠のすぐそばの端っこでしか発芽しなかったのだが,天然林では真ん中付近からも発芽している。林内では、ササはかなり丁寧に刈っているのだが,直播はかなり厳しそうである。
・低標高は実生数がさらに多くなり,中には200種子中80種子も発芽している処理区もあった。多くなるとカウントするのも大変であるが,その分,充実感はある。処理による違いも明瞭になりそうな予感で,何となく研究として成り立ちそうな気がしてきた,といったところ。

・Kさんが昆虫のトラップを見たいというので立ち止まったところで、オオカメノキの花が満開である。ちょっとのぞくと、花に見せられた昆虫達が乱舞している。甲虫類も多く、やはり生物相が多様であることを実感させられる。これを子どもに見せると喜ぶんだがなあと思いつつ、デジカメで撮影。この写真をよく見ると、ハナグモらしきものがアブ?を捕食している。
・午後から苗畑での播種試験の実生調査枠の設置と試験区の確認。秋に議論して計画したはずの試験設計をみんなが忘れていたりして・・・。いやはや,人の記憶とはいい加減なもので・・・。当方作成の野帳のメモを見ながらようやく理解でき,10×80cmの特注枠を設定してみる。この枠は重いのでそのまま置きっぱなしにできるところがいいところ。しかも,真ん中が2つに分かれているため,結局,1つの処理について6の反復を取ることができる。
・苗畑での実生の数は想像以上に集中分布で,これだけ近い6個の枠間でも相当のバラツキがあり,データ的にもなかなか楽しい。こちらの試験はむしろこれからが本番といったところ。

・Tさんにお願いしていた標高別トドマツのフェノロジー・データは想像以上に精密で、十分論文に耐えうるものである。相互移植の方はかなりの個体が着花していることが分かる。Tさんは接木個体の方も調べてくれていて、さらには晩霜害のデータも取ってくれていた(すごい!)。

・5月10日に富良野地方を襲った低温(霜)は、この地域に甚大な影響を及ぼしている。K林長が収集した小さな方のブナ産地試験もご覧の通りの有様である。しかし、これは、逆に、自然選択に対する応答反応をみる格好の機会と捉えることもできそうだ。被害のデータはK林長が取ってくれているとのことだが、開葉フェノロジーデータとあわせると、また面白い知見が見えてくるかもしれない。

・ブナの方はまだいいとしても、苗畑の被害(特に床替え苗)は厳しい。開芽の遅いアカエゾマツは大丈夫だが、トドマツとエゾマツは痛々しい状況である。新しい葉が展開し始めてはいるものの、最終的にどのようになるのか注意深く見守る必要がありそうだ。色々と気になること、面白いことばかりで、目がようやく開かれたところだったのだが、当方の都合で今日の最終便にとんぼ返り。すごい充実した出張であった。