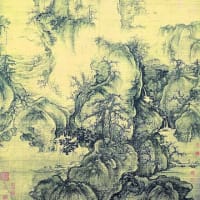平成30年に摘発された「M資金詐欺」の解明が進んでいることが報じられた。
戦後幾度となく繰り返されたM資金詐欺は、概ね資産家がターゲットにされているために被害額も桁違いで、今回の事案でも大手飲食チェーのトップが28億円搾取されたとされている。企業経営者ですら射幸心をくすぐられるM資金とは何かと勉強した。M資金とは、連合国軍最高司令部(GHQ)が占領下の日本で接収した巨額の資金が現在も日本政府の一部の人々によって秘密運用され、これまでに多くの国家的危機に際して利用されたものの、なお巨額の資産が残されているというものである。Mは、GHQ経済科学局の第2代局長であったマーカット少将の頭文字とするのが定説となっている。物語の始まりは、大東亜戦争末期の金属類回収令(昭和18年)で貴金属を含む戦争継続のための資源供出を求めたことに遡る。全国から寄せられた貴金属の大半は使用されることもなく日銀の本支店で保管されていたが、その額は戦後の大蔵省の発表によるとダイヤだけでも150万個、16万カラットにもなったとされる。これらの資産は敗戦とともにGHQ経済科学局の管理下に置かれることになった。講和条約発効後、これらの資産はGHQから接収解除され復興資金に充てられたが、使途については不透明な部分もあったとされている。その後、昭和33年の「接収貴金属等の処理に関する法律」で貴金属は供出した人に返還されることになったが、戦災による被災死や関係書類の消失によって返還不能となった多くの貴金属は国の所有するところとなった。では、なぜM資金が詐欺に利用されるかと云うと、GHQ経済科学局の日銀金庫管理担当官だったエドワード・マレーが帰国後、約500個のダイヤを不正に持ち出した容疑で米国当局に逮捕され禁固10年の実刑判決を受けたり、初代局長・同局将校ら十数人が後に米国で汚職や横領などの罪で検挙・更迭されたことから、秘密資金としてなお隠匿された部分があるとされるためである。また1946(昭和21)年に日本軍が東京湾の越中島海底に隠匿していた大量の貴金属地金が米軍によって発見・押収された事件等から、明らかにされていない隠匿資産があると噂されることも大きいようである。さらにGHQの管理下に置かれた押収貴金属類の返還を受けた日本金属が会社を清算した際に5億6580万円もの残余財産があったこともM資金の額と存在に信憑性を与えているらしい。1966(昭和41)年に、政府は国有財産となった供出(接収)ダイヤを業者・個人に売却し、公式には金属類回収令に起因する戦後処理を終えたが、その後もM資金の存在を信じる人も多く、これまでM資金詐欺は数百件も起きているとされている。
山下奉文大将率いる日本軍が終戦時フィリピンに埋めたとされるマル福金貨を含む山下財宝、大政奉還時の勘定奉行小栗忠順が幕府再興資金として赤城山中へ埋めたとされる徳川埋蔵金とともに、M資金は都市伝説として笑い飛ばすには惜しいもので、当時の社会背景と混乱を考えれば、説得力を持った詐欺の材料として今も活用できるのだろう。一方で、資産を投げ打って山下財宝や徳川埋蔵金の発見に執念を燃やす人の存在も報じられており、そこには金銭を度外視したロマンも隠されているようにも見える。