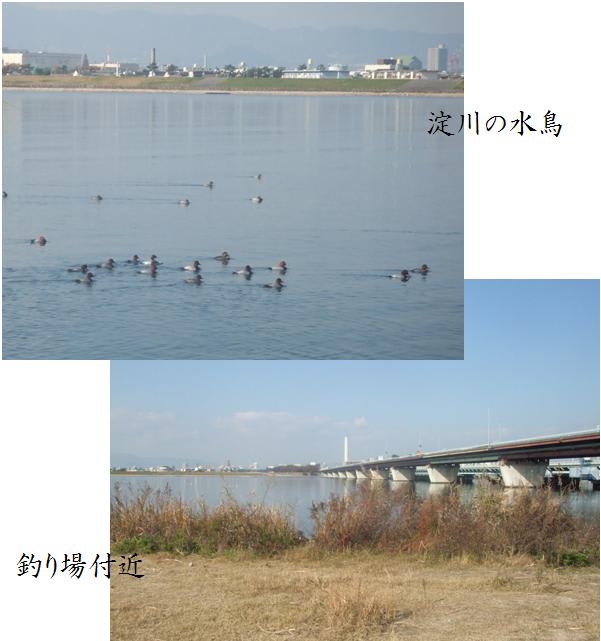昨12月21日四天王寺の終い弘法市でした。
京都の東寺の終い弘法が有名ですが、大阪四天王寺の終い弘法市もおおいに賑わいます。JR天王寺駅から四天王寺まで10分足らずの道のりですが人の列が途切れなく続き、道の両側には出店が沢山出ています。
石の鳥居をくぐり、西大門から境内に入ります、大変な賑わいで混雑していました。
古着を売る店が多く、骨董品の出店もかなりあります。
お正月用の食料品を買い求めておられる人もあり皆さん楽しそうでした。
キリジイも記念に中折れ帽子を一つ買うことにしました。

六時堂は
境内中央に位置する雄大なお堂で、昼夜6回 にわたって
諸礼讃をするところから六時礼讃堂の名があります。薬師
如来・四天王等をお祀りしており、回向(供養)、 納骨等を
行う当寺の中心道場でもあります。 入口には賓頭盧尊者
像やおもかる地蔵が祀られ、独特の信仰を集めています。
又、修正会・ 聖霊会などの大法要はこのお堂にて行われ
ます。『四天王寺HPより』



五重塔は
聖徳太子創建の時、六道利救の悲願を
込めて、塔の礎石心柱の中に仏舎利六
粒と自らの髻髪(きっぱつ)六毛を納めら
れたので、この塔を「六道利救の塔」とい
います。
塔の入口は南北にありますが、通常開放
しているのは北側のみで、南正面に釈迦
三尊の壁画と四天王の木像をお祀りして
います。なお、この中心壁と外壁の各面
に描かれた仏画は山下摩起画伯の筆に
よるものです。
四天王寺のHPより
四天王寺の歴史
四天王寺は、推古天皇元年(593)に建立されました。 今から1400年以上も
前のことです。 『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬子の合戦
の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、
自ら四天王像を彫り 「もし、この戦いに勝たせていただけるなら、四天王を安
置する寺院を建立しましょう」 と誓願され、勝利の後その誓いを果すために、
建立されました。
四天王寺のHPより
詳しくはここから