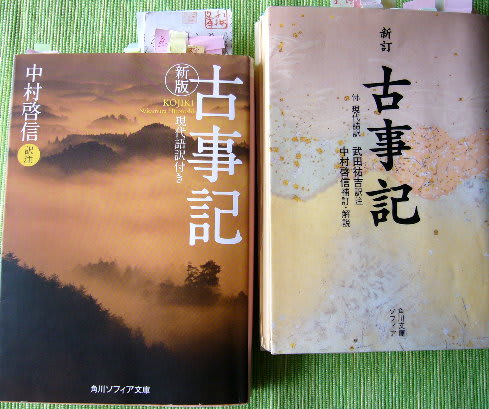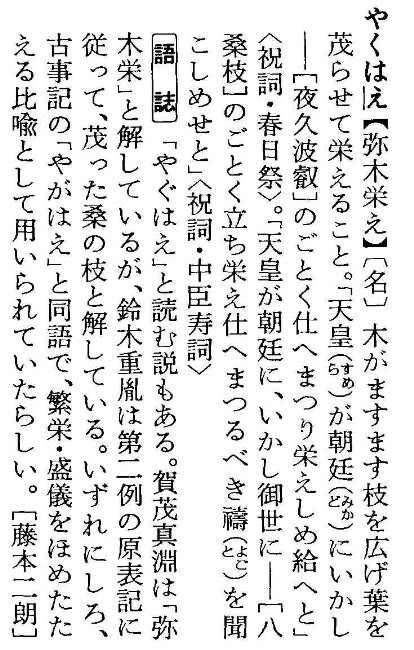携帯で娘との話が終わると、二人の孫がかわるがわる電話に出ます。
下の孫は、「今何の話していたの?」
電話での娘の受け答えから、外出の相談だと察して「しめた!」とばかりにすぐに聞いてきます。
上の孫が電話に出る時は、何かうれしい報告がある時。
今回は、毎年金管バンドが出演する市の行事の日程が決まったことと、徒競争でのタイムの報告でした。
50M走での記録が、7.9秒だったとのこと!
素晴らしい走りです。
男子の記録が、8.9秒だということなのでダントツに速いですねぇ~~~
「さきちゃんは、子どもの頃は8.3~8.4くらいだったと思うよ」というと、「四捨五入すると、8秒だけどね」っと孫。
(そこは四捨五入しなくてもいいんじゃぁ~~ ・・・・ )
)
当の本人も相当に嬉しかったらしく、しばらく会話が弾みました!
家族内で、「いったい誰に似て速いんだろうね?」という話になると、決まってそれぞれが「子どもの頃は速かった!」とか「よく選手になった!」とか。
かくいう私も小学生のころまでは、短距離では良く選手になっていました。
そういえば、息子が小学6年の時、学校代表で市の大会に出て、学校が優勝出来たということがありました。
その小学校は、大会で勝ったことが無かったので校長先生が甚く喜ばれたということでした。
そして、評判が伝わったのか、その年の町内の運動会に班の選手で出て欲しいと、家に担当の方がスカウトに来られました。
低い鼻も一気に高~~~く!!
そんなこともありました!!
やっぱり血筋ですか?
いえいえ、本人の頑張りです!
本人の頑張りなくしてこのような素晴らしい記録は生まれません!!
せっかく報告してくれるのですから、しっかりと褒めて喜びを分かち合いました!

下の孫は、「今何の話していたの?」
電話での娘の受け答えから、外出の相談だと察して「しめた!」とばかりにすぐに聞いてきます。
上の孫が電話に出る時は、何かうれしい報告がある時。
今回は、毎年金管バンドが出演する市の行事の日程が決まったことと、徒競争でのタイムの報告でした。
50M走での記録が、7.9秒だったとのこと!
素晴らしい走りです。

男子の記録が、8.9秒だということなのでダントツに速いですねぇ~~~
「さきちゃんは、子どもの頃は8.3~8.4くらいだったと思うよ」というと、「四捨五入すると、8秒だけどね」っと孫。
(そこは四捨五入しなくてもいいんじゃぁ~~ ・・・・
 )
)当の本人も相当に嬉しかったらしく、しばらく会話が弾みました!
家族内で、「いったい誰に似て速いんだろうね?」という話になると、決まってそれぞれが「子どもの頃は速かった!」とか「よく選手になった!」とか。

かくいう私も小学生のころまでは、短距離では良く選手になっていました。

そういえば、息子が小学6年の時、学校代表で市の大会に出て、学校が優勝出来たということがありました。
その小学校は、大会で勝ったことが無かったので校長先生が甚く喜ばれたということでした。
そして、評判が伝わったのか、その年の町内の運動会に班の選手で出て欲しいと、家に担当の方がスカウトに来られました。
低い鼻も一気に高~~~く!!

そんなこともありました!!
やっぱり血筋ですか?
いえいえ、本人の頑張りです!

本人の頑張りなくしてこのような素晴らしい記録は生まれません!!
せっかく報告してくれるのですから、しっかりと褒めて喜びを分かち合いました!