少々古い話になりますが、2013年に出版された東北大学の清和研二教授の「多種共存の森:1000年続く森と林業の恵み」は、森林の多様性がどのような仕組みで成り立っているかということを解き明かしていて、たいへん興味深いものでした。
多種共存の森: 1000年続く森と林業の恵み | 清和 研二 |本 | 通販 | Amazon
Youtubeに、清和教授の講演があったので、関心のあるかたはご覧ください。
東北大学サイエンスカフェ 第163回「多種共存の森~その仕組みと恵み~」 - YouTube
熱帯雨林の森林の多様性の仮説が温帯林でも適用されるということをフィールドワークを通じて解明しています。
樹木は毎年多くの種子を作って子孫を拡散していますが、親木の周りのすぐ近くで発生した芽生えに対して、菌根菌が選択的に同種の芽生えを枯らして、他の樹種が生育できる環境を作って、近くに同種の木が更新しないようにすることで多様な(樹種)の森が育つというものです。菌根菌による枯死率が低いブナなどは純林を作るようです。










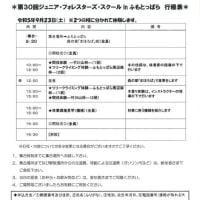



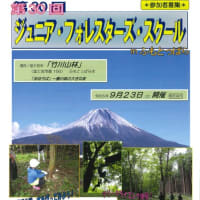
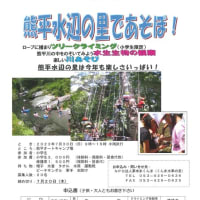


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます