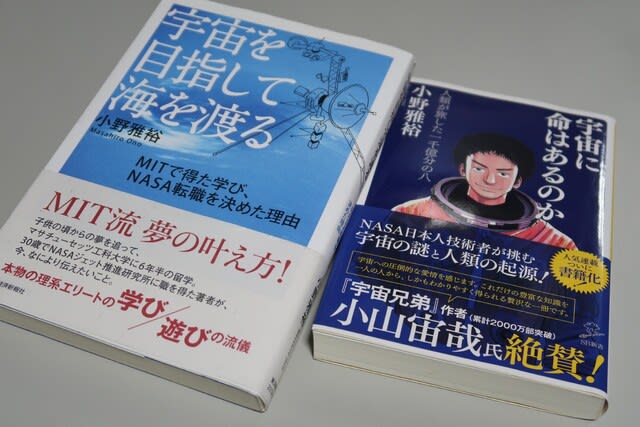
☆『宇宙に命はあるのか』(小野雅裕・著、SB新書、2018年)、『宇宙を目指して海を渡る』(小野雅裕・著、東洋経済新報社、2014年)☆
天文や宇宙に興味を持つ人たちは、大きく2つに分けることができるのではないかと、わたしはかねがね思っています。1つは「天文学」に興味を持つ人たちで、もう1つは「宇宙開発」に興味を持つ人たちです。実際にはどちらにも興味を持っている人が多いとは思いますが、どちらかと言えば「天文学」、あるいは「宇宙開発」に、もう片方よりも興味を持っているという傾向があるのではないでしょうか。大学の学部学科に例えれば、理学部の天文学科や宇宙物理学科に進みたいか、あるいは工学部の航空宇宙工学科などに進みたいのかのちがいとも言えるでしょう。
わたしも両方の分野に興味を持っていますが、いまからあらためて大学へ進学できるならば(その能力があるかどうかはともかくとして)迷わず理学部で宇宙物理学を学びたいと思う方です。本当にいまから大学院への進学を許されるならば、宇宙物理学よりも科学史や科学技術社会論のような学際的な分野を選ぶかもしれませんが、ここでは「天文学」か「宇宙開発」かの二択で考えた場合の話です。
これまで天文や宇宙に関する本はかなり読んできたと自負していますが、いまあらためて読んできた(買ってきた)本を振り返ってみると、圧倒的に「天文学」分野に偏っていることに気付かされます。近年はとくにその傾向が強まっているように思います。
カール・セーガンの名著『コスモス』は「天文学」の本でもあり、「宇宙開発」の夢を描いた本でもあったのですが、わたしはとても熱い気持ちで、夢中になって読んだことを昨日のように覚えています。地球外生命探査などは緒についたばかりの頃だったはずで、だからこそ素直に「夢」に酔えたのかもしれません。
ところが、現在では太陽系外に多くの惑星が発見され、それらの惑星に生命が存在できるかどうかを判定しようとする時代になりました。「ハビタブルゾーン」(生命が存在できる惑星系の空間で、生命居住可能領域などと訳される)という言葉を目にすることも珍しくなくなってきました。
いまやロケットの打ち上げなど日常的なイベントに近い状態となっています。それはロケットが国の威信をかけて打ち上げられるだけでなく、民間企業が商用のための衛星を打ち上げることが多くなってきた証拠でもあります。例えばイーロン・マスクによって設立されたSpaceXはとくに有名ですが、スターリンク計画で何かと物議を醸したりもしています。また、地球上を周回する衛星やその残骸(スペースデブリ)は数え切れないほどあります。
さらに国の威信をかけて打ち上げるロケットは、国威発揚や技術力の示威を超えて、現実的な安全保障上の問題となってきています。いつの間にか宇宙は軍拡競争やビジネスの場となり、純粋な「夢」を紡ぐ聖域ではなくなってきているように思います。それは技術開発において当然の成り行きでもあるのでしょうが、老境に足を踏み入れつつある「星好き」からすれば、やはり悲哀のような感情を抑えることはできないものです。
そういった現実を日々目の当たりにするからか、ある種の偏見や勉強不足もあるでしょうが、どうしても「宇宙開発」には負のイメージがまとわりついてしまい、その種の本からも目をそらしてしまう結果を招いています。
『宇宙に命はあるのか』の著者である小野雅裕さんはNASAの中にあるJPL(ジェット推進研究所)で宇宙開発(本書によれば火星探査ロボットの開発)に携わっている現役の研究者(技術者)です。本書は出版当初から相当な人気を博していたので、わたしも知っていました。しかし、1982年生まれの若い技術者が書いた宇宙開発の本らしいということで、あまり手に取る気にはならず黙殺していました。
ところが、ある時、SpaceXについて小野さんが「その技術力は高く評価するが、足りないとすれば謙虚さであろう」と発言していることを知り、俄然この本に対する興味がわいてきました。実際に一読してみて、すばらしい本であることがわかりました。たしかに「宇宙開発」系の本とは言えるでしょうが、地球外生命探査に関わる「天文学」的な話題も多く、そして何よりも著者の熱い気持ちが直に伝わってくるような本でした。わたしにしてみれば、むかし熱い気持ちで読んだあの『コスモス』の再来のように思えました(本書にもカール・セーガンの『コスモス』のことが出てきます)。読み終わって、わたしの偏見は完全に一掃されました。
『宇宙に命はあるのか』を買ったとき、同時に『宇宙を目指して海を渡る』も買いました。小野さんの経歴は東大工学部航空宇宙工学科を出てMITに留学し、いまはJPLで働いているという華々しいものですが、そこに至る人生について知りたいと思ったからです。だから『宇宙に命はあるのか』よりも先に『宇宙を目指して海を渡る』を読みました。
この『宇宙を目指して海を渡る』は、アマゾンのレビューなどを見ると「傲慢」だの「ナルシズム」だのという批判も散見されますが、わたしにはとてもそのようには思えませんでした。たしかに持って生まれた能力がある方なのでしょうが、自分の夢を叶えるために努力していることがわかるはずです。わたしが『宇宙に命はあるのか』を読む前に偏見を持っていたように、やはり偏見で批判的なことを書いている人もいるのかもしれません。
『宇宙に命はあるのか』は日本人の手による『コスモス』の再来であり、ここまで宇宙開発が進んだ時代に生きている幸せを感じさせてくれる本だと思います。願わくは、宇宙開発において人類が「謙虚さ」を忘却しないでほしいものです!

天文や宇宙に興味を持つ人たちは、大きく2つに分けることができるのではないかと、わたしはかねがね思っています。1つは「天文学」に興味を持つ人たちで、もう1つは「宇宙開発」に興味を持つ人たちです。実際にはどちらにも興味を持っている人が多いとは思いますが、どちらかと言えば「天文学」、あるいは「宇宙開発」に、もう片方よりも興味を持っているという傾向があるのではないでしょうか。大学の学部学科に例えれば、理学部の天文学科や宇宙物理学科に進みたいか、あるいは工学部の航空宇宙工学科などに進みたいのかのちがいとも言えるでしょう。
わたしも両方の分野に興味を持っていますが、いまからあらためて大学へ進学できるならば(その能力があるかどうかはともかくとして)迷わず理学部で宇宙物理学を学びたいと思う方です。本当にいまから大学院への進学を許されるならば、宇宙物理学よりも科学史や科学技術社会論のような学際的な分野を選ぶかもしれませんが、ここでは「天文学」か「宇宙開発」かの二択で考えた場合の話です。
これまで天文や宇宙に関する本はかなり読んできたと自負していますが、いまあらためて読んできた(買ってきた)本を振り返ってみると、圧倒的に「天文学」分野に偏っていることに気付かされます。近年はとくにその傾向が強まっているように思います。
カール・セーガンの名著『コスモス』は「天文学」の本でもあり、「宇宙開発」の夢を描いた本でもあったのですが、わたしはとても熱い気持ちで、夢中になって読んだことを昨日のように覚えています。地球外生命探査などは緒についたばかりの頃だったはずで、だからこそ素直に「夢」に酔えたのかもしれません。
ところが、現在では太陽系外に多くの惑星が発見され、それらの惑星に生命が存在できるかどうかを判定しようとする時代になりました。「ハビタブルゾーン」(生命が存在できる惑星系の空間で、生命居住可能領域などと訳される)という言葉を目にすることも珍しくなくなってきました。
いまやロケットの打ち上げなど日常的なイベントに近い状態となっています。それはロケットが国の威信をかけて打ち上げられるだけでなく、民間企業が商用のための衛星を打ち上げることが多くなってきた証拠でもあります。例えばイーロン・マスクによって設立されたSpaceXはとくに有名ですが、スターリンク計画で何かと物議を醸したりもしています。また、地球上を周回する衛星やその残骸(スペースデブリ)は数え切れないほどあります。
さらに国の威信をかけて打ち上げるロケットは、国威発揚や技術力の示威を超えて、現実的な安全保障上の問題となってきています。いつの間にか宇宙は軍拡競争やビジネスの場となり、純粋な「夢」を紡ぐ聖域ではなくなってきているように思います。それは技術開発において当然の成り行きでもあるのでしょうが、老境に足を踏み入れつつある「星好き」からすれば、やはり悲哀のような感情を抑えることはできないものです。
そういった現実を日々目の当たりにするからか、ある種の偏見や勉強不足もあるでしょうが、どうしても「宇宙開発」には負のイメージがまとわりついてしまい、その種の本からも目をそらしてしまう結果を招いています。
『宇宙に命はあるのか』の著者である小野雅裕さんはNASAの中にあるJPL(ジェット推進研究所)で宇宙開発(本書によれば火星探査ロボットの開発)に携わっている現役の研究者(技術者)です。本書は出版当初から相当な人気を博していたので、わたしも知っていました。しかし、1982年生まれの若い技術者が書いた宇宙開発の本らしいということで、あまり手に取る気にはならず黙殺していました。
ところが、ある時、SpaceXについて小野さんが「その技術力は高く評価するが、足りないとすれば謙虚さであろう」と発言していることを知り、俄然この本に対する興味がわいてきました。実際に一読してみて、すばらしい本であることがわかりました。たしかに「宇宙開発」系の本とは言えるでしょうが、地球外生命探査に関わる「天文学」的な話題も多く、そして何よりも著者の熱い気持ちが直に伝わってくるような本でした。わたしにしてみれば、むかし熱い気持ちで読んだあの『コスモス』の再来のように思えました(本書にもカール・セーガンの『コスモス』のことが出てきます)。読み終わって、わたしの偏見は完全に一掃されました。
『宇宙に命はあるのか』を買ったとき、同時に『宇宙を目指して海を渡る』も買いました。小野さんの経歴は東大工学部航空宇宙工学科を出てMITに留学し、いまはJPLで働いているという華々しいものですが、そこに至る人生について知りたいと思ったからです。だから『宇宙に命はあるのか』よりも先に『宇宙を目指して海を渡る』を読みました。
この『宇宙を目指して海を渡る』は、アマゾンのレビューなどを見ると「傲慢」だの「ナルシズム」だのという批判も散見されますが、わたしにはとてもそのようには思えませんでした。たしかに持って生まれた能力がある方なのでしょうが、自分の夢を叶えるために努力していることがわかるはずです。わたしが『宇宙に命はあるのか』を読む前に偏見を持っていたように、やはり偏見で批判的なことを書いている人もいるのかもしれません。
『宇宙に命はあるのか』は日本人の手による『コスモス』の再来であり、ここまで宇宙開発が進んだ時代に生きている幸せを感じさせてくれる本だと思います。願わくは、宇宙開発において人類が「謙虚さ」を忘却しないでほしいものです!

























