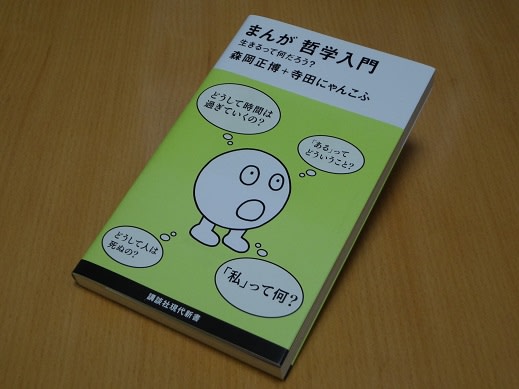
☆『まんが 哲学入門』(森岡正博・寺田にゃんこふ・著、講談社現代新書)☆
人は哲学に何を求めるのだろうか。哲学(philosophy)の語源に遡って、知を愛すること、知の根源に迫ること、それを哲学に求めるのだという答えもあるだろう。しかしそれは、哲学や学問にある程度親しんだ人の答えではないかと思う。ごく普通に毎日の生活を送っていても、ふと哲学に惹かれることがある。「毎日の生活に生きる実感がないのはなぜだろうか? そもそも生きるって何だろうか?」―そんな問いかけを哲学に託しているように思う。先の「知を愛するための哲学」に対して、「生きるための哲学」といえるだろうか。この動機は重要である。これをきっかけにして、うまく哲学の道に乗り、自分なりに哲学を深めていける人は幸せだ。有名な哲学者たちの学説との出会いは、その後にくるべきだろう。
森岡正博さんに初めて“出会った”のは、もう四半世紀も前、森岡さんのデビュー作『生命学への招待』においてである(ちなみに、実際の森岡さんとは、たぶん十年くらい前にあるシンポジウムで講演を拝聴しただけで、直にお会いしたことは一度もない)。この『生命学への招待』との“出会い”は、自分の後半生を決定づけたといっていい。けっして易しい本ではなかったが、既成の学問を解体し「生命学」を構想するスケールの大きさに圧倒され、アカデミズムを破壊するかのような森岡さんの若さに酔いしれた。自然科学だけでなく、フェミニズム、エコロジー、マイノリティなどの言説にも興味を持っていたこともあり、非才を顧みず、もう一度こんな学問をやってみたいと思った。もちろんこの経験は、「生きるための哲学」との出会いというよりは、「知を愛するための哲学」の自分なりの刷新(あるいは更新)というべきだろう。
その後、森岡さんの本が出るたびに買い続け、それなりに読み続けてきた。「それなりに」というのは、表面的な読みに終始しているのではないかという、忸怩たる思いをいつも抱いているからである。森岡さんの著書を次々と読み進めていくうちに、編著書の『ささえあいの人間学』あたりから、「知を愛するための哲学」だけでなく「生きるための哲学」を徐々に徐々に感じはじめた。とくに『無痛文明論』や『生命学に何ができるか』には、知的興奮というよりも、むしろ文学や芸術作品にも似た感動をおぼえた。
この『まんが 哲学入門』の発刊を知ったとき、どのような内容になるのか見当がつかなかった。実際に手に取って読んでみると、哲学の主要テーマと思われる「時間」、「存在」、「私」、「生命」について、森岡さんの考えがいきいきと伝わってきた。読むのに2時間もかからなかった。これを活字で読んだら、たとえ同じ新書であっても、時間的にも労力的にもかなりきついだろう。たとえば活字ではなかなか理解しにくい「いま」や「世界の存在」について、このまんがで初めてわかったような気がした。もちろん、世にはびこる「まんがでわかる○○」といったたぐいの本とは一線を画している。まんがを用いることで無意味に程度を落としたり、むしろわかりにくくなっている例を見かけるが、本書は程度を落とすことなく、ズバリ本質を突いている。まんがに本質を突く力があるとすれば、まんがと(やはり本質を突く)哲学的思考とは、たしかに相性がいいのかもしれない。
人は「いま」しか生きられないにもかかわらず、過去や未来を思い煩う、本当に「過去―現在―未来」があるかのように。森岡さんによれば「過去―現在―未来」が本当にあるかのような強烈な迫力で私に迫ってくるのは、私が身体全体で「生きよう」としているからであり、そのために「次の一歩」を踏み出すための確固たる地盤である「未来それ自体」があるという確信が生まれる。そこから「過去それ自体」があるという確信が生まれ、両者をつなぐものとして「現在それ自体」があるという確信が生まれる。これをてこにして(これだけでも十二分に卓見だと思うが)「第4章 生命論」では「誕生肯定」の哲学へと結実していく。
そこで森岡さんは、「私はなぜ生まれてきたのか」の問いに対して、「私によってのみ可能なかけがえのない誕生肯定の仕方を、この宇宙において実現するために私は生まれてきた」と答える。ここに示されているのは、「生きる」ことを肯定する強烈なメッセージである。それが宗教や文学ではなく、哲学によって(それも有名な哲学者の言葉を引用することなく、哲学者・森岡正博自身の言葉で)導き出されたことに感動する。森岡さんのウェブサイトでは、森岡さんの「生命の哲学」や「誕生肯定」についてさらに深い思索が綴られている。本書はそこへ至るための道標であり、そして「生きるための哲学」の嚆矢ともいえるかもしれない。さらに付け加えれば、巻末の詳細な「読書案内」は、哲学の道を進んでみようと思う人にとって、親切かつ有益である。
『生命学への招待』との出会いにはじまり、僭越ながら自分なりの考えや想いを表現したいと思い、後半生を過ごしてきた。幸いにも哲学や思想を若干ながら学ぶ機会も得られた。とはいえ、そこで学んだ哲学は、やはり学説の解釈や引用に終始するもののように思われた(それでも哲学プロパーの人から見れば、問題外にゆるやかだったようだが)。だからといって、けっして無益だったわけではない。自分が緻密な哲学的思考や、論文を書くことに向いていないことを自覚しただけでも有益だった。しかし、もっとも落胆したのは、そこで接した人たちの研究や論文のほとんどに、自分が感動をおぼえなかったことである。だからこそ、自分の能力を棚に上げて、感動するような研究をしたいと思った。そんなとき遠距離介護がはじまり、研究どころではなくなって、昨年末それが終わった。
ここへきて、体力や能力の減退を感じざるを得ない日々が増えてきた。これからは、具体的な「終活」も考えなければならないだろう。知的能力が保たれている間に、読みたい本をできるだけ読んでおこうと思う。その一環として、「森岡正博」をもう一度自分なりに読んでみようかとも思っている。この『まんが 哲学入門』は買ってから半年以上もツンドク状態だった。母の介護で読むのをすっかり忘れていたからだ。介護から解放されたいま、時間を与えてくれた母に感謝するとともに、自分に残された時間の有効な活用を、まずは読書に充てようかと思っている。

人は哲学に何を求めるのだろうか。哲学(philosophy)の語源に遡って、知を愛すること、知の根源に迫ること、それを哲学に求めるのだという答えもあるだろう。しかしそれは、哲学や学問にある程度親しんだ人の答えではないかと思う。ごく普通に毎日の生活を送っていても、ふと哲学に惹かれることがある。「毎日の生活に生きる実感がないのはなぜだろうか? そもそも生きるって何だろうか?」―そんな問いかけを哲学に託しているように思う。先の「知を愛するための哲学」に対して、「生きるための哲学」といえるだろうか。この動機は重要である。これをきっかけにして、うまく哲学の道に乗り、自分なりに哲学を深めていける人は幸せだ。有名な哲学者たちの学説との出会いは、その後にくるべきだろう。
森岡正博さんに初めて“出会った”のは、もう四半世紀も前、森岡さんのデビュー作『生命学への招待』においてである(ちなみに、実際の森岡さんとは、たぶん十年くらい前にあるシンポジウムで講演を拝聴しただけで、直にお会いしたことは一度もない)。この『生命学への招待』との“出会い”は、自分の後半生を決定づけたといっていい。けっして易しい本ではなかったが、既成の学問を解体し「生命学」を構想するスケールの大きさに圧倒され、アカデミズムを破壊するかのような森岡さんの若さに酔いしれた。自然科学だけでなく、フェミニズム、エコロジー、マイノリティなどの言説にも興味を持っていたこともあり、非才を顧みず、もう一度こんな学問をやってみたいと思った。もちろんこの経験は、「生きるための哲学」との出会いというよりは、「知を愛するための哲学」の自分なりの刷新(あるいは更新)というべきだろう。
その後、森岡さんの本が出るたびに買い続け、それなりに読み続けてきた。「それなりに」というのは、表面的な読みに終始しているのではないかという、忸怩たる思いをいつも抱いているからである。森岡さんの著書を次々と読み進めていくうちに、編著書の『ささえあいの人間学』あたりから、「知を愛するための哲学」だけでなく「生きるための哲学」を徐々に徐々に感じはじめた。とくに『無痛文明論』や『生命学に何ができるか』には、知的興奮というよりも、むしろ文学や芸術作品にも似た感動をおぼえた。
この『まんが 哲学入門』の発刊を知ったとき、どのような内容になるのか見当がつかなかった。実際に手に取って読んでみると、哲学の主要テーマと思われる「時間」、「存在」、「私」、「生命」について、森岡さんの考えがいきいきと伝わってきた。読むのに2時間もかからなかった。これを活字で読んだら、たとえ同じ新書であっても、時間的にも労力的にもかなりきついだろう。たとえば活字ではなかなか理解しにくい「いま」や「世界の存在」について、このまんがで初めてわかったような気がした。もちろん、世にはびこる「まんがでわかる○○」といったたぐいの本とは一線を画している。まんがを用いることで無意味に程度を落としたり、むしろわかりにくくなっている例を見かけるが、本書は程度を落とすことなく、ズバリ本質を突いている。まんがに本質を突く力があるとすれば、まんがと(やはり本質を突く)哲学的思考とは、たしかに相性がいいのかもしれない。
人は「いま」しか生きられないにもかかわらず、過去や未来を思い煩う、本当に「過去―現在―未来」があるかのように。森岡さんによれば「過去―現在―未来」が本当にあるかのような強烈な迫力で私に迫ってくるのは、私が身体全体で「生きよう」としているからであり、そのために「次の一歩」を踏み出すための確固たる地盤である「未来それ自体」があるという確信が生まれる。そこから「過去それ自体」があるという確信が生まれ、両者をつなぐものとして「現在それ自体」があるという確信が生まれる。これをてこにして(これだけでも十二分に卓見だと思うが)「第4章 生命論」では「誕生肯定」の哲学へと結実していく。
そこで森岡さんは、「私はなぜ生まれてきたのか」の問いに対して、「私によってのみ可能なかけがえのない誕生肯定の仕方を、この宇宙において実現するために私は生まれてきた」と答える。ここに示されているのは、「生きる」ことを肯定する強烈なメッセージである。それが宗教や文学ではなく、哲学によって(それも有名な哲学者の言葉を引用することなく、哲学者・森岡正博自身の言葉で)導き出されたことに感動する。森岡さんのウェブサイトでは、森岡さんの「生命の哲学」や「誕生肯定」についてさらに深い思索が綴られている。本書はそこへ至るための道標であり、そして「生きるための哲学」の嚆矢ともいえるかもしれない。さらに付け加えれば、巻末の詳細な「読書案内」は、哲学の道を進んでみようと思う人にとって、親切かつ有益である。
『生命学への招待』との出会いにはじまり、僭越ながら自分なりの考えや想いを表現したいと思い、後半生を過ごしてきた。幸いにも哲学や思想を若干ながら学ぶ機会も得られた。とはいえ、そこで学んだ哲学は、やはり学説の解釈や引用に終始するもののように思われた(それでも哲学プロパーの人から見れば、問題外にゆるやかだったようだが)。だからといって、けっして無益だったわけではない。自分が緻密な哲学的思考や、論文を書くことに向いていないことを自覚しただけでも有益だった。しかし、もっとも落胆したのは、そこで接した人たちの研究や論文のほとんどに、自分が感動をおぼえなかったことである。だからこそ、自分の能力を棚に上げて、感動するような研究をしたいと思った。そんなとき遠距離介護がはじまり、研究どころではなくなって、昨年末それが終わった。
ここへきて、体力や能力の減退を感じざるを得ない日々が増えてきた。これからは、具体的な「終活」も考えなければならないだろう。知的能力が保たれている間に、読みたい本をできるだけ読んでおこうと思う。その一環として、「森岡正博」をもう一度自分なりに読んでみようかとも思っている。この『まんが 哲学入門』は買ってから半年以上もツンドク状態だった。母の介護で読むのをすっかり忘れていたからだ。介護から解放されたいま、時間を与えてくれた母に感謝するとともに、自分に残された時間の有効な活用を、まずは読書に充てようかと思っている。

























