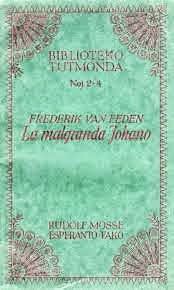Fasebook, Twitter, Line などなどいわゆる SNS の隆盛になかなか着いていけないでいるが、最近「note」という新しい SNS を知った。試しに読書ノートとエスペラントによる自己紹介を書いてみた。するとFacebookno の「いいね」のようなものだろうか「スキ」というのが1日で10個ほどもついたのだ。これをつけた人たちの note を一つ一つ見てみたが、エスペラントをやっているらしい人が一人だけいた。後の大部分は、自分の note へのアクセスを増やすために「スキ」をつけただけらしい。中にはこれで収入を得ようとしている人も見られる。note 自体が、そういうものらしい。これからも時々こちらにも書いてみようと思うが、メインはこのブログなので、これからもよろしく、である。
さて、今回の読書ノートは Julian Modest のエスペラント原作犯罪小説である。推理小説ではない。探偵たちも登場するが、特に優れた推理力を発揮するわけでもなく、殺人事件を捜査するうちに新しい事実が明らかになって、犯人が自然にわかってしまう。探偵小説・推理小説が好きな人には物足りないかもしれない。
エスペラン文は割に平易で読みやすい。エスペラント初心者にもお勧めである。2019年発行とずいぶん新しい作品なので、日本語訳はないと思う(そもそもエスペラント原作文学の日本語訳はあまりないと思うのだが)。
作者の Julian Modest は1952年生まれのブルガリアのエスペランチストである。1973年、ソフィアの大学生だった頃にエスペラントを学び、大学時代に早くもエスペラントで作品を発表している。1977年、ハンガリーのブダペストに移住、ハンガリーのエスペランチストと結婚、エスペラントで小説を発表。その後、ブルガリアエスペラント協会の出版部門編集長や会長を務める。1983年、リディア・ザメンホフの晩年を描いた戯曲「Ni vivos!」を発表、その後小説を次々に発表している。現代エスペラント界を代表する作家の一人である。