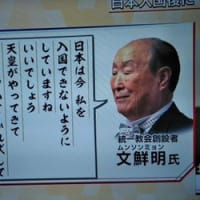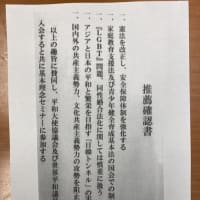GHQ焚書図書開封 第62回
第62回:戦争の原因は対支経済野望だった
出演:西尾幹二
平成22年10月13日 放送

■ 今回のご本
日米戦う可きか
出版社:世界知識増刊
発行年:昭和7年
前回に続き『日米戦う可きか』。
昭和6年に満洲事変が起った後、日米戦うべきか等、日米~という本が増えてくる。米国の対支政策と日米戦争の可能性が取沙汰されるようになる。結局、米国との争いの中心は満洲政策だった。
そこで、アメリカの実力とはどんなものなのかの詳細が語られるようになってくる。
米国の支那進出とその将来 高木睦郎(中日実業会社副総裁)
1784年のエンプレスオブチャイナに始まる通り、支那と米国の通商の歴史は古い。しかしその後、欧州列強が支那に食い込み、アメリカは出遅れる。進出した時にはフランス、イギリス、プロイセン、ロシアが中国各地に様々な形で影響圏を設定していた。そこで、遅れて登場したアメリカは、しきりに門戸開放を言う。
その後、ロシアの侵略的行動がとどまらないため、日本とロシアが戦うこととなり、アメリカ、イギリスは日本を応援した。この行動で日本はアメリカが自分の味方のような気になったがそういうことではなく、アメリカはロシアより御しやすい日本を使っただけなのだ。
また日露戦争後にはハリマンの満鉄買収計画もあった。桂内閣が結んだハリマンとの交渉も小村寿太郎が止めたことによってダメになる。巷間、この時ハリマンの言うことを聞いていたらアメリカとの戦争はなかったんじゃないかと言う人がいるが、西尾先生はその説には否定的。なぜならその後もアメリカは満洲へ野望を強烈に持っており、次から次から自国に都合のいい提案を持ってきて、結果的に日本とロシアの利害が一致していく(日露協商時代)。
後半は、辛亥革命、第一次大戦、ワシントン会議と続く。
第一次世界大戦の結果、欧州列強が極東どころではなくなり、極東に残ったのはアメリカと日本。戦後、1921年ワシントン会議が行われる。
この会議は「ひとくちでいえばアメリカが日本を封じ込めるための会議」と西尾先生。
この間、第一次世界大戦後の対支那投資は、確かにアメリカも大きくなったが日本の伸びも著しい。貿易額との比較を見ても日本の支那にもっている関心とアメリカのそれとは比較にならないほど日本の方が大きいことが明らかになる。
■ この回はGHQ焚書図書開封6に収録されている
 |
GHQ焚書図書開封6 日米開戦前夜 |
| 西尾幹二 | |
| 徳間書店 |
■ 感想
日米が満洲を巡って、そしてその後支那本土を巡って争う関係になっていく様子がコンパクトにまとまっていった回だった。
当時の感覚からすると、アメリカは最初は日本の味方のような付き合いをしていたのに段々と敵になっていくその様子に日本としては憤懣やる方なかったんだろうなと思う。また、アメリカはもっともおいしいところは自分が浚いたいが、日本をとことんまでは苛めない。それはシナの秩序の維持は日本にやらせておく必要があったからでこれはイギリスも同じだ、と著者は述べている点も重要な指摘だろうと思う。要するに最初欧州、次にアメリカが支那に利益を持つようになるが、本国から遠い以上一定以上の関与はできない。一方で辛亥革命以来支那は混乱している。そこで日本人に番犬になってもらいましょうというスキームだった、と。
憤慨するのも最もだけど、しかしワシントン会議の重要性はもっと述べられてもよかったようにも思う(西尾先生が読み飛ばしたのかもしれないけど)。この会議の直接の議題ではないが、この会議と並行して日英同盟の終了が確認されたことも重要。
で、日英同盟の終了について、それはアメリカが日本を蹴落としたかったからという意図のみで語られることが多いのだが、ここはもう少し丁寧に見るべきなんじゃないかと私は思う。つまり、それは確かにそうなのだが、イギリスの方も第一次世界大戦中の日本の行動についてイギリスの識者、関係者たちは不満に思っており、世論も不評だったため同盟を維持できなくなっていたという事情も一方にある。ドイツ、フランス、ロシアもそれぞれ別の理由で日本に対する心象を悪化させていく。
つまり、日本は明治維新以来イギリスの外交、技術、ドイツの学術、技術を柱にして育ってきたわけだけど、第一次世界大戦を境に欧州側との関係が冷たくなっていく。しかし残ったアメリカと暖かい関係かといえばそうではないから、ここで孤立化していったと言うべきなんだろうと思う。その上で満洲事変がある。この流れをこの当時の日本はどのぐらい認識していたのだろうか。
おそらく、外交関係者と軍+国民の認識が乖離していくポイントがこのへんだったのではなかろうか。
■ 参考記事
30年代に出版されたユダヤ関係の本を読んだ
戦間期の日本軍の動きはまだよくわかっていない