大河ドラマ「八重の桜」。このたびは、周囲からの
逆風にもめげずに八重が新島襄と結婚し、同志社
英学校を開校したという話であった。
時代は、八重と襄が結婚した時点で1876年1月。
新島八重31歳、山本覚馬48歳であった。
このたび、襄たちが同志社英学校を開校したのは
高松保実なる公家の旧宅であったが、襄たちに
とってこの場所はあくまでも仮の場所、襄たちは
開校前から別の候補地を探していた。そして
見つけたのが、かつて山本覚馬が閉じこめられて
いた旧薩摩藩邸の跡地であった。しかしながら、
資金面での問題などで購入できなかったため、
藩邸跡地で開校することはかなわなかった。
襄たちが藩邸跡地への移転を実現させるのは、
1876年9月のことであったという(『時代を駆ける
新島八重』による)。いっそのこと、京都ではなく
長崎あたりに移ってしまえば、風当たりはそれほど
強くならなかったかもしれない。しかしながら、
京都の人間や勝海舟からムリだと言われた襄のこと、
むしろそれで、京都での開校を絶対に実現させるの
だと意地になったのではないのだろうか。
(ドラマの襄を見てるとそういう印象は受けないが)
いずれにしても、周囲の逆風をはねのけて結婚し、
キリスト教の学校を運営していこうというのだから、
その絆が深くならないはずがなかろう。
これは次回でとりあげられるのかもしれないが、
私にとって驚くべきは、八重と襄が結婚した同年に
なんと八重の母・佐久が66歳の高齢にして洗礼を受け、
2年後には同志社女学校の舎監にもなっていた事だ。
八重の場合はまだまだ若いし、単に男とくっつきたい
一心で受洗もできるだろうという解釈も成り立つ
(それが当時の女性としてはとても思い切った行動
だったにせよ、少なくとも佐久と違って八重には
受洗の必要性があったと言えるのではないだろうか)。
また、八重を賢く導いていった兄の覚馬でさえ、
キリスト教の価値は早くから認めつつも、実際に
キリシタンになったのはこれからまだ9年も先のこと
であった。それにひきかえ、八重の母・佐久は
八重よりもずっと高齢にもかかわらず、覚馬よりも
受洗のタイミングが早いのである。
受洗などしなくたって「母」は務まるはずだが――
佐久はそうは考えなかったということだろうか、
それとも八重に刺激されて、自分も「母」を務める
だけでは飽き足らなくなっていたのだろうか。
それにしても、このたびの槇村正直の発言で興味
深かったのは、「(キリスト教に反感を持つ者たちを)
なだめすかすのが大変だからいい加減にしてくれ」と
いった趣旨のものである。この期に及んでようやく
私は理解したが、彼はただ単に面倒に巻きこまれて
自分のキャリアに傷がつくのを恐れている。
前回の私は勘違いしていたが、中央政界の重鎮たちが
もともと「天皇絶対教」の信徒であることと、
槇村正直がキリスト教を嫌っていることは、直接
関係ないということが分かったのだ。
中央政界の重鎮たちはもともと「天皇絶対教」の
信徒で、そうだからこそ、欧米列強が脅威となった
幕末においても「一人の売国奴も出な」かった。
しかし、ウィキペディアの日本キリスト教史の項を
見てみると、明治初期から中期にかけての国は
むしろ欧化政策を進めており、よって西欧精神の
中枢であるキリスト教に関心を持つ者も(主に
上流階級のあいだで)増えていたのだそうである。
槇村正直は、ただ単にキリスト教に対する世間の
偏見と、襄たちとの板挟みに悩まされていたという
ことになるのかもしれない。
世間は、覚馬や八重たちのように柔軟で勇気ある
人たちばかりではない。――そう思うと、
槇村正直もちょっとかわいそうな気もしてくる。
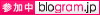 ←ランキングにも参加しています
←ランキングにも参加しています
逆風にもめげずに八重が新島襄と結婚し、同志社
英学校を開校したという話であった。
時代は、八重と襄が結婚した時点で1876年1月。
新島八重31歳、山本覚馬48歳であった。
このたび、襄たちが同志社英学校を開校したのは
高松保実なる公家の旧宅であったが、襄たちに
とってこの場所はあくまでも仮の場所、襄たちは
開校前から別の候補地を探していた。そして
見つけたのが、かつて山本覚馬が閉じこめられて
いた旧薩摩藩邸の跡地であった。しかしながら、
資金面での問題などで購入できなかったため、
藩邸跡地で開校することはかなわなかった。
襄たちが藩邸跡地への移転を実現させるのは、
1876年9月のことであったという(『時代を駆ける
新島八重』による)。いっそのこと、京都ではなく
長崎あたりに移ってしまえば、風当たりはそれほど
強くならなかったかもしれない。しかしながら、
京都の人間や勝海舟からムリだと言われた襄のこと、
むしろそれで、京都での開校を絶対に実現させるの
だと意地になったのではないのだろうか。
(ドラマの襄を見てるとそういう印象は受けないが)
いずれにしても、周囲の逆風をはねのけて結婚し、
キリスト教の学校を運営していこうというのだから、
その絆が深くならないはずがなかろう。
これは次回でとりあげられるのかもしれないが、
私にとって驚くべきは、八重と襄が結婚した同年に
なんと八重の母・佐久が66歳の高齢にして洗礼を受け、
2年後には同志社女学校の舎監にもなっていた事だ。
八重の場合はまだまだ若いし、単に男とくっつきたい
一心で受洗もできるだろうという解釈も成り立つ
(それが当時の女性としてはとても思い切った行動
だったにせよ、少なくとも佐久と違って八重には
受洗の必要性があったと言えるのではないだろうか)。
また、八重を賢く導いていった兄の覚馬でさえ、
キリスト教の価値は早くから認めつつも、実際に
キリシタンになったのはこれからまだ9年も先のこと
であった。それにひきかえ、八重の母・佐久は
八重よりもずっと高齢にもかかわらず、覚馬よりも
受洗のタイミングが早いのである。
受洗などしなくたって「母」は務まるはずだが――
佐久はそうは考えなかったということだろうか、
それとも八重に刺激されて、自分も「母」を務める
だけでは飽き足らなくなっていたのだろうか。
それにしても、このたびの槇村正直の発言で興味
深かったのは、「(キリスト教に反感を持つ者たちを)
なだめすかすのが大変だからいい加減にしてくれ」と
いった趣旨のものである。この期に及んでようやく
私は理解したが、彼はただ単に面倒に巻きこまれて
自分のキャリアに傷がつくのを恐れている。
前回の私は勘違いしていたが、中央政界の重鎮たちが
もともと「天皇絶対教」の信徒であることと、
槇村正直がキリスト教を嫌っていることは、直接
関係ないということが分かったのだ。
中央政界の重鎮たちはもともと「天皇絶対教」の
信徒で、そうだからこそ、欧米列強が脅威となった
幕末においても「一人の売国奴も出な」かった。
しかし、ウィキペディアの日本キリスト教史の項を
見てみると、明治初期から中期にかけての国は
むしろ欧化政策を進めており、よって西欧精神の
中枢であるキリスト教に関心を持つ者も(主に
上流階級のあいだで)増えていたのだそうである。
槇村正直は、ただ単にキリスト教に対する世間の
偏見と、襄たちとの板挟みに悩まされていたという
ことになるのかもしれない。
世間は、覚馬や八重たちのように柔軟で勇気ある
人たちばかりではない。――そう思うと、
槇村正直もちょっとかわいそうな気もしてくる。
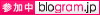 ←ランキングにも参加しています
←ランキングにも参加しています









