先日gooブログで「アクセス解析体験キャンペーン」が
おこなわれていて、そのおかげで私も自分のどの記事が
よく読まれているのかを特別に知ることができた。
(gooブログを有料で使用してれば常に知ることができるの
だろうが、私は無料で使用しているので、こうした機会が
無いと知ることができない)。
私のブログ内でよく読まれている記事の一つに
アルゼンチン・タンゴの名曲「ジーラ・ジーラ」に
関する記事があったが、その記事を再読してみると
どうも日本語の歌詞を詳細に載せてなかったようなので
このたびそれだけここで引用したい。
なお、引用元は『世界の名曲とレコード ラテン・
フォルクローレ・タンゴ』(著:永田文夫 誠文堂新光社
昭和52年)である。
訳詞:
石ころだらけの運命が、おまえをしくじりにしくじらせ、
途方にくれたまま突き放す時、うまく道に乗っかっても、
行くあてもなく、おまえが絶望している時、
信ずるものもなく、陽に干した昨日のマテ茶もなくなった
時、糊口をしのぐはした銭を求めて、おまえがわらじを
すりへらす時、つんぼでおしの世の冷たさを今こそ
おまえは悟るだろう。
☆すべてがいつわりで、愛もむなしく、
世間にとってはなんの関係もないのだと知るだろう。
ジーラよ、ジーラよ。たとえ人生がおまえを踏みにじり、
苦しみがおまえをさいなもうとも、決して助けを
待ってはいけない。ひとつの手をも、好意さえも・・・。
おまえが抱かれて死ぬために、兄弟の胸をさがしつつ、
押す呼び鈴のすべての電池がかわいている時、
私にしたのと同じように、世間がおまえを貧乏暮らしの
そのあとで放り出して捨て去る時、
おまえの手放そうとする服を人が試しに着てみるそばで、
おまえがメシにありつく時、おまえは思い出すだろう。
いつか疲れて泣き出した、このお人好しのことを・・・。
引用元の訳詞は、ここで終わっている。
――が、私の記憶が正しければ、☆以下の歌詞が
この後また繰り返されるはずである。
なお、私はこのタンゴの他に、お気に入りのものとして
「El lloron (泣き虫)」もとりあげたことがあるが、
これも日本語の歌詞の詳細は載せていなかった。
先に引用した本にもこの歌の訳詞はついているのだが、
私の手持ちのCDに書かれたもののほうが
スッキリとまとまった訳になっているし、
CDの訳は同じ永田文夫さんによるものらしいので、
CDのほうから引用したいと思う。
訳詞:
おれ様は恋にかけてはとっても弱い
女を征服するためには
時々涙を見せてやらなくっちゃ
惚れさせるにゃ、泣き虫のふりをするのだ。
今日、みんなはおれに言う:
「何言ってるんだい? 泣き虫」と。
何て言われたって、分っているのさ
恋にかけちゃ、泣き虫でなけりゃ
決してうまくいかないって…。
(2度くりかえす)
泣き虫!
何て言われたって気にしない。
泣き虫!
時には一番モテる奴が泣くのさ。
泣き虫!
おれにとっちゃ、どんな男も同じこと
結局おれが一番なんだから…。
おれは北部の鉢雀
踊りのステップは免許皆伝
公園でもサロンでもしゃべりまくり
ダンスを躍らせりゃ、まるでコマみたい。
どんな相手にも弱みを見せずに、
おれはうたう、「フロールかい?」じゃ全部賭けよう
このおれは、恋にかけては口先だけの甘いシロップ。
注意しろ、おれ様のお通りだい!
(※フロールとは、トランプの手、フラッシュのこと
だそうである)
――思えば、山本リンダさんの持ち歌
「狙いうち」に似たニオイがする歌である。
本に書かれた訳詞の一人称は「おれ様」ではなく
「ぼく」になっているが、歌詞の内容からすると
やはり「おれ様」がふさわしいように感じる。
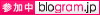 ←ランキングにも参加しています
←ランキングにも参加しています
おこなわれていて、そのおかげで私も自分のどの記事が
よく読まれているのかを特別に知ることができた。
(gooブログを有料で使用してれば常に知ることができるの
だろうが、私は無料で使用しているので、こうした機会が
無いと知ることができない)。
私のブログ内でよく読まれている記事の一つに
アルゼンチン・タンゴの名曲「ジーラ・ジーラ」に
関する記事があったが、その記事を再読してみると
どうも日本語の歌詞を詳細に載せてなかったようなので
このたびそれだけここで引用したい。
なお、引用元は『世界の名曲とレコード ラテン・
フォルクローレ・タンゴ』(著:永田文夫 誠文堂新光社
昭和52年)である。
訳詞:
石ころだらけの運命が、おまえをしくじりにしくじらせ、
途方にくれたまま突き放す時、うまく道に乗っかっても、
行くあてもなく、おまえが絶望している時、
信ずるものもなく、陽に干した昨日のマテ茶もなくなった
時、糊口をしのぐはした銭を求めて、おまえがわらじを
すりへらす時、つんぼでおしの世の冷たさを今こそ
おまえは悟るだろう。
☆すべてがいつわりで、愛もむなしく、
世間にとってはなんの関係もないのだと知るだろう。
ジーラよ、ジーラよ。たとえ人生がおまえを踏みにじり、
苦しみがおまえをさいなもうとも、決して助けを
待ってはいけない。ひとつの手をも、好意さえも・・・。
おまえが抱かれて死ぬために、兄弟の胸をさがしつつ、
押す呼び鈴のすべての電池がかわいている時、
私にしたのと同じように、世間がおまえを貧乏暮らしの
そのあとで放り出して捨て去る時、
おまえの手放そうとする服を人が試しに着てみるそばで、
おまえがメシにありつく時、おまえは思い出すだろう。
いつか疲れて泣き出した、このお人好しのことを・・・。
引用元の訳詞は、ここで終わっている。
――が、私の記憶が正しければ、☆以下の歌詞が
この後また繰り返されるはずである。
なお、私はこのタンゴの他に、お気に入りのものとして
「El lloron (泣き虫)」もとりあげたことがあるが、
これも日本語の歌詞の詳細は載せていなかった。
先に引用した本にもこの歌の訳詞はついているのだが、
私の手持ちのCDに書かれたもののほうが
スッキリとまとまった訳になっているし、
CDの訳は同じ永田文夫さんによるものらしいので、
CDのほうから引用したいと思う。
訳詞:
おれ様は恋にかけてはとっても弱い
女を征服するためには
時々涙を見せてやらなくっちゃ
惚れさせるにゃ、泣き虫のふりをするのだ。
今日、みんなはおれに言う:
「何言ってるんだい? 泣き虫」と。
何て言われたって、分っているのさ
恋にかけちゃ、泣き虫でなけりゃ
決してうまくいかないって…。
(2度くりかえす)
泣き虫!
何て言われたって気にしない。
泣き虫!
時には一番モテる奴が泣くのさ。
泣き虫!
おれにとっちゃ、どんな男も同じこと
結局おれが一番なんだから…。
おれは北部の鉢雀
踊りのステップは免許皆伝
公園でもサロンでもしゃべりまくり
ダンスを躍らせりゃ、まるでコマみたい。
どんな相手にも弱みを見せずに、
おれはうたう、「フロールかい?」じゃ全部賭けよう
このおれは、恋にかけては口先だけの甘いシロップ。
注意しろ、おれ様のお通りだい!
(※フロールとは、トランプの手、フラッシュのこと
だそうである)
――思えば、山本リンダさんの持ち歌
「狙いうち」に似たニオイがする歌である。
本に書かれた訳詞の一人称は「おれ様」ではなく
「ぼく」になっているが、歌詞の内容からすると
やはり「おれ様」がふさわしいように感じる。
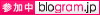 ←ランキングにも参加しています
←ランキングにも参加しています









