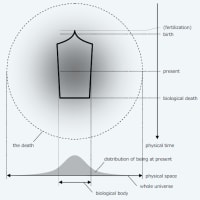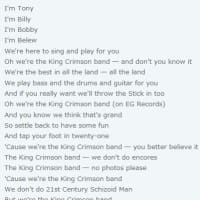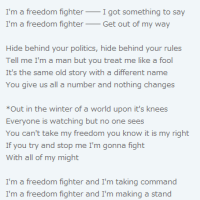| 匪賊の社会史 (ちくま学芸文庫) エリック・ホブズボーム著 船山榮一訳 筑摩書房 Amazon / 7net |
この本は訳者船山榮一氏が「斎藤三郎」の筆名で訳し、みすず書房から刊行されていた本の文庫化である。原書は1969年刊で、訳書も1972年に出て、長いこと絶版であったものが、(たぶん)ネタ切れに悩んでいるちくま学芸文庫から文庫化復刊の運びとなったものらしい。つまり、ムチャクチャ大昔の本なのである。訳者の生年を見たら実にわたしの父親より年上の人であった。
ネタがないのでもう何でも出してしまえという事情は確かにあるのだろうが、しかしこの本は文句なしに面白い。文庫化で判型は小さくなったが、一方では版も書体も新しくなっているわけで、みすず書房の本のあの(特に昔のは)クソ古い読みにくい、つまらない本でも何やらひどく難解に思えてきてしまう、あの書体に難儀しながら読まなくていいというだけで、ごく真面目な社会史の研究書がちょっとしたエンタテインメントのように読めてしまう。
内容はまったく題名の通りだが、そもそも匪賊(bandits)とは何のことかといって、典型的にはロビン・フッドのような義賊のことである。もちろんこの本にはそのロビン・フッドの話も出てくるが、それだけではない、義賊とは到底呼べないただの悪党みたいなもの、現代世界ではマフィアとかヤクザとかの扱いしか受けないであろうような反社会性の犯罪者集団みたいなものも陸続と登場してくる(ただし東アジアのそれはほとんど出て来ない。たまに水滸伝の話が出てくる程度である)。
なんでそんなものの研究書が大真面目に存在するかといえば、この本が出た時代のことを考えてもらえばだいたいは察しがつく人もいるだろう。要は近代以後の世界では革命として組織されるような、支配権力に対する民衆的反抗や叛乱の、そうなる以前の時代と社会における形態の社会史なのである。あからさまに言えば、そうした前近代の組織が革命を引き起こすまでには至らなかったのは、そこに何が欠けていたからなのかということを、マルクス主義の強い影響を感じさせる方法論のもとで分析しているわけである。
そういう風に説明するといささかミもフタもないことになってしまうが、革命とかマルクス主義とかはまったくどうでもいい世代のわたしがこの本を読んでいると、そういう、著者の本来意図したことではないかもしれない読み方が、それもひと通りではなくできそうな気がしてくる。まず第一に、最近読んでる「正義論」などの、ほとんど想定もしていないような種類の善悪や正邪の世界が、彼らが伝説や俗謡の中でいかに賞賛されたことか、その実態や末路がどんな風に間抜けだったり、みっともないものであったことか、にもかかわらず(前近代の)さまざまな時代や社会のあちこちから性懲りもなく繰り返し現れたものであったことか、そんなことがこの本の中にはふんだんに描かれている。
また、この本の中に出てくる悪党の中には、彼らが現代のケーサツに捕まったら「ムシャクシャしてやった。誰でもよかった。反省はしていない」などと供述するであろうようなタイプも当然のように登場してくる。その種の犯罪者の心理を解き明かすと称する現代の犯罪心理学の類がどうして、どんな風にくだらない戯言の類であるかは、この本を読むと非常によくわかる気がしてくる。
さらにまた、これを読む人の中には、今まさによからぬことを企んでいる、明日にもそれを実行しようとしているワカモノがいるかもしれない。そういう人はせめてその取り返しのつかない一歩を踏み出す前に、是非この本を読むべきである。本当は自分でもよく判らない憤懣がいったい何に由来しているのか、ひょっとするとこの本が教えてくれるかもしれない。そしてその場合、その憤懣を現実にぶち撒けようとした場合の末路がどんなものか、この本はその大略を解き明かしてしまうだろう。