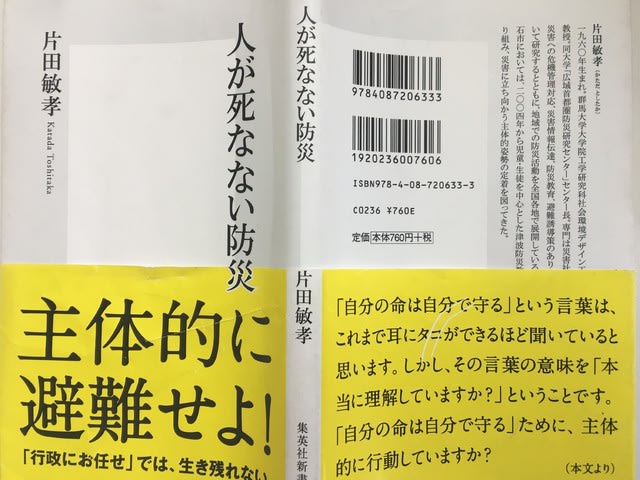激甚化する水害に備え 自分の命守る意識を!
東京大学・総合防災情報研究センター 片田敏孝特任教授
尾崎 洋二による要点・箇条書きまとめ
防災は、一人の犠牲者も出さないと決めて、地域のすべての人の命を守ることです。
そのためには、「防災の実効性を先に語るのではなく、心の有り様から防災を考える」という視点があって初めて、真の防災が達成されるのではないでしょうか?
変革すべきこと
心の有り様、災害情報の受け方、「正常性バイアス」、防災教育
- 心の有り様が他者依存になっている。
多くの人は、災害が激甚化している実態や、今の防災の課題、自助や共助が大事ということも分かっています。
しかし、不安が高まるばかりで個人レベルの対策には至らず、まだまだ行政の対応強化への要望という“他者依存”になってしまっている。
現在の日本の防災は、堤防を造るのは行政、ハザードマップで危ない所を教えてくれるのも行政、逃げろと言ってくれるのも行政、避難したらお世話をしてくれるのも行政。「あなたの命を守るのは?」と問われると、「行政」と言ってしまいかねない状況にあるのではないでしょうか。
- 他者依存になっているので、一つ一つの災害情報を、それに基づいて行動しなければならないという「行動指南」と捉えるのではなく、「一人一人が避難を考える状況ですよ」という「状況情報」として受け取っていない。
津波警報で考えてみましょう。「逃げなさい」という「行動指南」と捉えると、大きな津波が来なかった時には、「逃げなければよかった」と、少し不満な気持ちになりませんか。これを繰り返すうちに逃げなくなってしまうと、いつか必ず「逃げておけばよかった」と思う時が来てしまう。
ところが、「状況情報」と捉えて自らの判断で避難した時、実際には津波が来なかったとしても「津波が来なくてよかった」と思え、この繰り返しの先には「やっぱり逃げていてよかった」と実感する時が来ると思うのです。
要するに「空振り」と捉えるか、「素振り」と捉えるかの違いで、結果は大きく異なってくるということです。
- 「正常性バイアス(前回も大丈夫だったから、今回も大丈夫)という心理」にとらわれている。
「正常性バイアス」からの脱却には大事な人を思う時に働く心理が必要です。
人間は、大切な人のことを思うと、動けるようになるのです。
防災というのは、単に「あなたが逃げてください」ということを伝えるだけではだめだと思います。一人の犠牲者も出さないと決めて、家族や地域で話し合い、皆で生き残る方法を考えていく。つまり、“わが事”ではなく、“わが家庭事”“わが地域事”で捉えていく中で、実効性のあるものが生まれます。
- 防災教育というのは、さまざまな人たちが他者依存でなく、主体的に行動に結びつけていけるよう、10年、20年と持続的に行っていくプロジェクトでなければならない。
人間は、言葉だけでは動きません。具体的な行動に結びつけていくためにも、「共感」してもらうことが大事。
例えば、「お母さんは昼間のパート先で大地震に遭ったら、家に戻るのに10分以上はかかってしまうから、家には帰らずに近所の高台のおばさんの家に逃げるからね」とか、「学校から帰ってきた後に被災したら、隣に住んでいるおばあちゃんを連れて高台に逃げなさいね」といった話ができるかもしれません。
こうした悲観的な話は、あまりしたくないかもしれませんが、一度でいいので、きちんと家族で話し合っておく。それがいざという時の行動に直結します。だからこそ、何より大切なのは、そうした語らいを、気付いた人、つまり“自分から始めようとする”ことです。
各人が他者依存でなく主体的に行動していけば、家族や地域も変わっていきます。
子どもたちを“地域の財産”“地域を担う人材”として皆で育み、高齢者に対しても「災害なんかで死んじゃだめだ」と励ます。その中で生まれる思い合う喜びを、どんな小さなことでもいいから、積み重ねていくことです。
そうすることで、いざという災害に対して、思い合う相手に意識が向き、対応を講じることができ、その中で災害弱者という言葉もなくなっていくのではないでしょうか。
私が防災教育で大切にしているのも、そうした心を育む環境を整えることであり、防災で大事にしているのは「愛他性」「利他性」です。
防災教育実例紹介
黒潮町という地域は「南海トラフ巨大地震」が起きた際に34・4メートルという“日本一高い”津波が来ると、内閣府の中央防災会議が発表した町。
この町でのある高齢者の短歌
教育実施前
「大津波 来たらば共に 死んでやる 今日も息が言う 足萎え吾に」
教育実施後
「この命 落しはせぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」
避難を諦めていた姿勢を大きく変え、自分を思ってくれる家族や地域の人々に感謝しながら、避難訓練に参加する姿が目に浮かびます。
--------本文 聖教新聞 11月29日、30日 2022年 全文--------
激甚化する水害に備え 自分の命守る意識を:希望をつくる――災害と“心の復興”〉
東京大学・総合防災情報研究センター 片田敏孝特任教授へのインタビュー
災害に向き合う人々の生き方を通して、人生の希望を生み出す方途を探ってきた本企画「希望をつくる――災害と“心の復興”」。今回は「水害への備え」をテーマに、東京大学・総合防災情報研究センターの片田敏孝特任教授に、日本で多発する水害の現状や、その中で自らの命を守るために必要な視点を聞いた。(聞き手=水呉裕一、加藤伸樹。)
〈近年、水害が激甚化しており、その要因として地球温暖化が指摘されています〉
今月20日まで、エジプトでCOP27(国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議)が行われましたが、温暖化対策は待ったなしの状態です。
私は、地球温暖化は、大きく三つの観点で水害発生のリスクを高めたと考えています。
一つ目は、雨量の増加です。今年、海水温の高さは観測史上最悪を記録しましたが、温暖化によって海水温が高くなると、水蒸気がたくさん出るようになります。
加えて、大気が温まると当然、空気中に蓄えられる水蒸気量も多くなります。この大量の水を含んだ空気が列島に押し寄せることで、これまででは想像できないほどの雨を降らせているのです。
熊本を中心に甚大な被害をもたらした「令和2年7月豪雨」では、大気中の水蒸気量が信濃川の水量の800倍、アマゾン川の2倍にも達していたといわれます。
二つ目は、台風の巨大化です。海水温の上昇は、台風の発生や巨大化を助長させることが知られています。以前の台風は日本列島に近づくにつれて海水温が下がるため、勢力も弱まっていましたが、今は海水温が高いので、勢力を維持したまま上陸するようになったのです。
今年9月に九州地方を襲った台風14号の中心気圧は、910ヘクトパスカルでした。
1934年の室戸台風は日本上陸時点で911ヘクトパスカル、59年の伊勢湾台風は929ヘクトパスカルでしたので、この910という数字がいかに記録的なものかが分かるでしょう。
三つ目は、その台風が日本近海で発生するようになってきた点です。海水温が高くなるにつれて緯度の高いところでも台風が発生し、近年は、発生翌日には日本に接近することもあります。
本年9月に静岡などで大きな被害をもたらした台風15号もそうでした。接近までの時間が短い分、災害に備える時間が取れなくなってきているのです。
他者依存を排して
〈日本は毎年のように水害に見舞われていますが、日本全体で人々の防災意識は高まっていると思いますか〉
結論から言うと、あまり高まっていないと思います。もちろん、多くの人は、災害が激甚化している実態や、今の防災の課題、自助や共助が大事ということも分かっています。しかし、不安が高まるばかりで個人レベルの対策には至らず、まだまだ行政の対応強化への要望という“他者依存”になってしまっているように感じます。
現在の日本の防災は、堤防を造るのは行政、ハザードマップで危ない所を教えてくれるのも行政、逃げろと言ってくれるのも行政、避難したらお世話をしてくれるのも行政。「あなたの命を守るのは?」と問われると、「行政」と言ってしまいかねない状況にあるのではないでしょうか。
〈なぜ、そうした状況になってしまったのでしょうか〉
それは社会全体の流れでもあったように思います。
日本は自然が豊かな国です。大昔は、海は荒れ、川は暴れるものだと考え、みんなで助け合いながら自然と向き合っていくというのが、日本の文化でした。それが堤防などを造って一定の災害を防げるようになると、いつしか人々の中に「災害制御可能感」のようなものや“ゼロリスク”を追究する心が生まれ、“行政が堤防を造れば守られる”“災害は起こらないもの”といった認識に立つようになってしまったのではないでしょうか。
そうしたものは、新型コロナウイルスが流行した当初にもあったように思います。最初は世界各国で完全にウイルスの拡大を抑え込もうとしましたが、それができないと分かり、結局は、自分がマスクを着用し、自分が3密を避けるということが自分の命を守る一番の方法だと気付きました。これは自然災害においても同じで、どれだけハード面を整備しても、それを超えてくることがあるので完全に抑えることはできませんし、最後は自分の命は自分で守る以外にありません。
「ウィズコロナ」という言葉が生まれたのと同じように、防災においても「ウィズ災害」という心構えで、いつ想定以上の事態が起こったとしても、自分の身を守っていける意識を高めていかなければならないと思います。
その上で、防災は、どう備えたかが如実に結果として表れますので、一つでも二つでも行動に移していくことが大事です。
情報を軽んじない
〈自らの命を守るためにも、「正しい情報」が大切です。
災害時にそうした情報をつかむために注意すべき点を教えてください〉
情報を出す気象庁などでは、正しい情報を迅速に出そうと努力しています。しかし、それがなかなかできないのが現実です。
例えば、豪雨災害は「線状降水帯」がキーワードとなっていますが、微妙な気圧配置や地形によって偶発的に生じることから、極めて予測が難しいのです。
そんな中でも、本年6月から気象情報として、この線状降水帯の発生予測を伝えるようになりました。しかし、まだ全国を11ゾーンに分け、その中のどこかで発生する可能性があるということしか伝えることができず、防災情報として活用できるところまでは至っていません。
土砂災害の情報もそうですが、2009年から19年の間のデータで見ると、「土砂災害警戒情報」という「避難指示」相当の情報が出ても、実際に土砂災害が起きたのは5%以下で、20回に1回当たるかどうかです。
そうした意味では、「正しい情報」というものは、現状ではないのかもしれません。
しかし、この土砂災害において言えば、実際に災害が起こった現場で「土砂災害警戒情報」が出ていたのかどうかを見ると、9割以上の地域に出されていたことが分かっています。
もちろん、20回に1回という確率を上げていく努力は必要ですが、現在でも20回に1回は当たっているからこそ、警戒情報を決して軽んじることなく、自分の命を守る行動につなげていくことが大切であると思います。
〈一回一回の災害情報を軽んじないためにも、一人一人の意識変革が大切ですね〉
そのためにも、一つ一つの災害情報を、それに基づいて行動しなければならないという「行動指南」と捉えるのではなく、「一人一人が避難を考える状況ですよ」という「状況情報」として受け取っていくことではないでしょうか。
津波警報で考えてみましょう。「逃げなさい」という「行動指南」と捉えると、大きな津波が来なかった時には、「逃げなければよかった」と、少し不満な気持ちになりませんか。これを繰り返すうちに逃げなくなってしまうと、いつか必ず「逃げておけばよかった」と思う時が来てしまう。
ところが、「状況情報」と捉えて自らの判断で避難した時、実際には津波が来なかったとしても「津波が来なくてよかった」と思え、この繰り返しの先には「やっぱり逃げていてよかった」と実感する時が来ると思うのです。
要するに「空振り」と捉えるか、「素振り」と捉えるかの違いで、結果は大きく異なってくるということです。
毎年のように観測史上最大という雨が降る今、「これまで大丈夫だったから、今回も大丈夫」という保証はありません。行政がいくらハザードマップを作ろうが、それを超える災害が起きるということを理解し、自分がどう行動するかということが大切です。
今まで通りの避難を心掛けることを前提とした上で、その想定も超えることがあると認識し、一人一人が最善を尽くすしかないと思います。
“わが家庭事”と捉える。
〈「前回も大丈夫だったから、今回も大丈夫」という心理に陥らないために、どのようなことを意識すればいいのでしょうか〉
こうした心理は「正常性バイアス」といわれます。災害時の最大の敵は、この正常性バイアスと捉えている人も少なくありませんが、自分に降りかかる不運をあえて直視しないことは、ある意味で、人間が穏やかに生きていくために備えている機能だと思います。しかし、それを乗り越えていかないといけません。
そこで私が着目するのは、大事な人を思う時に働く心理です。
例えば、かつて子どもたちに「津波が来たら逃げるか」と聞いたところ、「おじいちゃんもおばあちゃんも逃げないから、逃げない」と答えられることがありました。それを踏まえ、今度は、そのおじいちゃん、おばあちゃんに、こういう話をしました。
「お孫さんたちは、皆さんの背中を見ています。いざという時、お孫さんたちの命を奪うのは、もしかしたら、皆さんの背中なのではないか」
すると、おじいちゃん、おばあちゃんの目の色が変わりました。自分のことだったら横に置いてしまうが、孫の命がかかっていると感じ、孫と一緒に逃げようという気持ちになってくれたのです。人間は、大切な人のことを思うと、動けるようになるのです。
私は、防災というのは、単に「あなたが逃げてください」ということを伝えるだけではだめだと思います。一人の犠牲者も出さないと決めて、家族や地域で話し合い、皆で生き残る方法を考えていく。つまり、“わが事”ではなく、“わが家庭事”“わが地域事”で捉えていく中で、実効性のあるものが生まれていくと考えています。
利他性こそ地域を守る鍵
家族や地域の人々を守るために必要な視点を語ってもらった。(聞き手=水呉裕一、加藤伸樹)
〈自分の命だけでなく、家族や地域の人々の命を守るためには、全体で防災意識を高めていくことが大切だと思います。そのためにも防災教育は欠かせません〉
その通りです。しかし、その防災教育は「座学」であると考えている人が多いのではないでしょうか。
防災に必要な知識を教え、「分かりましたか」と聞くと、「分かりました」と言ってくれます。しかし、それで実際に行動できるようになれるかは別問題です。
私はよく交通安全教室のことを引き合いに出しますが、「右を見て、左を見て、手を上げて横断歩道を渡りましょう」と教え、子どもたちは正直に「はい」と言ってくれます。しかし、街に出れば、大人たちは誰もやっていないので、子どもたちも次第に「やらなくていいものだ」ということを学んでしまうのです。
それと同じで、学校でどれほど災害の恐ろしさや、災害時に逃げる大切さを教えたとしても、それを社会の中で実践している人がいるか、その学んだことを育んでいける環境があるかということの方が、より大切だと思うのです。
だからこそ、防災教育というのは、さまざまな人たちが行動に結びつけていけるよう、10年、20年と持続的に行っていくプロジェクトでなければならないと感じます。
大事なのは「共感」
〈片田特任教授が、防災教育において大切にしている点は何ですか〉
人間は、言葉だけでは動きません。具体的な行動に結びつけていくためにも、「共感」してもらうことが大事だと感じます。
私は2004年から10年近く、岩手県釜石市の防災教育に携わってきました。その中で、私は子どもたちに、こんな質問をしてきました。
「家の外で大地震に遭ったとき、津波が来る前に、すぐ逃げますか」と。
すると、彼らは「逃げる!」と元気に答えてくれます。私は、さらに尋ねます。
「じゃあ、みんなが逃げた後、君たちのご両親は、どうするだろう?」
その途端、子どもたちの表情が曇り、「僕たちのことを迎えに来ちゃう」と答えます。
私は続けます。「そりゃそうだよ。みんなのお父さん、お母さんは自分の命よりも君たちの命の方が大事なんだから。だから、君たちが、ちゃんと『逃げる子』になることが大切だよ。それを、ご両親が信じてくれていれば、迎えに来ないよ」と。
そこまで話をして、私は彼らに宿題を出します。両親に、自分が「逃げる子」だということを分かってくれるまで、家で語らいの場を持つというものです。
その語らいの中で、子どもたちは両親の愛情に触れ、家族の絆を学びます。そして、自分の命を守ることが、家族の命を守ることにつながるということに気付くのです。
そうした中、2011年に東日本大震災が起きました。釜石市でもたくさんの津波犠牲者が出てしまいました。しかし、多くの小・中学生は自らの命を守り抜くために懸命に避難し、周りの大人や高齢者などの命も守ってくれました。ここまでたくましく育ってくれた子どもたちのことを、私は誇りに思っています。
東日本大震災の際、津波は同校の校舎の屋上を超える高さだったが、児童は逃げ切り、自らの命を守り抜いた。
いざという時には
〈やはり、いざという時のために、家族で語り合っておくことが重要ですね。家庭で防災の話をする際のポイントを教えてください〉
ハザードマップなどを活用しながら、さまざまなシチュエーション(状況)を想定し、非常時にどう行動するかを、現実感をもって話し合うことが大切です。
例えば、「お母さんは昼間のパート先で大地震に遭ったら、家に戻るのに10分以上はかかってしまうから、家には帰らずに近所の高台のおばさんの家に逃げるからね」とか、「学校から帰ってきた後に被災したら、隣に住んでいるおばあちゃんを連れて高台に逃げなさいね」といった話ができるかもしれません。
こうした悲観的な話は、あまりしたくないかもしれませんが、一度でいいので、きちんと家族で話し合っておく。それがいざという時の行動に直結します。だからこそ、何より大切なのは、そうした語らいを、気付いた人、つまり“自分から始めようとする”ことです。
主体性を持つ大切さ
〈各人が主体的に行動していけば、家族や地域も変わっていきますね〉
最近も、主体性を持つ大切さを実感した出来事がありました。
現在、高知県の黒潮町という地域の防災に携わっていますが、先日はこの町の防災シンポジウムで、小学5・6年の児童が「簡易トイレ」などの防災グッズの使い方を自ら学んで、地域の大人たちに説明してくれました。「大人たちは、きっと防災グッズの使い方を知らないから、僕たちが勉強して教えてあげる」と言って(笑い)。
また、避難所開設訓練も行い、受付の場所は「ここがいいんじゃないか」「こんなことに注意しないといけないよ」などと言いながら、説明してくれました。
子どもたちが地域のことを考えてくれたことに、その場にいた大人たちは皆、うれしそうでした。私も、自ら進んで学び、実践してくれていることが本当にうれしかった。
実は、この黒潮町という地域は「南海トラフ巨大地震」が起きた際に34・4メートルという“日本一高い”津波が来ると、内閣府の中央防災会議が発表した町なのです。
津波想定が出されてから、黒潮町は巨大な避難タワーを整備したり、避難路を整備したりと、できる限りの検討や対策を行いました。
しかし、高齢者を中心に避難を諦めてしまう人が出始めてしまいました。
ある高齢者は、このような短歌を詠みました。
「大津波 来たらば共に 死んでやる 今日も息が言う 足萎え吾に」
どんなに津波への対処を考えても、万全の対応策はなく、繰り返される避難訓練に参加しても、足腰の弱ったわが身をどうすることもできない。そんな絶望感の中で開き直るしかない心境と、息子さんの思いが込められています。
そんな中、地元の学校では、地域と連携して防災教育を実践するとともに、子どもたちが地域の一員として高齢者を気遣う声かけをしてくれました。
自主防災会では「地域から絶対に津波犠牲者を出さない」との決意で、高齢者に配慮した避難訓練を重ね、役場でも一軒一軒の個別避難計画を立て、避難できる手立てを一緒に考えてくれました。
そうした中、先の高齢者は、こう詠むようになりました。
「この命 落しはせぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」
避難を諦めていた姿勢を大きく変え、自分を思ってくれる家族や地域の人々に感謝しながら、避難訓練に参加する姿が目に浮かびます。
子どもたちの主体的な実践は、周囲の人の心を変え、やがては町全体の雰囲気をも変えていく。私はこの町の防災に携わる中で、地域の人々と共に生きるということが、「助かる」「助からない」という不安を超えて、むしろ喜びとなっていると感じます。
こうした、人と人との強固なつながりこそ、災害に負けない社会を築く鍵だと思えてなりません。
高知・黒潮町の各地には、「南海トラフ巨大地震」による巨大津波を想定した避難タワーが設置されている 。
皆で課題に向かう
〈そうした人々のつながりを築くために、どのようなことが必要と感じますか〉
思い合うこと、励まし合うことだと思います。
子どもたちを“地域の財産”“地域を担う人材”として皆で育み、高齢者に対しても「災害なんかで死んじゃだめだ」と励ます。その中で生まれる思い合う喜びを、どんな小さなことでもいいから、積み重ねていくことだと思います。
そうすることで、いざという災害に対して、思い合う相手に意識が向き、対応を講じることができ、その中で災害弱者という言葉もなくなっていくのではないでしょうか。
言い習わされた言葉で表現すれば、コミュニケーションなのかもしれませんが、防災の取り組みの良いところは、誰も反対する人がいないことです。皆で共通の課題に向かい合えることです。
私が防災教育で大切にしているのも、そうした心を育む環境を整えることであり、防災で大事にしているのは「愛他性」「利他性」です。
心の有り様から考える
〈「利他」の心は、私たち創価学会員も大切にしているものです〉
以前、創価学会の方々に、防災の話をさせていただいたことがありますが、私の話をストレートに理解していただいていると感じています。
学会の方々の防災への思いは、私と何も変わらないと思います。
災害や防災に関する聖教新聞の記事を読んでも、いつもぶれることなく、人の心のことを書いていますよね。
世間では、災害が起きた際に「ここをこうすべきだった」などと、防災のあり方そのものについて語られることが多い中にあって、学会では、被災した人たちを思う気持ちや、励ます気持ち、心の通い合いにスポットを当てています。
私はそうした姿勢があって、初めて防災の実効性が生まれると信じています。
防災の実効性を先に語るのではなく、心の有り様から防災を考えるということに、私は賛成です。こうした中に、本当の意味での防災力の向上があるように感じられてなりません。
〈プロフィル〉
かただ・としたか 1960年生まれ。東京大学大学院情報学環特任教授。日本災害情報学会会長。専門は災害情報学・災害社会工学。災害への危機管理対応、災害情報伝達、防災教育、コミュニケーション・デザイン等について研究するとともに、内閣府中央防災会議や中央教育審議会をはじめ、国や地方自治体の多数の委員会、審議会に携わり、防災行政の推進に当たる。著書に『人が死なない防災』『人に寄り添う防災』(集英社新書)など。