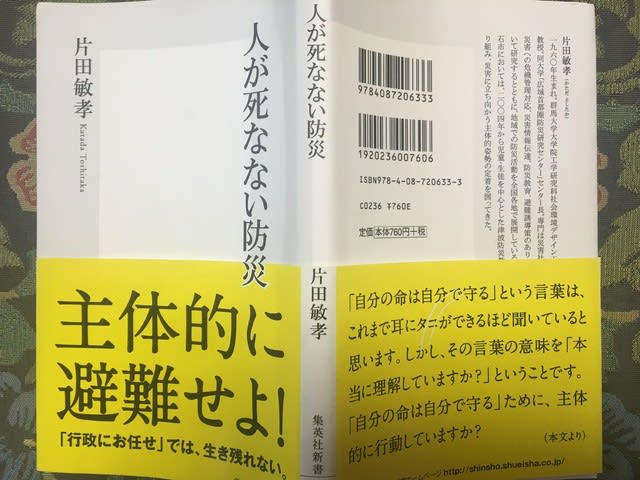避難行動の4つの指針を実践した兼信 陽二さん
1- 自分が暮らす地域の過去の災害歴や地理的な特徴を知る
2- 避難行動を起こす自分なりのルール、避難方法をあらかじめ決めておく
3- 大雨や台風のときには、自分から情報を取りに行く
4- あらかじめ決めたルール・方法に基づき、避難行動を起こす
この4指針をとにかく、ひたすら、確実に、避難行動として、実行された兼信 陽二さん(真備町川辺地区)の事例を紹介します。
----「ドキュメント豪雨災害」谷山宏典氏著から要点抜粋箇条書き------
1- 兼信 陽二さんは、川辺地区の防災活動に関わるようになったのは、2011年のこと。
2- 2010年に町内会の会長となって、まちづくり推進協議会に参加し、防災研修会や避難訓練の手伝いもするようになった。
3- 川辺地区では過去に大きな水害が起こっているので、地区外への避難が重要なことは頭ではわかっていたが、いざ大雨が降って避難準備情報などが発令されても、「まあ、大丈夫だろう」と安心しきっている自分がいた。
4- 研修会でも「近所の人に声をかけて逃げましょう」という話がたびたび出るが、自分の町内を思うと「防災に関心がない彼らに声をかけても相手にされないんじゃないか」と考えていた。そんなもやもやとした想いがずっとあった。
転機になったのは、2015年の防災研修だった。P133
1- その研修会で、釜石市の津波に関する石碑のひとつに刻まれた、地元の中学生の「100回逃げて、100回来なくても、101回目も必ず逃げて!」という言葉を教えてもらった。
2- この言葉を聞いたとき「これだ!」と腑に落ちた。
3- 避難をした結果、空振りだったとしてもいい。大事なのは、まず逃げることなんだと、素直に思えるようになった。
4- 逃げるためには、判断の基準を明確にしておこうと、ひとつには「避難勧告が発令されたら必ず逃げる」と決めた。
5- また地元でのハザードマップでは、高梁川の堤防が決壊して浸水被害が発声する雨量として「2日間で248ミリの降雨」を想定していたので、48時間降水量も避難行動に移る判断基準とした。
6- ハザードマップには、「2日間で248ミリの雨量」は「150年間に1回程度の確率」とも書いてあったので、兼信 陽二さんの中には「そこまで降ることは、まずないだろう」という想いもあった。だが、その150年に1回が現実になった。
7- そんな状況のなかでテレビニュースを見ていたら、「真備地区全域に避難勧告が発令」という情報が飛び込んできた。「2日間の累加雨量が300ミリを超える恐れもある」との予測も出た。それを見た瞬間、兼信 陽二さんは迷いなく「すぐに避難しよう」と考えた。
8- 避難をする旨を妻に伝えたら、はじめは「え~」と反対された。息子も「僕は行かないよ」と、やんわりと同行を拒否した。しかし兼信 陽二さんは、まず妻を説得し、次いで「母さんは夜、車運転しないから、代わりにお前が運転してくれ」と息子も説き伏せた。
9- 避難勧告の発令が22時で、家族3人揃って車に乗って家を出たのが22時30分頃だった。
10- 向かった先は、避難場所としてあらかじめ決めておいた、倉敷市南部の玉島乙島にある妻の実家だった。
11- そこへと至る道のりも、冠水の恐れのある道路をできるだけ避けて進んだ。
兼信 陽二さんの話でもっとも印象的だったこと p135
Q-1 避難するとき、身の危険を感じましたか?
A 避難を決断した際でも「身の危険はまったく感じていなかった」
「雨はかなり降っていたが、危険を感じるほどではなかった。どこかの堤防が決壊するとも思っていなかった。
逃げてはいるものの、危機感や切迫感はまったくといっていいほどなかった。
女房と息子に至っては半信半疑・・・いや、半信すらなかったかもしれません」
この言葉から見えてくるのは、人は危険を感じなくても、あらかじめ行動のルール(避難スイッチ:尾崎 注)を決めておけば、システマティックに避難できる事実である。
兼信 陽二さんの行動や意思決定のプロセスは、正常性バイアスの罠を回避して、逃げ遅れを防ぐひとつの有効な手段となり得る。