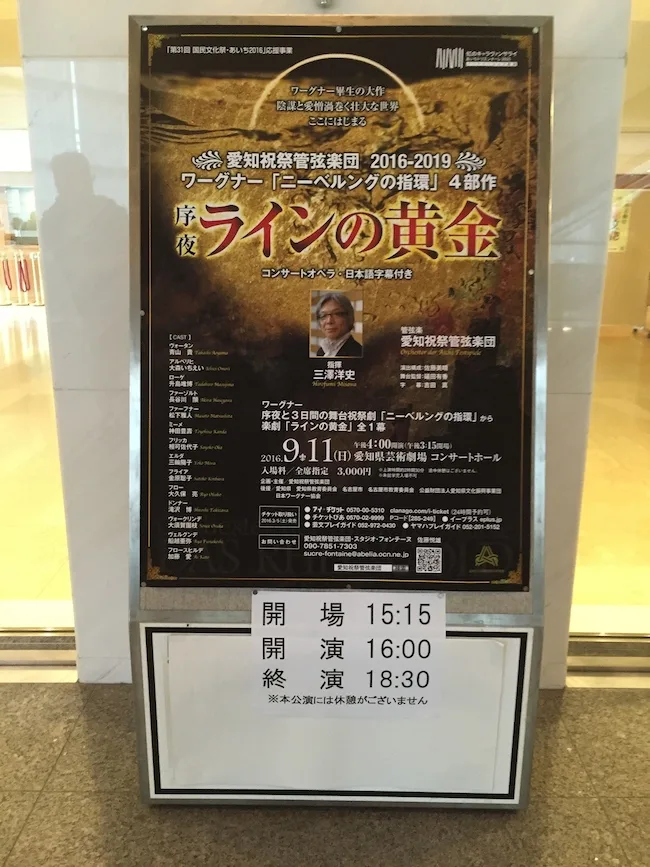昔、(そしてたぶん今も)ノンポリだった
学生時代、ベトナム戦争反対とか学費値上げ反対とかを
大きな看板に特徴のある文字を書き連ね、時にはヘルメット被って
棒を持って、拡声器で校内をアジっていた連中がいた
自分は「ノルウェーの森」の登場人物のように、その時代の雰囲気には
影響されながら、具体的には何もしない傍観者だった
でも強引に休講になった教室で行われた討論会(?)では
主催者が進める理屈に疑問というか質問をしたことがあった
それはノンポリの何も知らない、怖いもの知らず話で
「米帝国主義」とかそれに伴う日本の海外進出の姿勢を
批判していることに対して 、少なくとも貿易に関しては日本は
資源がない国で貿易で儲けようとすることは必然ではないか、、、
みたいなことを聞いた(本当に幼稚な質問?)
その答えが、どんなであったか今は覚えていない
ただ、その質問をしたことで馬鹿にされるとか
一方的に非難されることはなかった
むしろ相手にされなかった、、、という方が正確かも知れない
学費値上げについても、上がるのは嬉しくないが
あの時の国立の授業料を考えると、国民の税金を使って
そのままあの安い値段でつづけることが本当に良いことか疑問だった
自分は懸命に勉強していなかったし、モラトリアムみたいなもので
ダラダラと時間を費やしていただけだった
(でも、今で言う自分探しは必死になってやっていたかもしれない)
そこで、とりあえずいろんな経験をした今、少しばかり恥じることがある
あの時、彼らが言いたかったことを、自分は理解力がなかったために勘違いしていたということ
それは「帝国主義」という言葉
これを自分が植民地主義みたいな、スター・ウォーズの帝国みたいなものを勝手に想像していた
しかし、ある時レーニンの「帝国主義論」を読んでそれが全くの勘違いだった事がわかった
帝国主義とは、そんなドラマとなるような話ではなく、
資金の融通や両替など「ひかえめな仲介者」であった銀行は、銀行自体も独占体となり、
資金融通などや簿記を通じて産業を支配するようになる、、、
つまりは資本主義の行き着く先の混乱を説いているようなものだった
実はこの「帝国主義論」を読んだ時は、いつの時代の話だ?
と書かれた時代を確認したのだった(現代に書かれた本なのではないか、、と)
本当に、今でもそのまま通用するような話だ
だからといって、そのままノンポリを卒業するかというと、
それはなかなか簡単にそうはいかない
相変わらずの傍観者、ノンポリ
いや、少しは、変わったかな、、