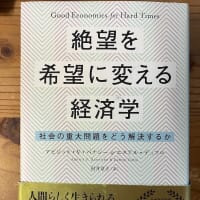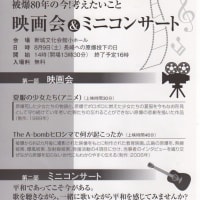江戸時代の識字率が、思いのほか高かったことが先日の本「江戸の教育力」でわかったが
昨年の大河ドラマ「光る君へ」の時代でも、宮中の女性は文字を読んだり書いたりすることができていた
一体、どのくらいの割合の人びとが文字を理解できていたのか?と疑問に思えたので
真偽は問わずに便利な道具のチャットGPTに聞いてみた
問 奈良時代、平安時代の識字率はどのくらいでしたか
答 チャットGPT
奈良時代(710〜794年)および平安時代(794〜1185年)の識字率については、
正確な統計は存在しませんが、歴史学者たちの研究に基づく推定があります。
◆ 奈良時代の識字率(710~794年)
-
ごく一部の上層階級(貴族・僧侶・官人)のみが読み書きを習得
-
識字率は1%未満と考えられています
-
仏教の経典を扱う僧侶、律令制度の文書を扱う官僚が主に文字を使用
-
農民や庶民には基本的に文字の知識は不要だった
-
◆ 平安時代の識字率(794~1185年)
-
識字層がやや拡大するが、依然として極めて限定的
-
識字率の推定は1〜5%程度
-
貴族階級(貴族女性を含む)は和歌や漢詩を書く文化があった
-
貴族の女性も仮名文字で日記文学などを記す例が増加(『紫式部日記』『枕草子』など)
-
一部の武士や地方豪族も文書作成を始めるが、庶民の識字率は依然としてほぼゼロ
-
◆ 要点まとめ
| 時代 | 識字率の推定範囲 | 主な識字層 |
|---|---|---|
| 奈良時代 | 1%未満 | 僧侶、貴族、官僚 |
| 平安時代 | 1〜5%程度 | 貴族、僧侶、一部の武士や女流文学者 |
◆ 補足
-
文字の種類:主に漢字(公式文書)と仮名(和文、文学作品)
-
教育機関:国学(地方の官吏養成機関)や大学寮(中央)などで官人教育が行われていた
識字率はそんなに高くない
でもそこで新たな疑問が浮かんだ
万葉集には識字率が低いとされている庶民の歌も入っている
それは何故なんだろうか?
ということで再度聞いてみると、答は
庶民の歌はどうやって『万葉集』に記録されたのか?
庶民の歌が万葉集に収録された仕組みはこうです:
-
庶民が口頭で歌を詠む(話す)
例:防人が別れの際に詠む歌、または妻が家で詠む歌。 -
それを役人や書記が聞き取って、漢字で記録する
例:防人の徴発の場にいた地方官(国司や郡司)が「防人歌」として筆録。 -
その記録が都に送られ、最終的に『万葉集』の編集者が選び、収録した
つまり、庶民自身が文字を書くのではなく、代筆・聞き取りによって記録されたのです。
◆ 例:巻20「防人歌」
この巻の序文にも、当時の東国から徴発された防人の歌が「書記が記録したもの」である旨が記されています:
「天平勝宝三年に...諸国の防人を...書記して上進せしむ」
◆ まとめ
-
奈良時代の庶民の大半は文字の読み書きができませんでした。
-
彼らの歌は、口述されたものを役人が記録し、それが『万葉集』に収められたのです。
-
これは、文字を持たない人々の声が記録されて残ったという意味で、極めて貴重な文化遺産です。
なるほど、そうなのか、、と少しスッキリした
でもこの時代、口述したものを役人に聞き取らせ、それを文字として記録したというのは
その手間とか、実行力とかを思うと、すごいことだな!と思えてならない
為政者の意欲というか信念みたいなものは、今の時代よりもずっと上だったのかもしれない