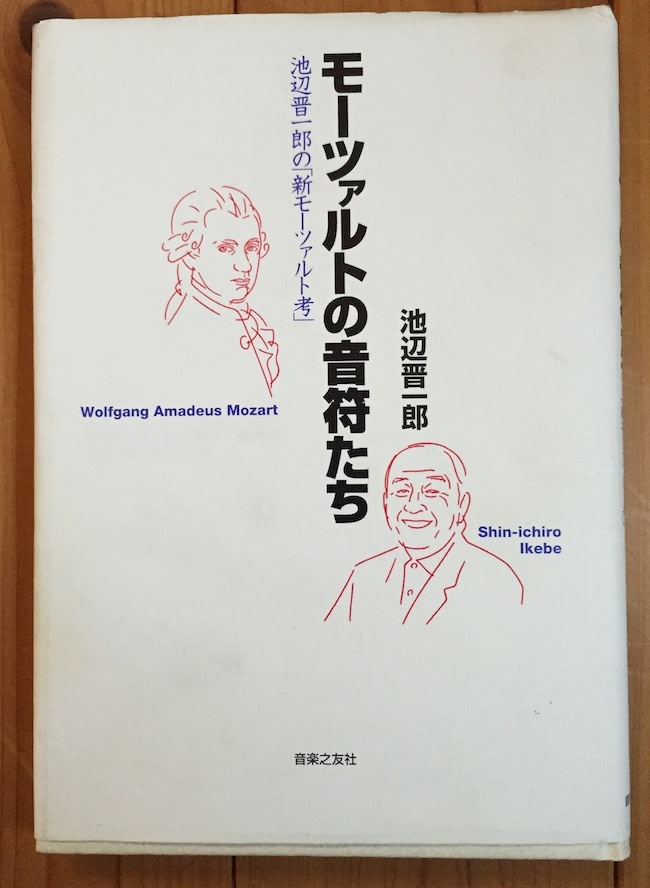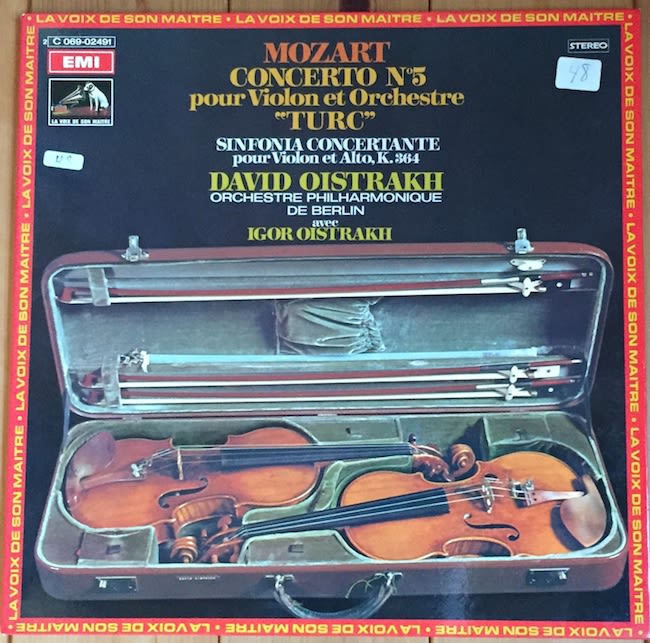中日新聞の夕刊にこんな記事が載っていた

大好きなブルックナーのこと
このブルックナーを好きなのは男が多いということについて松木武彦氏が書いている
これは巷でもよく言われることだし、現実に演奏会場でもその傾向は際立つらしい
でも何故か確信を持って、ここが問題なのだが、絶対に間違いなくブルックナーの音楽は
男にしかわからないと思ってしまう
と言っても、先日は女性指揮者のシモーネ・ヤングの初稿による8番の演奏が
気に入った、とここのブログでもアップしているのだから
少しばかり矛盾しているかも知れないが
それでちょっと考えてみると、ブルックナーの曲でも全部が全部男向きではなくて
先回も挙げたがピアノ曲の「思い出」とか「秋の夕べの静かな想い」などは
ロマンティックというか感傷的で女の人にも受けるかもしれないという気がする
現実にこの曲のCDを残しているのは 女性ピアニストの白神典子さん
でもこれらの曲の時代のブルックナーはブルックナーになっていない
本当の個性、彼らしさが出ていない
器用な、センスの有る、音楽的な才能のある若者(?)の曲になっている
(ブルックナーにも若い時代があったのだ)
ゴッホがいろんな変遷の後ゴッホになったように
ブルックナーはブルックナーになったのはもっと後のこと
後期になるとどこか他人に理解してもらおうというような
気がなくなっているような気がする
それがために弟子たちがいろんなおせっかいをして師匠の音楽の
理解を促すために後から見れば結果的に 余計なことをしたみたいだが
しかし、正確な説明はどうもできない
ただ間違いなく男しかわからないだろうな!
と言う思いは消すことが出来ない
大好きな8番の第3楽章 陶酔して恍惚となる瞬間のあるこの曲
はたして女の人がこれを美しいと思うかと考えると
(別にそんな想像はしなくても良いのだけれど)
なにか違うような気がしてならない
9番の神秘的な響きの深遠な世界も
女の人は 敢えて聴こうという気が起きないのではないか
突き詰めると、男にとってはとても大事なことだが
女にとってはどうでもいいどころか、関心のないものになっているのではないか
そういえば、これも思い込みなのだがベートーヴェンの32番のピアノソナタも
男向きの音楽のような気がする
後期のピアノソナタは全体的にその傾向があって、30番や31番は少しは
女の人も受け入れるかもしれないかもしれないが
32番の2楽章の世界はやっぱり男の世界のような印象を持ってしまう
でもこれも自ら否定するようにユーラ・ギュラーの演奏する32番が
ものすごいって言っているのだから、我ながら筋が通っていない
ブルックナーの音楽が男向きなのと同じように
ドストエフスキーの小説も男向きのような気がする
カラマーゾフの兄弟の大審問官なんて、
女のひとにはどうでも良いようなエピソードなのかもしれない
ところでクラシックの3Bというのは
バッハ・ベートーヴェンそれにもう一いて
その一人にブラームスを挙げる人と、ブルックナーを挙げる人がいるが
自分は圧倒的にブルックナー
田舎のおっちゃんみたいな容貌で、いつまでも自信無げで
でも結局は自分の世界を作り上げた音楽バカ
好きだな
ところで、東京の人はいいな!
バレンボイムのブルックナーチクルスで珍しい曲を聴けたのだから
自分も2番、5番、生で聴いてみたいな
いつか名古屋でやってくれないかな