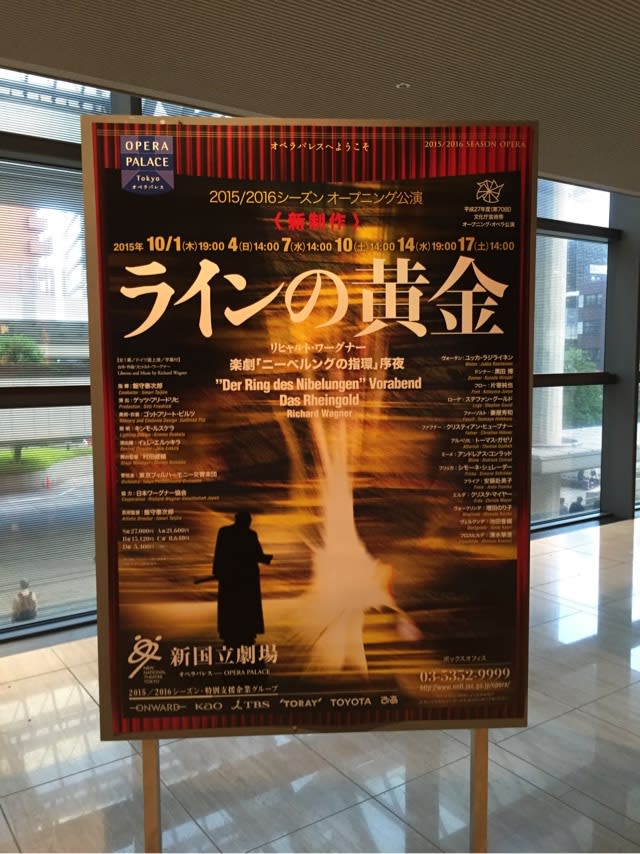今日永らく臥せっておられた方が亡くなった
接点はそれほどあったわけではないが
人は生まれて、生きて、死ぬだけのこと
いつか自分にもやってくるその最後のステージの知らせは
準備はしていたものの、少なからず心になにか重くにそかかる
その人を悼むつもりでふさわしい音楽を探した
葬送の音楽でも感情が表に現れすぎるのは
好ましくない気がした
フォーレのレクイエムでさえ饒舌すぎるような気がして
結局引っ張りだしたのが
アルヴォ・ペルトの声楽曲の一枚(タイトルのアルボスともう一曲は器楽曲だが他は声楽曲)
アルヴォ・ペルトは1935年生まれだから現代音楽の作曲家ということになる
しかし、ここに聞こえる音楽は難解な現代音楽とは違う
音楽的な技法上のことはわからないが、耳から入る音は
まるで中世の音楽と勘違いしそうな雰囲気に満ちている
2,私達はバビロン河のほとりに座し、涙した
4.デ・プロフィンデス(深淵より)
5. 何年もまえのことだった
6.スンマ
8. スターバト・マーテル
のトラックが声楽曲
音はあくまでも静寂に向かって進む
先程まで出ていた音は永遠の静寂の中に消え去ってしまいそう
これらの曲はシェーンベルクやヴェーベルン、シュニトケ、ブーレーズなどとは
違って聴きやすい
逆にもしかしたら飽きやすいのかもしれない
しかし、何度も聴くという行為は録音の技術が出来あがっている最近の聞き方
音楽は本来すぐに消えてしまうもので、半ば記憶の中で再生するもの
だとしたら、聞いている瞬間が印象的であること、
いかに心に響くかが全てなのかもしれない
世界が複雑な感情に支配されているこの様な時代に
この様なシンプルな静寂に向かう音楽が存在することは
一つの奇跡のようにさえ思えてくる
音楽は生活に、いや生きていくうえで必要なものだが
だからと言って聴き流すのは余りにももったいない
聴きたい気持ちが高まって聴いてこそ素晴らしい瞬間がやってくる
願うのは音楽が回りにあることではなく
聴きたいという気持ちが生きている内に数多く体験できること
こうした願いがだんだん冗談ではなくなってきている年齢になっている
私達はバビロン河のほとりに座し、涙した youtubeから
スターバト・マーテル youtubeから前半部分