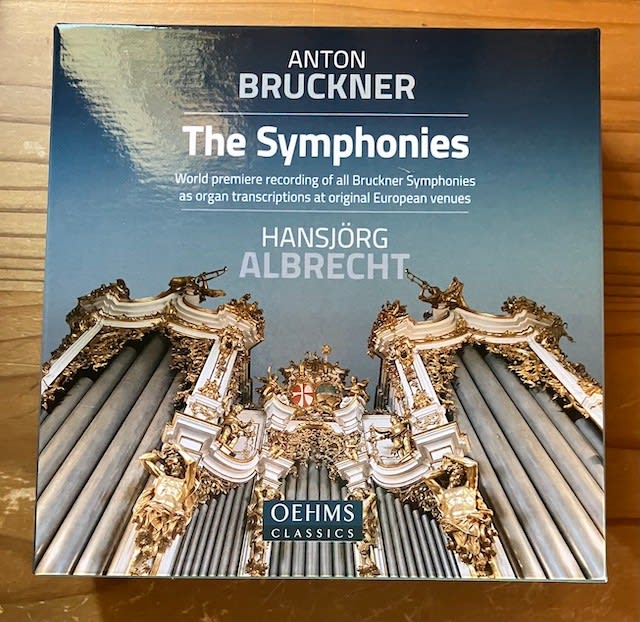最近、心が荒んでいる実感がある
世の中の分断とか理不尽な出来事のせいだが
こうした時、生き物としての人間はどこかバランス
を取ろうとするように思える
その一つの方法として、子どもの無邪気な心に触れたいと思い
モーツァルトのすごく初期のレコードを引っ張り出してみた
手元にあったのはKV10から15までのフルートソナタのこれ
子供の頃の作品だから、つまらないかもしれないと想像したが
前に聴いた時に思いのほか興味深かったことは覚えていて再挑戦したわけだ
改めて聴いてみると、凄いとしか言いようがない
それは9歳の人間が作曲したからという面は否定できないが
それでも、もう大人並みの音楽性が感じられる
湧き出るような音楽と、少しばかり意欲的な試みのようなメロディ
そして不意に寂しさを感じさせるようなフレーズ
ただただ、凄いなと思うしかない
このレコードが興味深かったので、次に聴いたのはやはりレコードで
初期のヴァイオリン・ソナタ
リリー・クラウスとボスコフスキーの組み合わせで、昔
その方面では有名な名古屋の小池レコード店で購入したものだ
1面、2面はケッヘルの50台だからとても幼い時の作品のはず
聴いてみると、なんで子どもがこんな曲をつくることができるのか?
という思いをまたもや覚えてしまう
音楽的には既に大人の領域で、本当に一体どういう頭をしているのだろう
と天才としか言いようのない存在に改めて圧倒される
そう言えば昔「モーツアルトの脳」という本を読んだこことがあった
そこにはやはり特別な脳だったとあったが
作曲という行為は作り出すのではなく
楽譜に書くことは既に頭にあることを書き写すだけの行為としていた
確かにモーツアルトの自筆譜を見ると、少しも躊躇したところがなくて
一気呵成に書かれた勢いが感じられる
すごいなあ、、と改めて思うと同時に、未来がある子どもの生命力が音楽にも現れて
いろんなことを吸収していく前の可能性みたいなものが
今の荒んでいる心を癒やしてくれるような気がする
自分が得意ではないニーチェには
精神は駱駝になり、駱駝から獅子になり、獅子から幼子になる
という変化を論じている
幼子に価値をおいているのだが、その気持ちわかるな、、
というのが現在の自分の気持ち(解釈は違っているとしても)
商業的な意味合いではなく、心を癒す音楽は人には必要なものだと
深く実感する