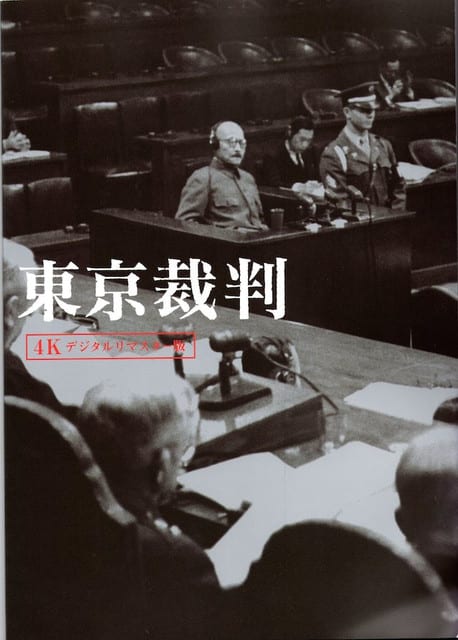数日前のウィーンフィルと全く同じ曲のコンサート(版は違うが)が
昨日、名古屋の芸術劇場コンサートホールで行われた
前回の関心の度合いは、ブルックナー8番、ウィーンフィル、ティーレマンの順番だったが
今回は順序が少し入れ替わってベルリン・フィル、ブルックナー8番、メータの順
今まで一度もナマで聴いたことのないベルリン・フィルの音色への関心が一番だ
肉体的、精神的コンディションを整えて全身で味わう準備をした
なにしろブルックナーの8番は聴く方も相当のエネルギーを消費する
全楽章で1時間半くらいだが、普通の前半後半に分かれたコンサート並みの総量を感じる
(ただし、不思議なのは長く感じないという点)
聴き終わったあとの印象、その思いつくままにあげていくと
この世界最高のオーケストラの凄まじさにぶったまげた
その合奏能力の凄さ、全体がフルで音を出しても濁らずにすべての音が
聞こえるような、それこそ職人たちの集合体の為せる技で
これだけの大勢の人が合わせるということの、そのレベルの高さには
ただただ圧倒された
音色は明らかにウィーンフィルとは違う
冒頭からそれは感じられた
コントラバス、ティンパニは主導するような重心の低い音色
全体でのフォルテもウィーンフィルのような輝かしさはない
しかし内在するエネルギー感は密度の濃さを感じさせる
音色はウィーンフィルが時に自然をイメージさせるような響きの部分があるのに対し
ベルリン・フィルは音の構造物を感じさせる
ブルックナーの音楽の建築的な部分が際立っているような気がした
この2つのオーケストラの違いは、
ウィーンフィルが歌劇場でオペラを経験しているメンバーで構成されているのに対し
ベルリン・フィルは純音楽を演奏することが多いことから来ているような気がする
オペラの登場人物の気持ちにスッと感情移入して効果的に演奏する
感情がたかまった時には自身もその渦の中に入ることをいとわない音楽家たち
登場人物はいい人間ばかりではなく、人間的な弱さを持っているがそれでも
なにか共感する懐の深さ(あるいはいい加減さ)を持つオーケストラの人々の集まりがウィーンフィル
一方ベルリン・フィルは北ドイツの風景を連想させる真面目なイメージ
ドイツは北と南では建築物の印象もだいぶ異なり、ブレーメンやリューベック、ベルリンは
明らかにミュンヘン(やウィーン)の醸し出す雰囲気とは違う
この真面目さが、重心の低い音を好み、音楽を音の構造物として捉えようとする傾向が
あるような気がした
人間の行うことは、同じことをしてもずいぶん違うものだと再確認したわけだが
どちらが良いか?は甲乙つけがたい
多分平均点ではベルリン・フィルのほうだろうが、ノッた時のウィーンフィルの
演奏も捨てがたそうな気がする
ベルリン・フィルは名人・職人が多くて強奏でも音がぶつからないが
各人はそれでもまだ余裕があるような気がしている
不意に、これがフルトヴェングラーの指揮だったらこの名人たちの奏者すら
余裕が無いほど演奏に夢中にさせたのではないか、、と頭に浮かんだ
フルトヴェングラーの指揮は聴いてる方も楽しめるが演奏してる方もスリルがあって
楽しんでいるのではないか、、と思ってしまう
話はフルトヴェングラーにそれてしまったが、とにかくベルリン・フィルは
凄いオーケストラということはわかった
メータでブルックナーの8番を聴くのは二度目だが
指揮台まで歩いていくメータは歩き方が少しヨボヨボして
かれがそれなりの年齢に達していることを実感させた
音楽はティーレマンがやったように静寂と緊張感を待って指揮を始めたのではなく
割と無頓着に始めた
そのためにその後の音楽への集中が心配されたがベルリン・フィルの音色で
それらの不安は気にならなくなった
メータは年齢がいっているし、この曲も既に数多く演奏している
その手の内に入っている感じが細かなニュアンスの変化として
ティーレマンの演奏よりは気づくところが多かった
いつもこの曲の一番の楽しみは第三楽章
徐々に瞑想的な世界になっていき、内的な時間経過は時間の存在すら
忘れるようなときがある
ここで気になるのが版の問題
それほど違いに詳しいわけではないが、聴きたい部分はどうしても気になる
ティーレマンはハース版、メータはノヴァーク版だったが
ティーレマンの方はクライマックスに向かうが急に弱音の挿入句があって
一気に輝かしい頂点には向かわない
ところがメータはの版は一気に頂点を目指す
最初レコード等で聴いてたのは一気に向かう方だったが
どちらが好みかといえば最近はモタモタしたところのあるところが
却ってブルックナーらしくて、挿入句のある方が好きとなっている
11月の主な行事(?)もあとは22日の京都太秦の聖徳太子像の見学と
あと一つ、同級生絡みのライブを残すだけ
しかし、今月はしっかり家計簿は赤字、、
赤字になることがわかると、やけくそ消費で赤字は増える
次は節約しなくては、、