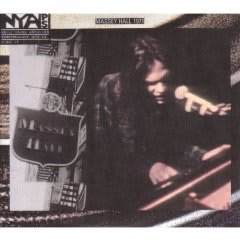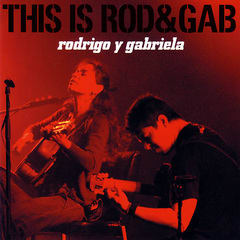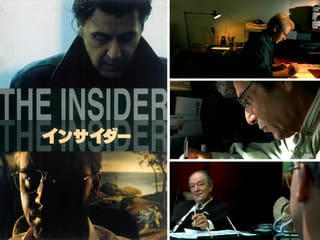日曜の午前、なぜか2歳の娘と二人きり。
珍しく早起きしたので、美術館に出かけた。
前から行ってみたかった国立新美術館。
ルノワール展をやっていた。
裸婦、肖像画、風景画。
まあルノワールは、どこまでいってもルノワールなのであった。
どっちかというと建物の方が面白かった。
黒川紀章設計。

不思議な円錐形の上にはレストランがある。
この美術館には、カフェやらレストランやらが沢山ある。
しかもかなりお値打ち。
今度、食事を目当てにやってこようっと。
館内のあちらこちらには、ウェーグナーのCH25が置かれている。

この椅子、好きなんですよね。
我が家にも一脚欲しいけれど、ちょっと高価で手が出ません。。。
お昼は、地下一階のカフェで娘とランチ。
ブロッコリーのスープに、チキンのサラダ、パンがとてもおいしかった。

結局、花より団子の娘とのデートでありんした。
珍しく早起きしたので、美術館に出かけた。
前から行ってみたかった国立新美術館。
ルノワール展をやっていた。
裸婦、肖像画、風景画。
まあルノワールは、どこまでいってもルノワールなのであった。
どっちかというと建物の方が面白かった。
黒川紀章設計。

不思議な円錐形の上にはレストランがある。
この美術館には、カフェやらレストランやらが沢山ある。
しかもかなりお値打ち。
今度、食事を目当てにやってこようっと。
館内のあちらこちらには、ウェーグナーのCH25が置かれている。

この椅子、好きなんですよね。
我が家にも一脚欲しいけれど、ちょっと高価で手が出ません。。。
お昼は、地下一階のカフェで娘とランチ。
ブロッコリーのスープに、チキンのサラダ、パンがとてもおいしかった。

結局、花より団子の娘とのデートでありんした。