ハーモニィセンターの小笠原キャンプで出会った、
富田涼都さんに会ってきました。

緑色の三点セット(足ひれ、水中マスク、マリンブーツ)
を使っていたので「カエルのお兄さん」と呼ばれていた少年が
20年経ったら、静岡大学の環境社会学の助教になっていました。
今の職業に就いたきっかけが、
一緒に過ごしたキャンプにあったという話には驚きました。
同じ場所で食う寝る遊ぶをともにしてても
全く違う事を感じていて面白かったなぁ。

富田諒都 「なぜ自然を守るのか?」
目次
第1話 こんな世界もあるのか
第2話 好きなんだったら、やればいいじゃん’
第3話 キャンプで見つけた空港建設の看板
第4話 生態学では答えがでなかった疑問
第5話 なぜ自然を守るのか
第6話 調査現場での研究者の立場
第7話 災害のときにできる事(3月13日更新)
第8話 誰にとっての「当たり前」を説明する仕事
第9話 学生に考えてもらいたい事
最終話 言い続ける事に価値がある
それでは、お楽しみに!!
富田さんは東京農工大学農学部卒業後、
東京大学大学院新領域学科を経て、
静岡大学で環境社会学の研究者、
助教として活躍しています。
せっかくなので、授業も受けてきました。
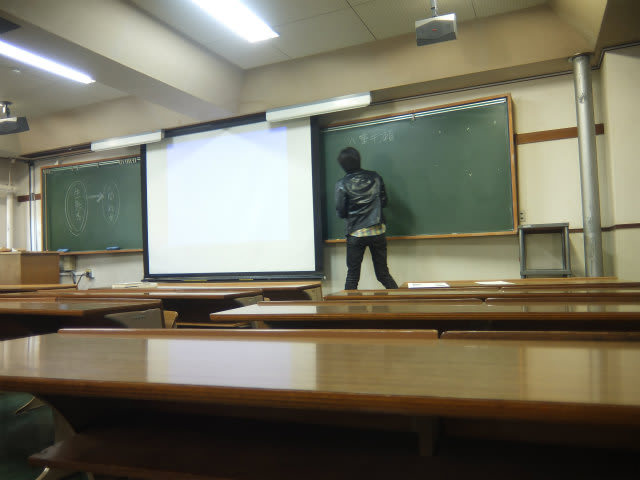
いやー、面白かったです。その授業についても
話の中で触れているので、紹介したいと思います。
その日の授業は
沖縄の八重干瀬(やびじ)に続く伝統的な漁のVTRを通して
「何のため、誰のために自然を守らないといけないの?」っていう
問いかけを学生にしていました。

その島には海が干潮の時だけ地上に現れる、
珊瑚礁の上を歩いて漁をする、伝統的な漁法がありました。
その島ならではの文化もあります。
お祭りに必要な巫女さんをくじ引きで選ぶのですが、
選ばれた3年間は、島から絶対に出てはいけない
という決まりがあったり。様々なお祈りがあったり。
その島ならではの「当たり前」がありました。
「守らなくてはいけない」と決めている貴重な珊瑚礁。
それなのに干潮の時には海面に現れた珊瑚礁の上を
海女さんたちが、歩いて漁をする姿が。
VTRではその背景に何百年と続いている、
文化、伝統、宗教的な意味も紹介されていました。
それを見にきた観光客。
サンゴの保全のみを考えれば
そこは立ち入り禁止にすべきですが。
なんで観光客は立ち入り禁止なのに、
海女さんは許可をされているんだろうか?
自然って、誰のために、なにを守ればいいんだろうね?
答えのない考える授業でした。
主に、農学部で生態学を学びに来ている学生さんが中心のクラスだそうです。
その分野の学生に環境社会学を教える意味とは?
富田さんの狙いとは?沢山聞いてきました!

静岡名産のしらす。お鮨も握ってきました。
それでは本編、お楽しみに。
arinomamaki@gmail.com
富田涼都さんに会ってきました。

緑色の三点セット(足ひれ、水中マスク、マリンブーツ)
を使っていたので「カエルのお兄さん」と呼ばれていた少年が
20年経ったら、静岡大学の環境社会学の助教になっていました。
今の職業に就いたきっかけが、
一緒に過ごしたキャンプにあったという話には驚きました。
同じ場所で食う寝る遊ぶをともにしてても
全く違う事を感じていて面白かったなぁ。

富田諒都 「なぜ自然を守るのか?」
目次
第1話 こんな世界もあるのか
第2話 好きなんだったら、やればいいじゃん’
第3話 キャンプで見つけた空港建設の看板
第4話 生態学では答えがでなかった疑問
第5話 なぜ自然を守るのか
第6話 調査現場での研究者の立場
第7話 災害のときにできる事(3月13日更新)
第8話 誰にとっての「当たり前」を説明する仕事
第9話 学生に考えてもらいたい事
最終話 言い続ける事に価値がある
それでは、お楽しみに!!
富田さんは東京農工大学農学部卒業後、
東京大学大学院新領域学科を経て、
静岡大学で環境社会学の研究者、
助教として活躍しています。
せっかくなので、授業も受けてきました。
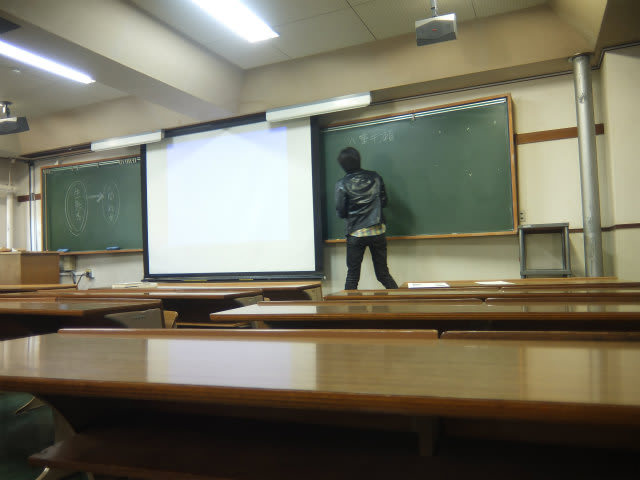
いやー、面白かったです。その授業についても
話の中で触れているので、紹介したいと思います。
その日の授業は
沖縄の八重干瀬(やびじ)に続く伝統的な漁のVTRを通して
「何のため、誰のために自然を守らないといけないの?」っていう
問いかけを学生にしていました。

その島には海が干潮の時だけ地上に現れる、
珊瑚礁の上を歩いて漁をする、伝統的な漁法がありました。
その島ならではの文化もあります。
お祭りに必要な巫女さんをくじ引きで選ぶのですが、
選ばれた3年間は、島から絶対に出てはいけない
という決まりがあったり。様々なお祈りがあったり。
その島ならではの「当たり前」がありました。
「守らなくてはいけない」と決めている貴重な珊瑚礁。
それなのに干潮の時には海面に現れた珊瑚礁の上を
海女さんたちが、歩いて漁をする姿が。
VTRではその背景に何百年と続いている、
文化、伝統、宗教的な意味も紹介されていました。
それを見にきた観光客。
サンゴの保全のみを考えれば
そこは立ち入り禁止にすべきですが。
なんで観光客は立ち入り禁止なのに、
海女さんは許可をされているんだろうか?
自然って、誰のために、なにを守ればいいんだろうね?
答えのない考える授業でした。
主に、農学部で生態学を学びに来ている学生さんが中心のクラスだそうです。
その分野の学生に環境社会学を教える意味とは?
富田さんの狙いとは?沢山聞いてきました!

静岡名産のしらす。お鮨も握ってきました。
それでは本編、お楽しみに。
arinomamaki@gmail.com



















