文永11(1274)年、身延山に入られた日蓮聖人は一時、波木井公の邸に滞在しました。

(↑画像は身延の円実寺)
そして御草庵の場所を決めると、庵ができるまでの間、甲州をお説法に廻ったといいます。

富士川沿いには日蓮宗のお寺が非常に多く、例えば8年前に鰍沢町と増穂町が合併してできた富士川町には実に57ケ寺が存在します。(日蓮宗ポータルサイトより)
わずか1万5千人の町ですよ~!
この地で日蓮聖人がいかに精力的にお説法して廻ったのかが窺えます。

その富士川町の中心部、県道42号線、通称身延みちに昌福寺はあります。
「虫切加持」って書いてあるな。

通り沿いにある大きな法塔は

江戸の講の方々が寄進したようです。
「惣」とは、農村部の自治組織のこと、だったと思います。昔は江戸にも田畑が沢山あったんでしょうね!

巨大な樹木があり、歴史を感じさせるお寺です。

山門です。

扁額には山号「壽命山」と書かれています。何か寿命にまつわる逸話があるのかな?

す、すごい。550遠忌の法塔がフツ~に建っている。

まずは日蓮聖人のご尊像に合掌。

体力、気力ともに充実のお祖師様に見えます。
ここ青柳を訪れた時も、こういう表情だったのでしょう。

本堂です。
この日は小雨だったんですが、本堂に灯る明かりに温かみを感じました。
多くのお寺を巡っていて感じることですが、お寺の明かりって、そのお寺の印象を残す上でとっても大切です。
意外と「和モダン」の雰囲気が好きな方って、多いと思います。歴史のある建物内に、少しでいい、電球色のシンプルなLED照明を入れるだけで、イメージがグッと温かくなります!
これで軽く腰掛ける場所でもあれば、コーヒーでも飲みたくなるし、長~い時間そこに居たくなります。

お寺の縁起にまつわるお上人方の供養塔でしょうか。

開山は日全上人となっています。
日全上人は、善智法印改め日伝上人の弟です。

青柳の至近にある小室山(当時真言宗)の善智法印は、日蓮聖人との法論に敗れて表向き改宗しましたがそれは本心ではなく、密かに毒入りの餅で日蓮聖人を毒殺しようと企てました。その時どこからか白い犬が現れて毒餅を食べ、日蓮聖人を助けました。
日蓮聖人が身代わりとなった白い犬を手篤く葬り、お墓に立てたイチョウの杖が、現在の下山・上沢寺の逆さイチョウになったと言われています。
善智法印は今度は本当に改心、帰依して日伝上人になりました。
自らお祖師様のご尊像を刻すると、お祖師様から「延寿のお像」として開眼供養を受けました。

そして日蓮聖人のご入滅から16年後、日伝上人の実弟・日全上人がここ青柳で開いたお寺が昌福寺です。
日全上人が延寿のお像を兄から引き継いだことが、山号である壽命山の由来だと思われます。

昌福寺の12世・日法上人は病気平癒の祈祷で有名な方だったようです。
もともとお祖師様がここ青柳を通った時、住民が疫病に苦しむのを見て、病気を鎮める祈祷をしたという由緒ある地。
現在でも昌福寺のご住職は、病気平癒の祈祷「虫切加持」を受け継いでいるそうです。
「虫」は疳の虫の「虫」だそうで、宇津救命丸で効かない時は祈祷をお願いするといいかもしれません。

石橋湛山氏の顕彰碑もありましたよ!
石橋湛山は立正大学の学長、そして内閣総理大臣の経験者ですが、父親が昌福寺で住職を務めていたため、少年期の3年間を昌福寺で過ごしています。
けっこうやんちゃなガキだったみたい(笑)
ちなみに石橋氏の父親・杉田日布師は、のちの久遠寺81代法主です。
あ~、いろいろありすぎておなかいっぱい~!
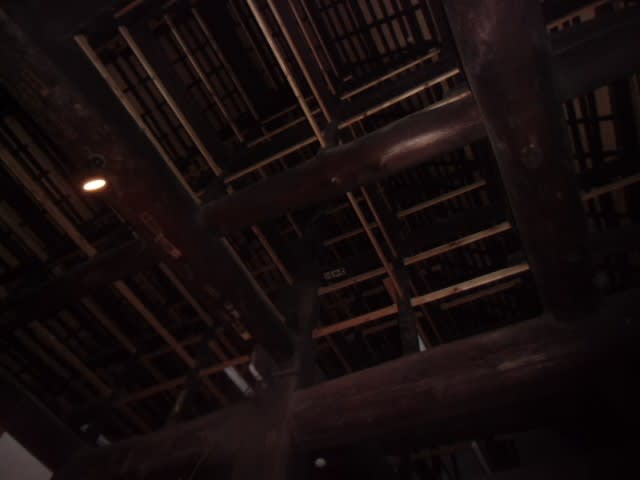
庫裏でご首題を頂いたのですが、庫裏もメチャクチャいい雰囲気!
ゆる~くジャズのBGMでも流したら、まんまカフェになりますね~

廊下の向こうに見える庭園も良さそう!先人達から引き継いだものを上手く生かしています。
昌福寺の若いお上人のセンスがいいと見た!
頂いたお寺の縁起にも、フェイスブックやツイッターのアドレスが書いてありました。
僕はフェイスブックをやっているので覗いてみると、おお~!お寺でライブや料理講習会なんかをやっているみたい。
敢えて言いましょう!このお寺には若い人が集まると思う。何故ならお上人が若い人を寄せつけるキモの部分をよく理解しているから。
僕もまた行きたいもん。

最後に昌福寺のお上人に、身延参詣道の話を伺いました。
江戸時代、江戸の町なかで法華信仰が庶民に広まったこともあり、江戸から身延に参詣する人が絶えなかったといいます。
確かに身延の山中や七面山の登詣路には江戸の講中が寄進した法塔や狛犬などが沢山見られます。

彼らはまず昌福寺で虫切の護符を求め、次いで小室の妙法寺で毒消しの護符を求めたあと、身延山を参詣するというのがお決まりのルートで、このあたりに通じていた道は「小室道」と呼ばれていました。
実は昌福寺の境内には小室道が南北に通じていたそうです。

お寺の外側に、「左 小室道」と刻まれた石碑がありました。
小さくてさりげなくあるので見落としがちですが、こういうのを見つけると一気に往時にタイムスリップした気持ちになります!
そうそう、古典落語「鰍沢」はこの小室道を舞台にしたお話ですよ!とお上人に伺い、早速YouTubeで見てみました。
実際にお話の中に昌福寺、妙法寺や法論石などが出てきて、聴き入ってしまいました!
江戸時代も現在も、元気な市井の庶民達が集まる昌福寺。
印象に残りまくりのお寺でした。















