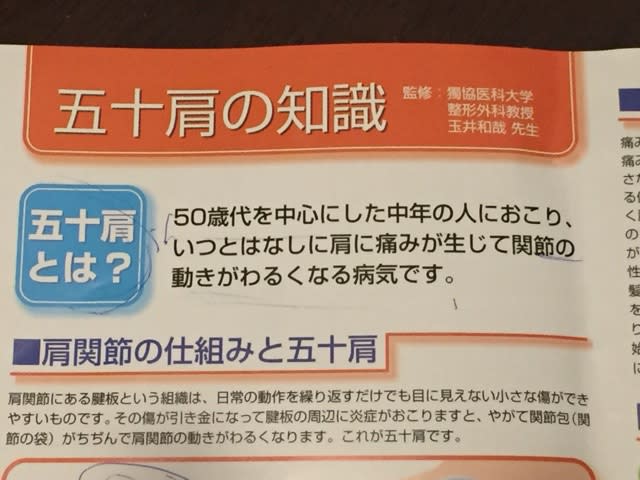新しい職場に車で通うようになってもうすぐ半年。
(と書いて、半年経ちつつあることに自分で驚く )
)
ラジオを聴きながら帰ることが多いのだけど
こないだ、FMヨコハマのTresen+で
「自分の仕事のつらいところ」というテーマ投稿があって
高校教師が
「高校生諸君、君たちはテストが嫌いだろう。
実は高校教師もテストが嫌いだ(準備から採点が大変だから)」
という発言があった。
そりゃそうだよねと思いつつ聞いてたら
高校時代のあるテストを思い出した。
中間か期末かは覚えてないけど、定期テスト、
科目は現代国語。
担当教師から言われたのは
「教科書を持ち込むこと」。
範囲は森鴎外の「舞姫」。
問題用紙は、とにかく舞姫を読んで答えなさい、
という設問がずらり。
しかも全問題記述式。選択式いっさいゼロ。
解答用紙を見てさらにたまげた。
右側に(縦書きだからね)氏名欄があって
あとは設問番号がだーっと
並んでるだけのほぼ白紙状態。
ここまで手抜きの解答用紙は
あとにも先にも見たことがない。
テストが終わるが早いが職員室に
ヤンキーっぽい男子たちが
「解答用紙手ぇ抜くなー!」
と文句を言いに来たが
担当教師(40代ぐらいの女性でした)はにっこり笑って
「作るのめんどくさかったんだもん」
さっぱり、すっきり。
男子たちは笑いながら出て行った。
いま思うと、あのテスト、
採点するほうがめちゃめちゃ大変だはず。
今ほどではないけど多忙な公立高校の先生が
大胆なテストをしたものである。
今までのテストはとにかく記憶して、
脳みその表面に記憶が貼りついてるうちに
せっせとテスト用紙に書き写していたんだけど
あんなに「考えた」テストは初めてだった。
とにかく読み込むこと、感じたことを書くこと。
それを徹底的に教え込まれた。
やたらレポートや作文の宿題が多かったけど
思えば、それは教師のほうも負担は大きかったはず。
そりゃー宿題やるほうも楽じゃなかったんだけど、
私は結構嫌いじゃなかった。
この先生に「思ったことを表現する」ことを
徹底的に仕込まれた気がします。
そのあと、受験、就職、職場の昇級試験と
論文を書くシーンのたびに、あの先生の教えが
どんだけ役に立ったことか。
30年経っても思い出す、まっしろな解答用紙。
M浦先生、お元気でしょうか。