《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》
さて、前回私は こうなれば、この「常盤樹」でそれがどのように扱われていたのかをもっと具体的に知りたいと思ったのだが、残念ながらそれは「館内限定閲覧」ということなので閲覧は不可能だった。
とぼやいたのだったが、たまたまラッキーなことに、そのことに関して山口泉氏の『人間ドキュメント 宮澤賢治伝説』によってほぼその中身を知ることができた。どうやら同書によれば、「常盤樹」に掲載された「雨ニモマケズ」についてはそこでは次のように解説されていたようだ。
この詩が発見されたのは此の詩人の死んだ後であつた。図らずも令弟が詩人の小さな手帳を見つけ出されたところ、手ずれた汚い、普通のポケット用手帳の中のいろいろな覚書などにまじつて、この詩が鉛筆で書きしるされてあつたのである。
詩人はこの詩をまつたく人に見せる気はなく、純粋に自分の心構のためにひそかに書きしるした。この詩を読むと第一にさういう、心を一途に内に傾けてゐる純粋さがわれわれを打つ。この平凡なやうな、へりくだつた、最低の願のやうに見える「サウイフモノニワタシハナリタイ」といふ声をよくきいてゐると、それが実に大きな願であることにわれわれは気づいてくる。此の「私」を滅した、はからひや高ぶりの無い境地に人は容易には到り得ない。しかし斯ういふ人にして始めて萬人の真の友たり得るのだといふことにわれわれはだんだんに気づいてくる。この詩人は岩手県の農民のためにその一生を捧げた。
(「雨ニモマケズ」解説/大政翼賛会文化部編『詩歌翼賛-朗読詩集 日本精神の詩的昂揚のために』第二輯/一九四二年三月、東京・目黒書店刊)
<『人間ドキュメント 宮澤賢治伝説』(山口泉著、河出書房新社)272p~より>詩人はこの詩をまつたく人に見せる気はなく、純粋に自分の心構のためにひそかに書きしるした。この詩を読むと第一にさういう、心を一途に内に傾けてゐる純粋さがわれわれを打つ。この平凡なやうな、へりくだつた、最低の願のやうに見える「サウイフモノニワタシハナリタイ」といふ声をよくきいてゐると、それが実に大きな願であることにわれわれは気づいてくる。此の「私」を滅した、はからひや高ぶりの無い境地に人は容易には到り得ない。しかし斯ういふ人にして始めて萬人の真の友たり得るのだといふことにわれわれはだんだんに気づいてくる。この詩人は岩手県の農民のためにその一生を捧げた。
(「雨ニモマケズ」解説/大政翼賛会文化部編『詩歌翼賛-朗読詩集 日本精神の詩的昂揚のために』第二輯/一九四二年三月、東京・目黒書店刊)
そしてたしかにこの「解説」からは、大政翼賛会の思惑が透けて見えてくる。
そこでこの「解説」を少し分析してみたい。まずは、
(1) 此の「私」を滅した、はからひや高ぶりの無い境地に人は容易には到り得ない。しかし斯ういふ人にして始めて萬人の真の友たり得るのだといふことにわれわれはだんだんに気づいてくる。
についてだが、ここからは、この詩の採録の目的として国民に「滅私奉公」の精神を浸透させようという大政翼賛会の狙いがあったであろうことが窺える。次に、
(2) この平凡なやうな、へりくだつた、最低の願のやうに見える「サウイフモノニワタシハナリタイ」といふ声をよくきいてゐると、それが実に大きな願であることにわれわれは気づいてくる。
についてだが、これは(1)の「「私」を滅した、はからひや高ぶりの無い境地」を説明していることになるわけだから、その境地とは「この平凡なやうな、へりくだつた、最低の願のやうに見える「サウイフモノニワタシハナリタイ」」という境地のことを指すことになる。ということであれば、
雨ニモマケズ/風ニモマケズ/雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ/丈夫ナカラダヲモチ/慾ハナク/決シテ瞋ラズ/イツモシヅカニワラッテヰル…(略)…ヒドリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ/ミンナニデクノボートヨバレ/ホメラレモセズ/クニモサレズ……①
であることが「平凡なやうな、へりくだつた、最低の願のやうに見える」とこの「解説」は言っているということになるから、忍耐と滅私奉公の外延的表現とも言える〝①〟を戦意高揚のために使いたかったということになりそうだ。たしかに論理的には、この〝①〟はそのような意味ではまさに、戦争遂行を鼓舞するための国民運動推進機関であったともいえる「大政翼賛会」にとっては戦意高揚のために願ったり叶ったりの、しかも国民に訴えやすくてわかりやすい事柄の羅列だったと言えるだろう。したがって(1)と(2)からは、〝①〟であるようにはなかなか「人は容易には到り得ない」が、〝①〟でありたいと願うことは「実に大きな願であることにわれわれは気づいてくる」のだと訓え導こうとしている大政翼賛会の思惑が見えてくる。
そして、
(3) 詩人はこの詩をまつたく人に見せる気はなく、純粋に自分の心構のためにひそかに書きしるした。この詩を読むと第一にさういう、心を一途に内に傾けてゐる純粋さがわれわれを打つ。
についてだが、その訓導の効果をあげるためには、まず最初に読者の心構えを外にではなくて「心を一途に内に傾けてゐる」状態にさせておきたいと目論んだのでこの(3)を一連の文の最初に置いたのだと私は解釈した。だからもしこの解釈が正しいとすれば、この「詩人はこの詩をまつたく人に見せる気はなく、純粋に自分の心構のためにひそかに書きしるした」は爾後、是が非でも「事実であった」ということであり続けねばならなくなってしまったという恐れもある。(4) 最後に残りの
この詩人は岩手県の農民のためにその一生を捧げた。
についてだが、「この詩人」である賢治はもちろん「心を一途に内に傾けてゐる純粋さ」がなければならないのだから、まさにその「純粋さ」を直截的に表現するこの一文で最後を締めくくったのはなかなか効果的な文章構成になっていると思う。しかしながら、現実の賢治がそうであったとは言い切れないこともまた私から言わせれば事実だ。だから逆に、爾後この「解説」に沿うような「賢治」が、国策に叶うような「望ましい賢治像」がますます創り上げられていったということになりそうだ。
こうして、「雨ニモマケズ」が戦意高揚のために使われ、延いては賢治という人物像までもが国策に沿って造られたと考えれば、巷間広まっている「賢治像」とこの「解説」が述べているところの賢治とがかなりの部分で重なっているように見えてしまうのも宜なるかなと思えてくる。
なお蛇足かもしれないが、あと一つ気になることがこの「解説」にはある。それはまだ言及していなかった前段の中で述べられている、「令弟が詩人の小さな手帳を見つけ出されたところ」という敬語表現がなされていることがである。なにか、そこに不自然さを私は感じてしまう。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。
【『宮澤賢治と高瀬露』出版のご案内】
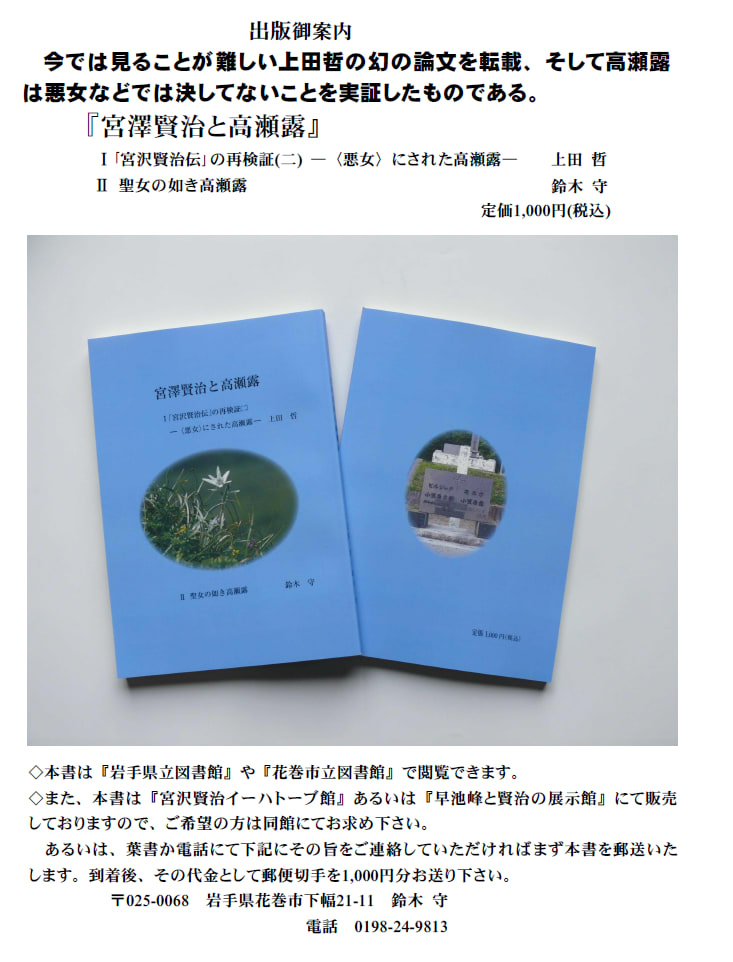
 その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。
その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。









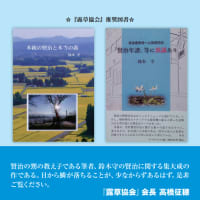
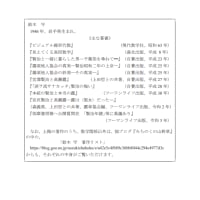
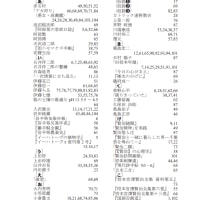
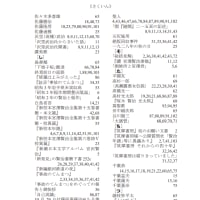

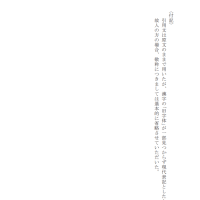
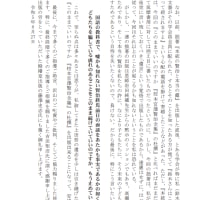
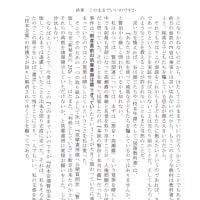
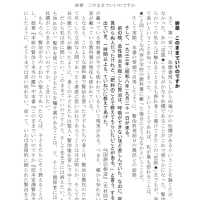






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます