不景気とはいうけれど...。サラリーマンの生活は本当に厳しいの?(マイナビスチューデント)
4月から社会に出て働く皆さんにとって、身近な先輩のお給料の額は自分の懐に入るお給料を知る上での貴重な参考。気になる人も多いのでは? 今年の11月に厚生労働省から発表された、『平成24年賃金構造基本統計調査結果』によると2012年6月の大卒社会人1年目平均給与の額(税引き前)は19万6500円だという。「不景気」と叫ばれて数十年ですが、この額って実際のところ高いの、低いの?
「新卒の給料平均だけで考えると、この額は悪くないといえるでしょう。意外に思うかもしれませんが、大卒男子の初任給が10万を超えるようになったのは1977年からで、1976年には9万4300円だったのです。それから倍以上お給料が伸びているのに対して、物の値段を相対的に図る消費者物価指数は当時と比べて58.8%の増加率とされています。つまり、物の値段に対して、倍以上お給料が増えているのが現代なのです」
と、教えてくれたのは『意外と知らない 給料のカラクリ』の著者で税理士の落合考裕さん。物価上昇率に対してお給料が倍以上に膨らんでいるのに、なぜここまで「不景気」とか「生活が厳しい」と言われてしまうのでしょうか?
「経済成長の伸びしろがあった高度成長期に比べて、成長が頭打ちとなった現在は、年齢を重ねても給料が伸びにくくなっていることが最たる理由として考えられます。また、厚生年金や健康保険といった社会保障の額が増え、新卒の場合は手取り額が13~14%減ってしまうというのも理由の1つとして考えられます。1977年当時の年収に対する社会保障負担額はおおよそ10%であったので、3~4%程度負担が増加したことになります。あるいは、派遣社員などのワーキングプア問題や大手会社のリストラ問題など、必ずしも大学を出て大手企業に就職したからといって、必ずしも一生安泰ではないことがメディアに大きく報じられていることも考えられますね」
……とまぁ長々と引用しましたが、とりあえず実態として日本全体の給与水準が下がり続ける中でも新卒時点での給与平均は概ね維持されてきたわけです。引用元では比較対象が1970年代と遠すぎてあまり意味のない議論になっているのが残念ですけれど、まぁ過去に比べて若者が貧しくなっているとは言えないと。ではなぜ「『不景気』とか『生活が厳しい』と言われてしまう」のか、その辺への回答が引用した最終段落に当たるようです。中には妥当な部分もあれば、誤魔化しを感じさせるところもありますかね。
経済成長の伸びしろがあった云々は典型的なミスリーディングで、経済成長を止めたのは日本だけ、日本を置き去りにして世界経済は成長を続けているという現実に向き合って欲しいものですが、これを経済系の論者に望むのは木に縁りて魚を求むと言ったところでしょうか。社会保障費負担に関しても、給与の10%から13%程度に上がったくらいでは、所得の伸びに対しての影響を論じるにはあまりにも小さすぎます。あるいは「○○がメディアに大きく報じられていることも考えられます」云々の結びも怪しい、ではメディアが沈黙して何も伝えなければ良いのか、コンサルよろしく作り話を吹き込むことに専念しておけば問題は解決するのかと首を傾げるばかりです。
ただ根幹である「年齢を重ねても給料が伸びにくくなっていることが最たる理由」との指摘は至って妥当と言えます。昨今は「将来にツケを残すな」と大騒ぎする人も多いですが、それでもローンを組んで大きな買い物をする人がいなくなったわけではありません。「現在」の手持ちのお金に不足があっても「将来」の収入を使って買い物をすることが可能であり、それが経済を膨らませるものでもあります。「今」あるいは「若い内」の収入は少なくとも、将来的に収入が増えることが確実視されていれば、使えるお金はずっと大きくなる、そういうものなのです。
ところが今や会社に長く勤めても給与が上がる保証はなく(新人がすぐに辞めると不平を並べ立てておきながら、仕事を続けさせるためのニンジンを差し出すつもりは皆無というわけです!)、むしろ年齢が上がるにつれ会社からリストラされるリスクは高まるばかり、そして年を取ってしまえば再就職先など容易に見つかるものではありません。こうなると「将来の収入」を使うどころか、逆に「今の収入」を将来の備えとして残しておかなければならなくなってしまいます。故に、健康で扶養家族もおらず、給与削減の波から免れた額の初任給を受け取ってもなお自分の懐が寂しいと感じる人もいるのでしょう。
新卒一括採用を批判する論者は珍しくありません。とりあえず日本の「これまで」の慣行とされるものをネガティヴに論じておけば改革派を気取れると、そんなノリもあるでしょうか。まぁ確かに、就業機会が新卒時に集中しすぎている、そのアンバランスさが我々の社会を歪ませているところはあるかも知れません。ならば同様に、真っ当な就業機会が若年時に集中していることにも疑問を抱いて欲しいところです。新卒一括採用にダメ出しをするなら、年齢差別の罷り通る若者優遇の採用姿勢を問題視するぐらいはできないと、とうてい筋が通っているとは言えませんから。
このブログでも何度か指摘してきたように、問題なのは若年層の「今」と言うより「将来」であり、それは中高年層にとっての「今」でもあるわけです。新卒として採用された時点での給与が低いから若者に希望がないのではなく、「年齢を重ねても給料が伸びにくくなっていることが」未来を暗澹たるものにしているということを直視する必要があります。「若者のため」を掲げる論者は専ら若年層の「今」のための施策を呼びかけますが、これは根本的に誤っているどころか逆効果です。若者の雇用機会のためと称して今以上に中高年を会社から追い出すようになれば、なおさら将来不安は増すばかりなのですから。長く勤めていれば給料も上がると、そう信じられるようにならなければ若年層にとって会社を辞めずに働き続ける動機は弱まるばかりですし、将来の収入を当てにしたローンも組めない、むしろ「今」の収入を貯蓄に回すことを迫られます。これまでの若者中心の雇用政策が若者の将来を暗くするばかりであったことを省み、方針を改めるべき時がとっくに訪れているのではないでしょうかね。
参考、元・若者
「未来の若者」のために「若者の未来」を犠牲にしているとも言えます。中高年層の「既得権」とやらを剥奪して「若者の雇用機会」を増やすとなると、確かに「若者」の雇用機会「だけ」は増えるでしょう。ところが10年、20年、30年と時が経つにつれて若者は中高年になる、それこそ若者の避けられない未来であり、この未来に「若者が」全く希望を見いだせなくなっているのが現状であるわけです。上記のリンク先では、いわゆる「氷河期世代」に若者であった人が既にリストラ対象者に含まれるようになってきた、「今」の若者に椅子を譲ることを迫られ始めているという事例を取り上げました。今後も若者の雇用機会を増やそうという取り組みは続く、その手の主張が支持を集めてゆくことでしょう。そして今以上に、若者の未来は暗いものとなっていくのです。














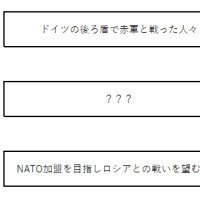




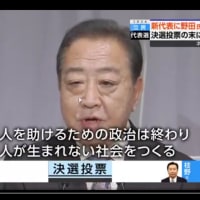

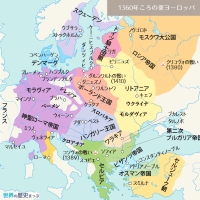





まぁ、その辺の都合の悪いデータを気にしていては経済系の記事はかけないものなのじゃないでしょうかね。