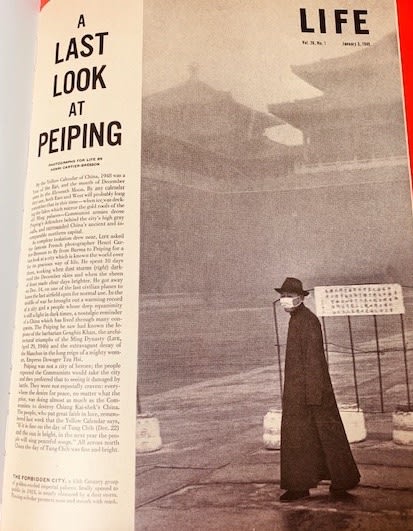ケンブリッジ大学キングス・コレッジ前 (Kings Parade St) YK Photo
新型コロナウイルスの蔓延で、自宅に閉じ込められた生活を強いられた人は多い。急に増えたゆとりの時間の使い方に悩み、フラストレーションがたまったりする人もいるようだ。この期間、人々が何をして過ごしたかという点について、いくつか報道があった。1)「家財の断捨離・掃除」、2) 「家の中でできる運動」、3) 録画や本など眠るコンテンツの消費、 4)動画配信サービスの利用、5) 飲食店のテークアウトの活用などが上位を占めていた(『日本経済新聞』2020年5月30日)。
興味深いことは、こうした大不況期においても、人間の文化活動は衰えることなく、独自の文化遺産が残されていることが知られている。1930年大恐慌時代のアメリカでも、文学や映画、演劇、音楽、建築など多くの領域で後に「ニューディール・カルチャー」と呼ばれる独自の時代文化の形成があった。
長年購読している雑誌のひとつに、危機の時期に記された日記類には、後代の人々にとって慰めや新たな発想の源となりうるものが含まれているとの短い記事*が掲載されていた。
* ’The lives of others’ The Economist May 23th-29th 2020
第一次大戦期の日記
そこでひとつの例として挙げられていたのは、ヴァージニア・ウルフ Virginia Wolf *の日記であった。約30年にわたる日記が残されている。この作家の日記はしばしば戦争によって、ブックエンドのように区切られている。彼女が未だ若かった頃、第一次世界大戦(1914 年7月から1918年11月)の時期に記された日記では、他の人々、場所、書籍についての観察は、しばしば意地悪く、偏見が含まれていた。時には歪み、辛辣でもあった。今は知る人も少なくなった1917年のロンドン大空襲の時、彼女は自宅のキッチンで仕事をしていた。
The Diary of Virginia Woolf, Volume 1: 1915-1919 , 1979
N.B.
* ヴァージニア・ウルフ Virginia Woolf (1882年 - 1941年)は、 [イギリスの 小説家 、 評論家、書籍の出版元であり、20世紀 、モダニズム文学の主要な作家の一人。両大戦間期、ウルフはロンドン文学界の重要な人物であり、 「ブルームズベリー・グループ」の一員であった。ジョン・メイナード・ケインズもそのひとりだった。
ウルフの代表的小説には『 ダロウェイ夫人』 Mrs Dalloway (1925年)、『 灯台へ』To the Lighthouse (1927年) 、『 オーランドー』 Orlando (1928年)などがある。
第二次大戦期の日記
第二次世界大戦(1939年9月– 1945年9月)の時期、1940年10月、モダニストとしての名声を確保したウルフは、イギリス、サセックスの自宅で仕事をしていた。この戦争の時代について、彼女はなんとなく積極的、ポジティブな心を保っていたと振り返っている。村の狭い範囲での生活に小さくなっていた時にはおかしなことではあった。暖房などに使う薪は十分買ってあった。友人たちは暖炉の火で隔離されていた。車もなく、ガソリンもなく、列車の運行も不確かだった。それでもウルフ夫妻は素晴らしい自由な秋の島を楽しんでいたと記している。村での静かな日々に心の癒しや慰めも感じていたようだ。
それからほぼ5ヶ月後、彼女は別の精神的挫折を感じていた。彼女は遺書を残し、コートのポケットに石を詰め、ウーズ川に身を沈めていた。1941年3月末のことだった。
日記はこうした日々に複雑に揺れ動く微妙な心の動きを記しているが、混沌の中に美も見出していた。1904年の父の死去の頃から、ウルフは生涯を通して周期的な気分の変化や神経症状に悩まされた。大変繊細なところもあり、心は絶えず揺れ動き、「落ち込み」depression は頻出する言葉だった。それでも、文筆活動は一生を通してほとんど中断することなく続けられていた。天才的な芸術家にしばしば見られる性向でもあった。しかし、彼女が終生悩まされた病については議論があり、明らかではない。
ウルフはユダヤ人の夫レナードと幸福な結婚をしていながらも、日記に「私はユダヤ人の声が好きではない。ユダヤ人の笑い方も好きではない」と書いている。また、ウルフはレナードのユダヤ人であることを嫌がった自分は「 スノッブ」だったと回想している。こうした点もウルフの複雑な精神状態を伝えている。
ブログの時代
ヴァージニア・ウルフは、ブログ筆者は特に好んで読んできた作家ではない。しかし、かつて過ごしたケンブリッジでの生活の間、何人かの日本からの英文学研究者に出会ったが、そのほとんどがウルフを研究対象にしていることに驚かされた。そうしたこともあって、暇な折に代表的といわれる小説だけは読んでいた。自分で車を運転してサセックスまで行ったこともあった。日記も公刊されていたことは知っていたが、文学は専門でもなく、立ち入って読んだことはなかった。
今回、偶然にウルフの日記に言及した記事に出会い、この複雑で揺れ動いた精神状態の持ち主であった優れた女性作家が記した日記は、彼女の最善と最悪の精神状態を包み隠さず、読者にも自分たちだけが悩み苦しんでいるのではないことを知らせてくれる。さらに、暗い時代でも時には喜びの瞬間もあることを伝えてくれる。I T上にブログが溢れる今の時代も、次の世代の人たちから見ると、「新型コロナウイルス」大不況期として、固有な特徴を持ったひとつの時代として回顧されるかもしれない。