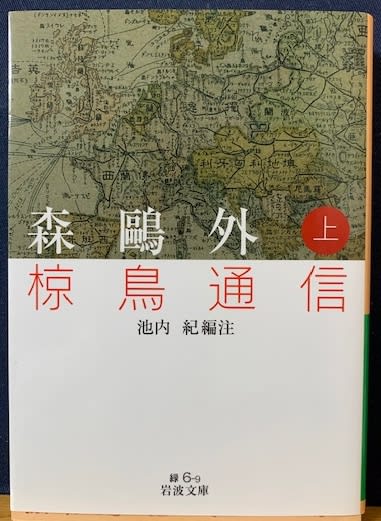西周肖像
森林太郎「西周伝」『鷗外全集』第3巻、岩波書店、1972年、国立国会図書館コレクション
英語のencyclopediaは、日本語ではさしづめ「百科事典」とでもいうことになるだろうか。ところが、その語源を訪ねると、「子どもを輪の中に入れて教育する」という予想もしない意味になる*。今回の話はそこから始まる:
英國の Encyclopedia なる語の源は、希臘のΕνκυκλιος παιδειαなる語より來りて、即其辭義は童子を輪の中に入れて教育なすとの意なり。故に今之を譯して百學連環と額す。
(西周「百學連環」第1段落第1-2文)
英語の Encyclopedia という語は、古典ギリシア語のΕνκυκλιος παιδεια〔エンキュクリオス・パイデイア〕に由来しており、それは「子どもを輪の中に入れて教育する」という意味である。そこで、これを「百学連環」と訳して掲げることにしよう。
(上掲部分現代語訳:山本貴光、p.481)
*「輪の中の童子」が「円環を成した教養」となり、西先生の「百学連環」となるかは、上掲の山本氏の推論が大変興味深いので、山本著該当部分(第2章)をぜひお読みいただきたい。
安易な教養ブーム
この数年、書店の棚を見ると「教養」の必要性、身につけ方を掲げた本が多数目につくようになった。しかし、その多くは雑学本に近く、中には一日1ページを読み、一年後読了するころに教養が身に付きますと麗々しく記した本もある。
さらに最近はリベラルアーツ論も目立つようになった。リベラルアーツというと、筆者には前々回に取り上げた西周、さらに筆者が訪問したアメリカでのいくつかのリベラルアーツ カレッジが思い浮かぶ。筆者がかつて在学した総合大学は、この分野の草分けともいえる大学のひとつだが、新しい形でのリベラルアーツ教育が、絶えず試みられてきた。
この数年、書店の棚を見ると「教養」の必要性、身につけ方を掲げた本が多数目につくようになった。しかし、その多くは雑学本に近く、中には一日1ページを読み、一年後読了するころに教養が身に付きますと麗々しく記した本もある。
さらに最近はリベラルアーツ論も目立つようになった。リベラルアーツというと、筆者には前々回に取り上げた西周、さらに筆者が訪問したアメリカでのいくつかのリベラルアーツ カレッジが思い浮かぶ。筆者がかつて在学した総合大学は、この分野の草分けともいえる大学のひとつだが、新しい形でのリベラルアーツ教育が、絶えず試みられてきた。
西は明治時代にリベラルアーツを「藝術」という訳語として造語した。現代の用法からすると、いまひとつという感じはあるが、日本におけるリベラルアーツ議論に際しては、明治の啓蒙家としての西の思想と努力を欠かすことはできない。リベラルアーツは、元来ビジネスマンに必要な知識、あるいは社会人として身につけるべき教養といった軽い意味のものではない。そこにはギリシャ、ローマ時代以来の長い歴史が脈々と存在するものであることは、西周の著作などを通して筆者も感じ取っていた。
かなり以前の話である。ブログ筆者が世紀の変わり目に当たり、所管することになった大学で、近い将来、大学が目指すべき姿を提示したいと思った。そこでの目標のひとつは、新たな時代環境で考えうるリベラルアーツを基盤とする教育の再編・充実であった。ギリシャ、ローマの時代へ戻そうというのではない。歪みに歪んでしまった日本の大学教育に小さな梁を入れたいと思ったに過ぎない。そのために、明治期に学園創設者が熱意を持って説いた学問の世界についてのヴィジョン、その体系化に、教職員の注意を集めたいと思った。
日本の大学の危機が次第に認識されるようになった21世紀の初頭に当たり、今後の教育の指針を示すことが、教育、運営の責任を負う者の責務であるとの思いが背景にあった。不完全なものであっても、海図と羅針盤なしに激動する教育の世界を漂流することは無責任だと感じた。
言い換えると、大学の未来をいかに設定すべきかという課題である。それまで日本の大学は、国公私立の別を問わず、総じて時代の成り行きに任せ、入学希望者の増加するままに拡大してきたという傾向が多分にあった。教職員の間でも、自分が勤務する大学の将来をどう構想するかという思いは希薄だった。
形骸化が進んだ「般教」
各大学の置かれたポジションで異なってはいたが、総じて大学教育のあり方について、深く考え、検討するという空気はあまり感じられなかった。事態は深刻であった。筆者は大学に勤務する前に日本・外国の企業、国際機関など、異なった組織風土を体験していたが、日本の大学ほど改革が難しい組織も少ないと感じていた。大学は潰れることはないと思い込んでいる教員も少なくない。
ひとつには、大学における一般教養課程については、形式的な面で制度改革が一段落し、多くの大学が専門課程に進むに先立って、一般教養科目(教養課程)の整備を済ませていて、改革の必要はないと思い込んでいる教員も少なくなかった。。しかし、大学は激しい競争の渦中にあることは紛れもない事実なのだ。そうした中で一部の大学を除き、建物などの建造、改築は進むが、教育内容の充実は進度が遅かった。
当時から日本の多くの大学では、一般教養課程は専門課程よりも一段下という評価がいつの間にか出来上がってしまい、しばしば「般教」の名で学生の間にも軽視する風潮が広がっていた。大学の重点は専門課程にあるので、「般教」は早く済ませたいという受け取り方が強かったように思えた。
確かにリベラルアーツを日本語に訳すと「教養教育」が最も近い。しかし、リベラルアーツはしばしば一般教養課程と重ねて考えられがちな従来型の教養教育とは全く別物なのだ。
かなり以前の話である。ブログ筆者が世紀の変わり目に当たり、所管することになった大学で、近い将来、大学が目指すべき姿を提示したいと思った。そこでの目標のひとつは、新たな時代環境で考えうるリベラルアーツを基盤とする教育の再編・充実であった。ギリシャ、ローマの時代へ戻そうというのではない。歪みに歪んでしまった日本の大学教育に小さな梁を入れたいと思ったに過ぎない。そのために、明治期に学園創設者が熱意を持って説いた学問の世界についてのヴィジョン、その体系化に、教職員の注意を集めたいと思った。
日本の大学の危機が次第に認識されるようになった21世紀の初頭に当たり、今後の教育の指針を示すことが、教育、運営の責任を負う者の責務であるとの思いが背景にあった。不完全なものであっても、海図と羅針盤なしに激動する教育の世界を漂流することは無責任だと感じた。
言い換えると、大学の未来をいかに設定すべきかという課題である。それまで日本の大学は、国公私立の別を問わず、総じて時代の成り行きに任せ、入学希望者の増加するままに拡大してきたという傾向が多分にあった。教職員の間でも、自分が勤務する大学の将来をどう構想するかという思いは希薄だった。
形骸化が進んだ「般教」
各大学の置かれたポジションで異なってはいたが、総じて大学教育のあり方について、深く考え、検討するという空気はあまり感じられなかった。事態は深刻であった。筆者は大学に勤務する前に日本・外国の企業、国際機関など、異なった組織風土を体験していたが、日本の大学ほど改革が難しい組織も少ないと感じていた。大学は潰れることはないと思い込んでいる教員も少なくない。
ひとつには、大学における一般教養課程については、形式的な面で制度改革が一段落し、多くの大学が専門課程に進むに先立って、一般教養科目(教養課程)の整備を済ませていて、改革の必要はないと思い込んでいる教員も少なくなかった。。しかし、大学は激しい競争の渦中にあることは紛れもない事実なのだ。そうした中で一部の大学を除き、建物などの建造、改築は進むが、教育内容の充実は進度が遅かった。
当時から日本の多くの大学では、一般教養課程は専門課程よりも一段下という評価がいつの間にか出来上がってしまい、しばしば「般教」の名で学生の間にも軽視する風潮が広がっていた。大学の重点は専門課程にあるので、「般教」は早く済ませたいという受け取り方が強かったように思えた。
確かにリベラルアーツを日本語に訳すと「教養教育」が最も近い。しかし、リベラルアーツはしばしば一般教養課程と重ねて考えられがちな従来型の教養教育とは全く別物なのだ。
リベラルアーツは「般教」ではない
リベラルアーツの原義は、「人を自由にする学問」、「自由学科」のことであり、それを学ぶことで、自由人たる思考・行動の素地が身につくとされてきた。
筆者はたまたまアメリカ、イギリスなどで、研究・教育の機会を経験したが、彼の地で共有されているliberal arts のイメージと内容は、日本で使われている教養教育とは大きく乖離していた。
筆者はリベラルアーツ論の源流に立ち戻って、マンネリ化しつつあった教養課程活性化のための教職員の理解を深めたいと考えた。そこで出会ったのが、西周の著作集だった。大学執務の傍ら、手に取った著作の中に「百学連環」*があった。文章全体は決して長いものではないが、文語体にギリシャ語、英語の引用が混じり、現代人にとってはかなり難渋する部分がある。それでも丁寧に読むと、明治人が感じとった当時の西洋の学問体系の地平が見えてくる気がした。それから150年余りを経過した今日、学問の世界はどのように展望できるのだろう。
「百学連環」は西周の著作を集めた全集の第4巻(宗高書房、1960-1981年)などに収められている。しかし、明治期の文語体で書かれた著作は現代人にはかなりハードルが高いものになっている。『即興詩人』など森鴎外の著作の現代語訳が求められる時代である。それでもその後刊行された現代語訳などを参考に読めば、理解に困難を感じることはないだろう。
その後、大学を退職し自由な身になった時にふと手に取った書籍が、山本貴光氏による「百学連環を読む」であった。大変興味深く読了した。ややマニアックな感はあるが、「百学連環」の最善のコンメンタールであると推薦に値する。著者の絶え間ない探索力に支えられた旺盛な思索の過程を辿ることができ、長らく忘れられてきた明治の啓蒙家が描いた学問の世界のマップ・地平のイメージが目に浮かぶようになる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
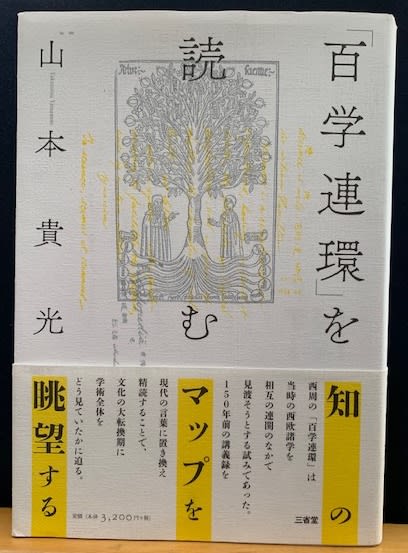
山本貴光「百学連環を読む」三省堂、2016年
改めてこの労作を読み返し、もう少し早く刊行されていたならば、と思ったことしきりであった。世俗化し、本来の方向とは別の方向へ走り、定着してしまった日本での「リベラルアーツ」の概念を正しい道に引き戻すことは容易ではない。筆者の始めた試みも、全学共通カリキュラムの導入などに多大な時間をとられてしまった。新たな時代におけるリベラルアーツ再興への関心も育たなかった。数は少ないが、一部の大学は積極的にこの方向へ移行の努力をされ、成功を収めつつある。
リベラルアーツは本来「自由の技術」であり、(一般)教養とは大きく異なる。そこにはギリシャ、ローマ以来の長い語源上の歴史が存在している。現代において『百学連環』の輪郭はどう描けるのだろうか。
リベラルアーツは本来「自由の技術」であり、(一般)教養とは大きく異なる。そこにはギリシャ、ローマ以来の長い語源上の歴史が存在している。現代において『百学連環』の輪郭はどう描けるのだろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
N.B.
リベラル・アーツの起源は古代ギリシアにまで遡り、自由人としての教養であり、手工業者や商人のための訓練とは区別されてきた。古代ローマにおいては、技術(アルス ars)は自由人の諸技術・方策( artes liberales)と手の技である機械的技術・方策(artes mechanicae)に区別されていた。前者を継承するのが「リベラル・アーツ」である。人間社会のさまざまな制約から自らを解き放ち、自由人として生きるための技術と言える。
ローマ時代の末期にかけて、自由技術は七つの科目からなる「自由七科」(septem artes liberales)として定義された。自由七科はさらに、主に言語にかかわる3科目の「三学」と主に数学に関わる4科目の「四科」の二つに分けられた。 それぞれの内訳は三学が文法・修辞学・弁証法(論理学)、四科が算術・幾何・天文・音楽である。音楽がここに入るのは不思議な感じもするが、当時は技術の範疇に含まれていた。哲学はこの自由七科の上位に位置し、自由七科を統治すると考えられた。
その後、時代が下り、13世紀のヨーロッパで大学が誕生した当時、自由七科は学問の科目として公式に定められた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
激動する現代社会において、世界を見通す手がかりとして、150年近い時空を遡り、日本が理想に燃えていた明治期の啓蒙思想家の知の世界の展望を再体験することは、見え難くなった世界への新たな可能性を提示もしてくれる。西周は当時のオランダ、ライデン大学におよそ2年間滞在し、西欧世界の学問の体系と輪郭を確認し、帰国後日本に生かすための基盤材料とすることを企図していた。そのためには、先進地域である西欧の学問の体系、その輪郭を確定し、学問相互の間の関係を理解することに努めた。「百学連環」の表題はその作業にふさわしい。
複雑さを増し、行動が制限されることが多くなった今日、制約が多くなり生きにくくなった社会で、自らの力で壁を乗り越え、切り開き、自由な発想で生きてゆく術を考えることは、学問に携わる者、これから激動する世界で生きる者にとって、必要なことなのだ。専門化が進み、学問の全体俯瞰ができなくなっている複雑な世界であるからこそ、「百学連環」の視点が必要になっている。西周が現代に立ち戻ったとしたら、いかなる展望と内容で学問の体系を提示してくれただろうか。晩夏の時を迎えたブログ筆者の真夏の夢の一齣である。