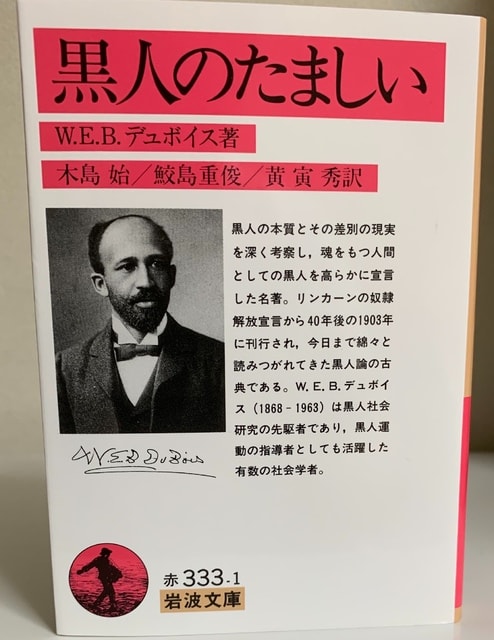世界レベルでの新型コロナウイルスが蔓延するに従って、混迷の度は日に日に高まり、将来への不安も強まっている。偶然に見たTV番組『ズームバック 落合陽一/エコノミー」(教育TVl2020年6月25日)で考えさせられた。といっても、ブログ筆者は、教育、メディア・アーティストその他の分野で多彩な活動を展開しているこの人のことをほとんど全く知らない。
番組の目的は混迷した時代の「半歩先を読む」ということにあるらしい。稀代な天才と言われる若者がその課題に挑戦するというのがウリのようだ。番組自体は詰め込み過ぎで、理解するには苦労した。テーマに掲げられた時代の「半歩先を読む」ということは、「一寸先は闇」といわれる複雑怪怪な世の中で、いかなる天才であっても科学的な意味では不可能に近い。しかし、ブログ筆者も多少記したことはあるが、長い歴史軸の延長上に起こりうるリスクをある程度の確率で予想することは全く不可能というわけではないと思う。
進行のテンポが早すぎ、理解にやや困難を感じたが、番組の中で落合氏が「大恐慌の時に人々がいかなる生活をしていたか」ということを知りたいと述べていたことに、あれと思った。最近、このブログで筆者が細々と試みていることは、1930年代のアメリカに始まり世界に拡大した「大恐慌」the Great Depressionの時代に立ち戻り、人々の生活実態など、実際にいかなる時代であったかを不完全ながらも推察してみたいということにあった。
これまで残っていた記録や伝承に見る限り、この時代は大恐慌の最中であり、企業の倒産、破産、失業、病気など暗いイメージで塗りたくられていた。
しかしウオール街の株式大暴落から始まった1930年代の現実に見る限り、アメリカでは株式市場の低迷、失業者の増大などの暗い実態が存在したにもかかわらず、「1930年代文化」と称されるように、文学、演劇、音楽、スポーツなどの文化活動は予想を裏切り、さまざまに花開いていた。
今日、われわれの生活に溶け込んでいるさまざまな技術、製品なども、この時代に発明、発見されているものが多い。建築分野でも、歴史的建造物として今に残るクライスラービル、コカコーラ本社、ゴールデンゲートブリッジなどもこの時代に建造されている。さらに、この大恐慌期を締めくる1941年の真珠湾攻撃から始まる世界大戦に備えた軍事的開発が多方面で展開していた。
当時の日本は迫りくる大戦の予兆を感じつつ、国民は暗く不安な時代を過ごしつつあったが、アメリカの大恐慌期は、圧倒的な軍事力を背景に世界に君臨していたこともあり、大恐慌期にあっても、独自の豊かな文化的発展があったことが最近の研究で明らかになったいる。前回記したのは、その中での文学的側面であった。
生活文化の開花
さて、このたびの新型コロナウイルス感染を避ける自粛期間の間に目立ったことのひとつは、TVや新聞などのメディアで、家庭における調理や料理の番組が急増したことだ。ウイルス感染を防ぐためにできうる限り、不要不急な外出を避け家庭に留まるという必要から、ある意味では当然のことであるかもしれない。
そんなことを考えながら、古い資料を片付けていると、少し興味深い記事が目に止まった。アメリカ人の好きなホット・ドッグ、グリルド・チーズ・サンドウイッチ、ミルクシェーキ、チョコレート・チップ・クッキーなどは、ほとんどが大恐慌期の1930年代に生まれた食べ物らしい。
人気を呼んだクッキー
今回取り上げるチョコレート・チップ・クッキーは、今からおよそ82年前の1938年にマサチューセッツ州ウイットマンにあった著名なレストラン、トルハウスを経営していたルース・ウエイクフィールド夫妻が作り出したレシピから生まれたといわれている。このクッキーは最初はアイスクリームの付け合わせとされていたが、その後急速に独自の菓子として有名になった。1939年末、夫妻はこのレシピによる商品化を図るが、無償でネスレ社にレシピを譲渡してしまった。夫妻にとっては、取り立ててユニークさを誇示できないと思ったらしい。実際、その頃までには評判を聞きつけて、およそ75種類のクッキーのレシピが世に出ていた。
こうした夫妻の謙虚な考えにもかかわらず、クッキーの評判は高まるばかりで、アメリカ人にとって大好物なスナック、果てはワインのつまみとして、大変な評判を勝ち得たのだった。
話題のToll House レストランは1984年の大晦日に火災で焼失してしまったが、レストラン店主は店の中に小さな展示場を設置してウエイクフィールド夫妻とトル・ハウスの功績を今に残している。
史料の筆者は、店でクッキーを頼むのもいいが、まず家でレシピに従いこの歴史的なクッキーを自分の手で作ってみなさいと勧めている。ネットで調べてみると、確かに多くのレシピが公開されている。ご関心のある向きは試してみられると、1930年代のアメリカ食文化の一端に触れることができるだろう。
Source:
’SWEET MORSELS: A HISTORY FO THE CHOCOLATE-CHIP,’ (By Jon Michaud, December 19, 2013
[Vintage chocolate chip cookies recipe | BBC Good Food](https://www.bbcgoodfood.com/recipes/vintage-chocolate-chip-cookies)