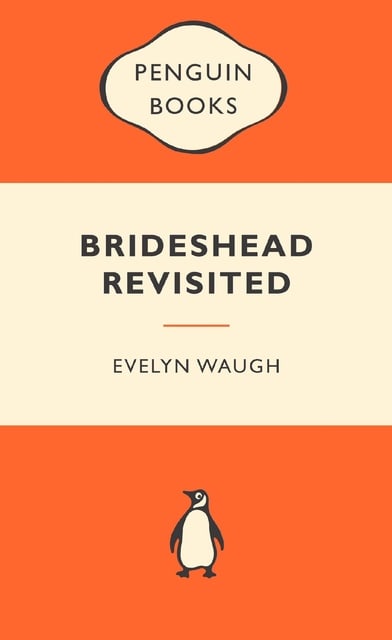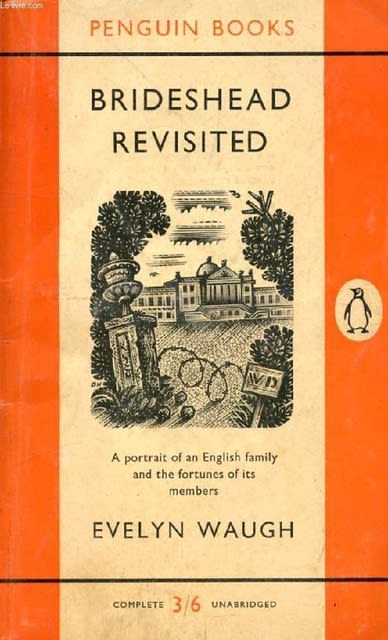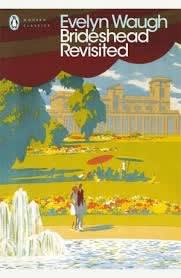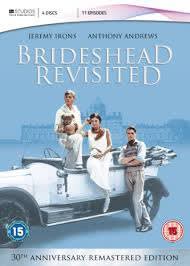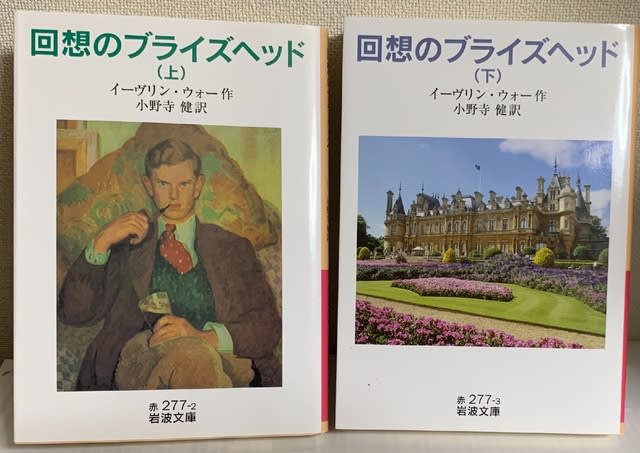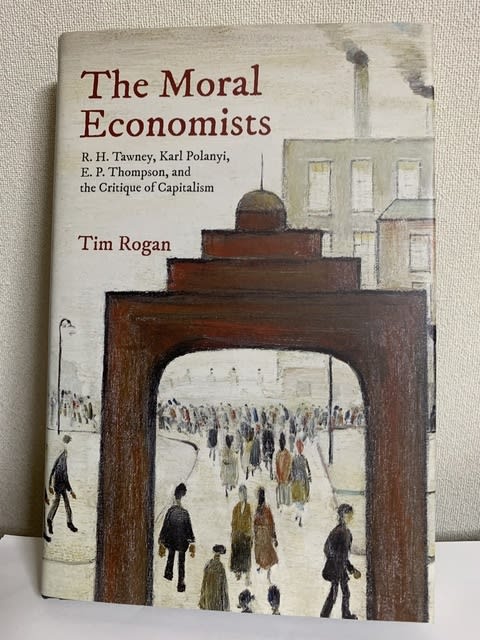J.M.W.Turner, Peace – Burial at sea
oil on canvas, 87x86,5cm
Tate Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856
exhibited 1842
J.M.W. ターナー 《平和ー海での水葬》
Tate Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856
exhibited 1842
J.M.W. ターナー 《平和ー海での水葬》
英国ロマン主義の巨匠ジョセフ・マロード・ウイリアム・ターナー(J.M.W.Turner:1775~1851)の名前は、日本人の間にいつごろ知られるようになったのだろうか。筆者の場合、やはり夏目漱石の「坊っちゃん」に出てきたことで、その名を知ることになった。あの有名な場面である。
「あの松を見給え、幹が真直で、上が傘のように開いてターナーの画にありそうだね」と赤シャツが野田にいうと、野田は「全くターナーですね。どうもあの曲り具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ」と心得顔である。ターナーとは何の事だか知らないが、聞かないでも困らない事だから黙っていた。――『坊っちゃん』(1906年)
「あの松を見給え、幹が真直で、上が傘のように開いてターナーの画にありそうだね」と赤シャツが野田にいうと、野田は「全くターナーですね。どうもあの曲り具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ」と心得顔である。ターナーとは何の事だか知らないが、聞かないでも困らない事だから黙っていた。――『坊っちゃん』(1906年)
その後の人生で、ターナーの作品にはかなり出会った。特に、17世紀の画家たちの世界に深い関心を抱き、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールと同時代のロレーヌ出身の理想的風景画家クロード・ジュレ(ロラン)の作品を探索していた頃、クロードから大きな影響を受けたターナーについてかなり知見を深めることができた。ちなみに、イギリスではクロード・ジュレは、クロードとファースト・ネームで呼ばれる事が多い。いうまでもなく、ターナーは今ではイギリス屈指の国民的画家である。
比較的最近では、筆者の知るかぎりでは、下記の企画展*が晩年の画家の作品を展示した。会場のテート・ブリテンはターナーが国に遺贈したほぼ全作品と関連資料を所蔵している。いわばターナーの殿堂である。画家の作品数は極めて多い
*特別展「LATE TURNER PAINTING」。2014年9月10日~2015年1月25日開催。
筆者にとって、画家の作品で印象に残るものがいくつかある。そのひとつが、ここに掲げた《平和ー水葬》(Peace - Burial at Sea) と題した画家晩年の名作である。長年、仕事場の壁にポスターを掛けていた。そして昨年急逝したイギリス人の友人WBも同じようにしていたことをふとしたことで知った。本年4月にケンブリッジで追悼の会が開催されるはずであった。
画面中央へ配されているのは汽船(帆布も併用する蒸気船?)と思われる。そこには立ち上る黒煙と共に深い影が落ち、帆先の部分まで黒色で支配されている。そして汽船を分断するかのように一本の光の筋が縦に入れられ、観る者の視線を強く惹きつける。さらに画面上部にはやや白濁した色の空が広がり、また画面下部では汽船を反射し黒ずむ水面が描き込まれている。しかし、画題がなにであるかは、説明がないと分かり難い。一見したかぎりでは、なにを描いたかすぐには分からない不思議な作品である。
中央部の煙突のようなものからは黒い煙のようなものが吹き出している。画面全体は黒色系統の暗色が支配しているが、焔のような光源で照らし出された船体、空などが画面にかなりの明るさを与えている。船上では何が起きているのか明らかではない。
もともと本作品は、八角形の画面で展示・公開されていた。色彩について最も注目すべき点は、晩年期のターナーの特徴とされる黒色の使用にあるとされる。本作の対画として展示されたナポレオンの晩年を描いた《戦争-流刑者とあお貝》に用いられている燃えるような赤色や黄色の色彩と対照的に、この作品では青色を始めとした黒色など、寒色系が主色として使用されている。この色彩使用は画家も読んでいたヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『色彩論』に記される「青色・青緑色・紫色は落ち着き無く、過敏で不安な色彩」の具現的描写であると考えられている。また当時としては「不自然な暗さ」と批判も大きかった汽船部分に用いられている黒色は、画家の死に対する不安を象徴していると推定されている。
この作品の対画となる『 戦争-流刑者とあお貝』(別の機会に取り上げたい)と共に1842年のロイヤル・アカデミーで発表された本作は、ターナーのかつてのライヴァルであり、数少ない良き友人のひとりでもあった画家サー・デイヴィッド・ウィルキーが、1841年に汽船オリエンタル号の船旅での途中に起こった海上事故で没し、ジブラルタル沖合へ水葬されたことに対する追悼の含意が込められた作品である。同じくウィルキーの友人であった画家仲間のジョージ・ジョーンズが船上の情景を素描し、その素描に基づいてターナーが本作を仕上げたことが伝えられている。
もともと本作品は、八角形の画面で展示・公開されていた。色彩について最も注目すべき点は、晩年期のターナーの特徴とされる黒色の使用にあるとされる。本作の対画として展示されたナポレオンの晩年を描いた《戦争-流刑者とあお貝》に用いられている燃えるような赤色や黄色の色彩と対照的に、この作品では青色を始めとした黒色など、寒色系が主色として使用されている。この色彩使用は画家も読んでいたヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『色彩論』に記される「青色・青緑色・紫色は落ち着き無く、過敏で不安な色彩」の具現的描写であると考えられている。また当時としては「不自然な暗さ」と批判も大きかった汽船部分に用いられている黒色は、画家の死に対する不安を象徴していると推定されている。
この作品の対画となる『 戦争-流刑者とあお貝』(別の機会に取り上げたい)と共に1842年のロイヤル・アカデミーで発表された本作は、ターナーのかつてのライヴァルであり、数少ない良き友人のひとりでもあった画家サー・デイヴィッド・ウィルキーが、1841年に汽船オリエンタル号の船旅での途中に起こった海上事故で没し、ジブラルタル沖合へ水葬されたことに対する追悼の含意が込められた作品である。同じくウィルキーの友人であった画家仲間のジョージ・ジョーンズが船上の情景を素描し、その素描に基づいてターナーが本作を仕上げたことが伝えられている。
本作品がロイヤル・アカデミーで発表された際のカタログには「真夜中の光が蒸気船の舷側に輝き、画家の遺体は潮の流れに委ねられた-希望の挫折」との一句が共に掲載された。画題につけられた「 Peace 平和」とは亡き友の鎮魂を祈る画家の心情なのだろうか。
折しも新型コロナウイルス禍に世界が揺れ動く時、この作品に接した人たちはいかなる印象を受けるだろうか。先の見えない現実を前に、多くの人たちが「希望の挫折」を感じる中で、この作品を見る人たちはなにを感じるだろうか。「平和」それとも迫りくる時代への「不安」のいずれだろうか。