
高齢化の影響で、全国の大病院の混雑ぶりはすさまじい。外来受診の日は、朝から1日かかりという患者もいる。当然、対応する医師や看護師などスタッフの負担も大きい。このごろの勤務医離れ、開業医志向には、こうした労働実態も反映していると思われる。医師、とりわけ勤務医、看護師の労働条件は、想像以上に厳しい。
人気上昇の医学部
医療の地域間格差が拡大する中で、医学部志望者が急増している。少子化で大学入学人口が減少、私大の4割は定員割れと言われる中で、本年度の医学部志望者数は10万人(延べ人数)を上回ったと推定されている。
全国の国公立大学と私立大学の80の医学部(医学科、防衛医大を含む)の定員は約7700人だが、志願者数は04年度入試では10万人を突破し、05年度入試は10万6千人近くになった。2000年度入試では約8万9千人だったから、大幅な増加となる。医学部の入学式に何度か出席した印象では、合格した本人はいうまでもないが、親や親族などの喜びようも並大抵ではなかった。
人気の裏側
他方で同じ期間に大学・短大の志願者数は約9万2千人減少した。こうした医学部人気の背景には何があるのだろうか。
その裏側はかなり複雑である。考えられる大きな理由のひとつに将来に対する不安感があるとみられる。「失われた10年」の後、日本経済は漸く回復の兆しが見られるようになったが、格差拡大、将来への漠然たる不安は若い世代にも広く浸透している。 医師になれれば、生活も安定し、一生安心という見方が、受験生世代や親たちのかなり有力な見方らしい。
同じことが法科大学院の場合にも見られた。もっとも、こちらの方はかなり幻想に近いことが分かってきたようだ。法科大学院へ入学しても、新司法試験の合格率は、設立当初の予想よりもかなり低くなることが明らかになった。法科大学院は間もなく厳しい淘汰の過程に入ることは間違いない。
多額な投資
他方、医学部は学費に大学によって大きな差異があることに加えて、修業年限も長く、一人前といわれる医師になるためには他の職業とは比較にならないほど投資も必要である。負担額が少ない国公立大でも入学金30万円くらい、年間授業料は50万程度。私立大では入学金100-200万、年間授業料は200-300万、さらに施設費などが200-700万と、負担は大きい。医師として自立できるまでの修業年限も長い。私大医学部の場合、6年間の学費だけでも、2005年で2千万から4千万円台という巨額である。教科書や実習費用なども他学部よりもはるかにかかる(一部にはこうした負担もさほど気にならない、裕福な家庭の子弟も相当いる)。
したがって、自治医科大学などの場合を別にして、両親や家族などの負担も大きい。いきおい期待も大きくなるのだろう。裕福な開業医などの子弟も多い。私大の医学部キャンパスの学生用駐車場には、高級車が多数並んでいたりする光景も珍しくない。
医学部ブームの背後では、かなりの経済計算がなされている。大きな負担を上回るベネフィットがあると思われている。適性などに関係なく、医学部合格がひとつの目標になっている側面もある。有名大学への合格者数を誇る高校の尺度が、医学部合格者数へ移っている面もある。
医師に要求されるもの
医療は仁術といわれてきたように、医師という職業には、専門能力に加えて、高い倫理性やコミュニケーション能力などが要請される。ペーパーテスト中心の入学試験などでは、計りきれない人間としてのさまざまな能力が必要である。受験の成績と医師としての適性・人格とはほとんど関係がない。現実に、医師になるまでの過程での脱落者も多い。研究はできても、診療ができない医師もいる。街中のクリニックを見ても、順番待ちで大変混雑しているところと、閑古鳥が鳴いているところがある。患者側の選別の目も厳しい。
医療の世界の進歩も急速である。医師も絶えず自分の技量を磨き、時代に遅れないようにしなければ職業生活がまっとうできない。一度、医師免許を取得したら、その後は自動更新できるという制度は検討を迫られている。
高校生の年齢で医師の職業生活の実態と求められる要件について、十分見通すことはきわめて難しい。親たちの判断も必ずしも当てにならなくなっている。
医学部をメディカル・スクールとして再編し、広い視野と検討に基づいて専門課程への進学方向を選択する専門大学院型の教育システムへの転換が、より明確に実施されるべきではないだろうか。受験競争の渦中では視野が狭小になりがちで、しばしば誤った選択を招きかねない。いかなる職業にもいえることだが、優れた医師への道は決して平坦ではない。医学部ブームが法科大学院のような失敗につながらないよう望みたい。
Reference
「時時刻刻 医学部シフト過熱」『朝日新聞』2006年7月25日


















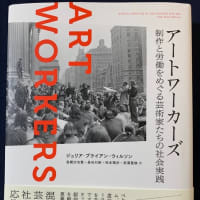







前まで法務教官として、ある医療少年院で働いてましたが、合わなくてすぐ辞めちゃいました(^_^;)こんな自分ですが、よかったら友達になってほしいです。よろしくね(^-^)
http://blog.livedoor.jp/keijikun/
自分にとってこれが「適職」と思えるまでには、多分かなりの試行錯誤、模索の過程が必要なのではないかと思うようになりました。自分のやりたいことと、仕事が合致している人は百人に一人もいないといわれるくらいですから。多くの人は、さまざまな不満を抱えながらも、なんとか折り合いをつけて生きているのではないでしょうか。それが人生なのかな。
私自身、いくつかの職業遍歴を経験しました。回り道をしたようですが、多くの世界を経験できてよかったと思っています。ポジティブ志向で行きましょう。
これは、自分の卒業大学で、実証済みです。
医師には、コミュニケーション能力は要りますが、患者さんとのコミュニケーションには、ものすごい記憶力(記憶保持力)が必要ですので、記憶力がないと、患者さんの信頼がすぐに落ちます。それは、残念ながら、大学受験のセンター試験の得点と比例してしまいます。
自分の印象ではセンター試験の正答率が75%を下回ると、医学部の勉強についていけなくストレートで医師になれない方が優位に増える、そんな感じですね。
医師国家試験に一回落ちた人は、多浪する傾向にありますので、それはそのまま、医師の適性といってもいいでしょう。
倫理性は確かに成績関係ないないね。
だから、自分は面接だけで、医学部の受験をパスしてしまうのは、反対だなあ。少なくとも、センター試験75%で足切りはすべきとは思いますね。
大変興味あるコメント、有り難うございます。
友人の医学部教授(60代)から、自分たちの医学生時代と比較して、今の医学生は100倍近い情報・知識を要求されているという話を聞きました。患者さんとのコミュニケーション能力と記憶力の関係も、なるほどと思いました。
ところで、面接だけで医学部の受験をパス?してしまうような大学があるのでしょうか。これからの医師には知的能力に加えて、時に患者の側に立って考えることもできるような人間性の充実が、他の職業以上に必要な気がします。ペーパーテストの成績だけでなく、できるだけ時間をかけて医師としての適性をインタビューで計ってほしいと思っています。
追々思ったことを書き込みたいと思います。長々とすみません