松平容保公については様々な評価があります。
名君という評価から、酷いのになると「バカ殿」なんてものまで、ホントに様々だ。
まあ、「バカ殿」は論外にしても、「名君」と言い切ってしまうのも、私はちょっと違うような気がする。まあ、いずれであるにせよ、
私は人間として、この方を尊敬します。
【志には虚邪無く、行いは必ず正直にす。游居するには常あり、必ず有徳に就く】(原漢文)
容保公が起居した京都黒谷の金戒光明寺に遺した墨書です。意味としては「志には虚(いつわり)や邪(よこしま)なこころがなく、行いは必ず正しく真っ直ぐにして、外出した時も家にいる時もその言行が一定のきまりに従っており、必ず徳の高い人(孝明天皇)に就き従う」(星亮一氏訳)というものです。
天皇のため身命を賭して忠節を尽くす。容保公のこころざしであり、本当にこの通りに生きた。
会津藩の藩是は徳川幕府に忠節を尽くすこと。しかし会津藩主は代々神道を学んでおり、当然天皇をこの国の頂点と捉えます。幕府に忠節を尽くすことはイコールで天皇に忠節を尽くすことになる。容保公はこれを真っ直ぐに信じた。真っ直ぐに貫こうとした。その真摯な姿勢が孝明天皇の心を打ち、御宸翰(天皇直筆の書状)を賜るという栄に浴する。容保公は身が打ち震えるほどの感激を味わったことでしょう。
この正直さが、容保公を苦しめることになる。なんともやるせない話ではありますが、容保公がもうすこし融通の利く、ある程度処世術をわかっている人物であったなら、幕末の会津藩の悲劇は、無かったとは言わないまでも、もう少し様相は違ったものになっていたかも知れない。そういう意味で、名君とまでは言い切れないものが、私の中にはあるのです。
しかし、こういう人物だったからこそ、会津武士道は、会津の“こころ”は、後世にまで語り伝えられたのだ、とも言えます。この藩主だったからこそ、会津藩士たちは武士らしく生き、武士らしく死ねたのだ。彼ら藩士達は満足だったと思います。
会津藩は、容保公は、賊軍の汚名を晴らすため、そしてなにより天皇の為に、君側の奸薩長を排除するため、戊辰戦争を戦いました。なによりも天皇のために戦ったのです。ただ戦争回避の道もなかったわけではない、もしこの時容保公の側に、冷静に和平を解く側近がいたなら、あるいは展開は違っていたものになっていたかも知れない。しかし山本覚馬は薩摩藩に幽閉されており、秋月悌次郎は主戦派でした。側近中の側近、神保修理は徳川慶喜の“敵前逃亡”を促したという汚名を着せられ、切腹して果ててしまった。容保公の周りには、積極的に和平を唱える者がいなかった。
いるべき時に、いるべき人がいない。幕末会津藩の悲劇は、こんな不幸な偶然の積み重ねが続いた故であるとも言え、またなんとも、やるせない話です。
神保修理のことも、容保公は慶喜に従って、一緒に“敵前逃亡”してしまったという負い目があって、助命を強く言い出せなかった。容保公にはこうした「弱さ」があった。いや、弱いというのは酷かな。でも藩主にしては優しすぎる方ではあった。その優しさと正直さという、人間としては間違いない「徳」故に、悲劇が起こるやるせなさ。
そういう時代だった。と言ってしまえばそれまでですが。
会津藩は、容保公は天皇のために戦った。しかし情勢はもはや薩長こそ官軍。このままでは賊軍の汚名を着せられたまま、会津藩は滅びてしまう。それは懸命ではない。
米沢藩の使者はこう諭して、会津藩に降伏を促します。これ以上戦うことは、むしろ若き天皇(明治天皇)に反逆することに繋がる。それは会津藩の本意とするところではない。
こうして容保公は降伏を決意します。会津藩は、容保公は天皇のために戦い。
天皇のために降伏した。
どこまでも、天皇に忠節を尽くそうとした。
尊皇を貫いたのです。
悲しいくらい、真っ直ぐに。
維新後、容保公は日光東照宮の宮司となりました。容保公の側には、かつて容保公と悉く意見が対立し、ついには城を追放された元筆頭家老・西郷頼母が付き従っていました。この西郷頼母のことも、いずれ書きたいと思います。
容保公の頭には、常に会津戦争のことがあったようです。夜中にうなされて、二度三度と飛び起きることもあったとか。はからずも三千人以上の犠牲者を出してしまったことに、強い責任を感じていたのでしょう。そんな容保公の唯一の心の支え。
それは、孝明天皇より賜った御宸翰と、2首の御製。
自分は孝明天皇の篤い信頼を、有難くも畏れ多くも頂戴させていただいていたのだ。自分は尊皇を尽くしたのだ。
誰が何と言おうと、
自分は奸賊などではない。
それだけを支えに、容保公は生きた。
「往時は茫々として何も覚えてはおらぬ」
維新のことも、御宸翰のことも、何一つ語る事なく、明治26年(1893)容保公はその生涯を閉じました。
享年59歳。
容保公の逝去より35年後、昭和3年(1928)
容保公の孫娘、松平勢津子が、秩父宮妃殿下として皇室に入りました。これにより、晴れて会津藩は、賊軍の汚名を雪ぐことが出来た、と解釈されました。
「多年の雲霧、ここに晴れたり」
当時の新聞の見出しが、会津の人々の喜びを今に伝えています。
容保公は名君ではなかったかもしれない。しかし、この無骨なまでに、悲しいまでに真っ直ぐに、真摯に、誠実に生きようとする姿に、
日本の武士道の美しさを、いや、かつての日本人が持っていたであろう美しさを見るのは、
私だけではないはず。
私は容保公を尊敬します。
誰が何と言おうと。
参考文献
『会津武士道』
中村彰彦著
PHP文庫
『会津のこころ』
中村彰彦著
PHP文庫
『山川家の兄弟 浩と健次郎』
中村彰彦著
人物文庫
『会津維新銘々伝
歴史の敗者が立ち上がる時』
星亮一著
河出書房新社
名君という評価から、酷いのになると「バカ殿」なんてものまで、ホントに様々だ。
まあ、「バカ殿」は論外にしても、「名君」と言い切ってしまうのも、私はちょっと違うような気がする。まあ、いずれであるにせよ、
私は人間として、この方を尊敬します。
【志には虚邪無く、行いは必ず正直にす。游居するには常あり、必ず有徳に就く】(原漢文)
容保公が起居した京都黒谷の金戒光明寺に遺した墨書です。意味としては「志には虚(いつわり)や邪(よこしま)なこころがなく、行いは必ず正しく真っ直ぐにして、外出した時も家にいる時もその言行が一定のきまりに従っており、必ず徳の高い人(孝明天皇)に就き従う」(星亮一氏訳)というものです。
天皇のため身命を賭して忠節を尽くす。容保公のこころざしであり、本当にこの通りに生きた。
会津藩の藩是は徳川幕府に忠節を尽くすこと。しかし会津藩主は代々神道を学んでおり、当然天皇をこの国の頂点と捉えます。幕府に忠節を尽くすことはイコールで天皇に忠節を尽くすことになる。容保公はこれを真っ直ぐに信じた。真っ直ぐに貫こうとした。その真摯な姿勢が孝明天皇の心を打ち、御宸翰(天皇直筆の書状)を賜るという栄に浴する。容保公は身が打ち震えるほどの感激を味わったことでしょう。
この正直さが、容保公を苦しめることになる。なんともやるせない話ではありますが、容保公がもうすこし融通の利く、ある程度処世術をわかっている人物であったなら、幕末の会津藩の悲劇は、無かったとは言わないまでも、もう少し様相は違ったものになっていたかも知れない。そういう意味で、名君とまでは言い切れないものが、私の中にはあるのです。
しかし、こういう人物だったからこそ、会津武士道は、会津の“こころ”は、後世にまで語り伝えられたのだ、とも言えます。この藩主だったからこそ、会津藩士たちは武士らしく生き、武士らしく死ねたのだ。彼ら藩士達は満足だったと思います。
会津藩は、容保公は、賊軍の汚名を晴らすため、そしてなにより天皇の為に、君側の奸薩長を排除するため、戊辰戦争を戦いました。なによりも天皇のために戦ったのです。ただ戦争回避の道もなかったわけではない、もしこの時容保公の側に、冷静に和平を解く側近がいたなら、あるいは展開は違っていたものになっていたかも知れない。しかし山本覚馬は薩摩藩に幽閉されており、秋月悌次郎は主戦派でした。側近中の側近、神保修理は徳川慶喜の“敵前逃亡”を促したという汚名を着せられ、切腹して果ててしまった。容保公の周りには、積極的に和平を唱える者がいなかった。
いるべき時に、いるべき人がいない。幕末会津藩の悲劇は、こんな不幸な偶然の積み重ねが続いた故であるとも言え、またなんとも、やるせない話です。
神保修理のことも、容保公は慶喜に従って、一緒に“敵前逃亡”してしまったという負い目があって、助命を強く言い出せなかった。容保公にはこうした「弱さ」があった。いや、弱いというのは酷かな。でも藩主にしては優しすぎる方ではあった。その優しさと正直さという、人間としては間違いない「徳」故に、悲劇が起こるやるせなさ。
そういう時代だった。と言ってしまえばそれまでですが。
会津藩は、容保公は天皇のために戦った。しかし情勢はもはや薩長こそ官軍。このままでは賊軍の汚名を着せられたまま、会津藩は滅びてしまう。それは懸命ではない。
米沢藩の使者はこう諭して、会津藩に降伏を促します。これ以上戦うことは、むしろ若き天皇(明治天皇)に反逆することに繋がる。それは会津藩の本意とするところではない。
こうして容保公は降伏を決意します。会津藩は、容保公は天皇のために戦い。
天皇のために降伏した。
どこまでも、天皇に忠節を尽くそうとした。
尊皇を貫いたのです。
悲しいくらい、真っ直ぐに。
維新後、容保公は日光東照宮の宮司となりました。容保公の側には、かつて容保公と悉く意見が対立し、ついには城を追放された元筆頭家老・西郷頼母が付き従っていました。この西郷頼母のことも、いずれ書きたいと思います。
容保公の頭には、常に会津戦争のことがあったようです。夜中にうなされて、二度三度と飛び起きることもあったとか。はからずも三千人以上の犠牲者を出してしまったことに、強い責任を感じていたのでしょう。そんな容保公の唯一の心の支え。
それは、孝明天皇より賜った御宸翰と、2首の御製。
自分は孝明天皇の篤い信頼を、有難くも畏れ多くも頂戴させていただいていたのだ。自分は尊皇を尽くしたのだ。
誰が何と言おうと、
自分は奸賊などではない。
それだけを支えに、容保公は生きた。
「往時は茫々として何も覚えてはおらぬ」
維新のことも、御宸翰のことも、何一つ語る事なく、明治26年(1893)容保公はその生涯を閉じました。
享年59歳。
容保公の逝去より35年後、昭和3年(1928)
容保公の孫娘、松平勢津子が、秩父宮妃殿下として皇室に入りました。これにより、晴れて会津藩は、賊軍の汚名を雪ぐことが出来た、と解釈されました。
「多年の雲霧、ここに晴れたり」
当時の新聞の見出しが、会津の人々の喜びを今に伝えています。
容保公は名君ではなかったかもしれない。しかし、この無骨なまでに、悲しいまでに真っ直ぐに、真摯に、誠実に生きようとする姿に、
日本の武士道の美しさを、いや、かつての日本人が持っていたであろう美しさを見るのは、
私だけではないはず。
私は容保公を尊敬します。
誰が何と言おうと。
参考文献
『会津武士道』
中村彰彦著
PHP文庫
『会津のこころ』
中村彰彦著
PHP文庫
『山川家の兄弟 浩と健次郎』
中村彰彦著
人物文庫
『会津維新銘々伝
歴史の敗者が立ち上がる時』
星亮一著
河出書房新社












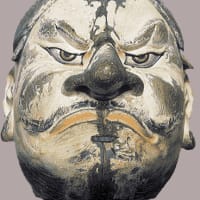







今や私の中で容保公は泥の中に咲いた蓮の花のように眩しい美しい存在にしか見えません。
だって、私だったら逃げちゃうよ。こんな時代背景で、謀略や無理難題を押しつけられたり、勝手なこと言われたりしてね。
でも黙って受けて立っている。
それが本当にスゴい。
慶喜君も身内に「あれはあれで仕方なかったんだ」と洩らしたとか記録残っているけど(勿論私だってその立場だったらそうやって言い訳したいしそれが人間だからね)そんな言い訳も自分の士道、心に反すること、と一切しない容保公。
本当に尊敬します。
敵前逃亡の件にしたって、あれは容保公の側近神保修理が、「一旦引いた方がいい」みたいなことを言ったからそうしたんだ。俺のせーじゃねーよ!と言い訳したらしいんです。そのあおりを食らって、神保修理は切腹するはめになってしまった。ヒドイ話ですよ。
京都守護職の座を、容保公に押し付けた松平春嶽なんか、自分は政治総裁職を1年で辞めちゃって、戊辰戦争が始まると、とっとと新政府軍側についちゃって、会津のことは知らん顔です。
そんな時代にあって、よくぞ自身の生き方を全うしたものです。スゴイ方です。
終生なにも語る事はなかったようです。特に孝明天皇とのことは、語る事そのものが不敬になる、と思っていたのでしょうね。
なにもかも全部飲み込んで…晩年はどんな想いで過ごしていたのだろう。それを考えると、なんだか切なくなります。
慶喜公は、名君だったという評価も以前どこかで聞きましたが、賛否両論なんですかね。この記事を読む限りでは、ヒドイ人、ですね(汗)
行い正しく、正直なだけでは、世の中渡っていくのは厳しいのか…?でも確かに、バカ正直も相手を見極めないと、危険な場合がありますね。
慶喜という方は、言うことや態度が、その場その場でころころ変わる。例の敵前逃亡の数日前には、身命を賭して戦うと将兵達の前で宣言したにも関わらず、その下の根も乾かぬうちに自分だけ逃げてしまう。将兵達を置き去りにしたままですよ。これが武門の棟梁のすることでしょうか?
私としては、口が裂けても名君だなどとは言えません。ただこの方が将軍だった御蔭で、一地方の戦争で終わったことはたしかですが、それは結果です。この方の英慮などではあり得ません。
私の私見ですけどね。
現在、何にも変わらぬ自分が大好きです。迷う必要ないし、生きているうちが、勝負かとおもいます。自分のなかでの自分とです。虎岩爺がくれた言葉です。会津の魂は、消して滅びません。ふつうに、考えれば、知らなくて当たり前、必要もないとおもいます。それぞれの人生ですから、感謝しかないとおもいます。お疲れ様です。ありがとう御座います。
孝太郎君上手だね~。
よく私も名君話はえっ?と思うのですが平時だったら名君ではいられた、かもしれないとかよく思う。何故か斉昭親父も名君として水戸に銅像あるが…。
女性としては男性を見る時に楽しい時はいいけど、何か悪いことが起こった時は男性が逃げるか受けきる人かどっちだ~とか気になります。
馬鹿坊ちゃんを見て嫌な気持ちが湧く私は同じく馬鹿嬢ちゃんな私も私の中にいるな~とかも。
池内博之は茨城県出身。好きな役者じゃなかったけど、良い役者になってくれ~と昨日思いました。
嗚呼、近藤勇が将軍だったらいいのに(笑)
取り留めない妄言失礼。
でも最後まで無念は残った。私はその無念に、思いを寄せたい。
梶原平馬は、玉山鉄二演じる山川大蔵(後の山川浩)同様、会津戦争では重要な役割を果たすのですが、山川浩が後に明治政府の下、陸軍少将や東京高等師範学校の校長に就任したのに対し、梶原平馬は北海道で寂しい晩年を過ごしたようです。人それぞれとはいえ、なにやら憐れです。