幕府の要人が白昼堂々、テロによって暗殺された「桜田門外の変」。
幕府の権威がいかに墜ちているかという事を示す、象徴のような事件です。
幕府は体勢を立て直すため、朝廷との結びつきを強めようと画策、孝明天皇の御妹君・和宮内親王を、将軍・徳川家茂の御台所として降嫁させようとします。
孝明天皇としても、幕府への大政委任を揺るがすおつもりはいささかもなく、これもお国のためと、すでに有栖川宮熾仁親王とのご婚約が内定しており、関東などという野蛮なる土地に下るのは嫌だと泣く和宮を説得し、和宮降嫁が決定します。
和宮様と家茂は後々大変仲睦まじい夫婦となったといいます。
文久2年(1862)、薩摩藩の「国父」島津久光が兵を率いて上洛します。久光は兵を京都に駐屯させ、勅使の大原重徳らとともに江戸に入り、未だ謹慎の解けぬ松平慶永を大老に、一橋慶喜を将軍後見職に就任させるよう要求してきました。
久光は公武合体論者であり、公武合体をよりよく進めるためと、薩摩藩の中央における発言力とを強めることが狙いだったようです。
幕府としては、薩摩の背後には朝廷があり、軍隊も控えている。事を荒立てぬためにも、ここは受け入れる方がよいと判断したようです。
そうして、松平慶永は政治総裁職、一橋慶喜は将軍後見職に就くことになるのです。
松平慶永の政治総裁職とは、慶永のために新設された役職で、これは今まで親藩大名が大老になった前例がなかったためです。
この久光一行が帰国の途上、生麦村にて、行列の前を横切ったイギリス人を斬り捨ててしまうという事件が起こります。
世に言う「生麦事件」です。
さて、この文久2年頃は、京都の治安が最悪な状態に陥っていました。
声高に攘夷を叫び、そのためにはテロも辞さぬという主に長州者を中心とした尊攘激派テロリストが、天子様のお膝元である京都に続々と集結し、日夜残虐なる乱暴狼藉を働いており、従来の京都所司代や京都町奉行所では手に負えない状態でした。
そこで、京都の治安を回復させるために、強い権限を持った「京都守護職」が新設されるに至ったわけです。
このお役に抜擢するには誰が相応しいか?
そこで候補に挙がったのが、松平容保公及び会津藩でした。
松平慶永が容保公説得に当たります。そのころ容保公は体調が思わしくなく、元々病弱ななところがあった容保公としては、己の体調への不安もあり、また会津から京都は非常に遠く、藩の財政は度重なる飢饉等で逼迫しており、到底お役を務めることなどままならぬと、これを固辞します。
しかし慶永は諦めません。毎日のように容保公の元を訪れては説得にあたり、ついには会津藩の祖法というべき家訓十五ヶ条を例に出され、「土津公(初代藩主・保科正之)ならお受けしたであろう」と言われ、これに容保公は返す言葉を無くしてしまう。
ついに容保公は御役を受けざるを得なくなってしまいます。容保公の生真面目な性格を利用した、慶永の勝利といっていいでしょう。
この事態に国元より、家老の西郷頼母と田中土佐が駆け付け、容保公に京都守護職就任を断るよう進言します。
『京都守護職始末』によれば、西郷や田中らは容保公に謁し「このころの情勢、幕府が非であり、いまこの至難の局にあたるのは、まるで薪を背負って火を救おうとするようなもの。おそらく労多くして功少なし」と、言辞凱切、至誠面にあふれて戒めます。
これに容保公は「それはじつに余の初心であったが台命しきりに下り臣子の情誼としてはもはや辞する言葉がない。聞き及べば余が再三固辞したのを一身の安全を計るものとするものがあったとやら。そもそも我家には宗家(徳川宗家)と盛衰存亡を共にすべしとする家訓がある。余不肖といえども一日も報恩を忘れたことはない。ただ不才のため宗家に累を及ぼすことを怖れただけである。他の批判で進退を決めるようなことはないが、いやしくも安さをむさぼるとあっては決心するよりほかあるまい。しかし責任を拝するとあれば我ら君臣の心が一致しなければならないだろう。卿ら、よろしく審議をつくして余の進退を考えて欲しい」
この家臣たちの気持ちを慮っての容保公の発言に、家臣らは感激し
「この上は義の重きにつくばかり、君臣共に京師の地を死に場所としよう」と君臣肩を組んで涙したと云います。
『京都守護職始末』は元会津藩士の筆による記録なので、多少の誇張はあるかもしれませんが、ここには松平容保という人がよく表されていると思いますね。生真面目さ故に断ることができず、一方で家臣たちの気持ちをよく慮る優しさもあって、家臣たちに慕われていたそのわけがわかるというものです。
京都を死地と定める。会津藩は京都で滅びるのだ。このような覚悟を持たねば、とても京に巣食うテロリストに対応することができなかった。
逆に云えば、会津藩以外に、京都の治安維持を任せられる者達はいなかったといっていいのかもしれない。
いずれにせよ、容保公及び会津藩はこの時より、運命の時へ向かって走り出したのです。
続く。












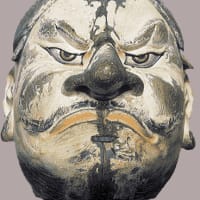







あるいみ、スサノオみたい…。
さすが丑寅、東北というか…。
利するところなしの負荷だけ背負い、破滅したあとも、100年後の原発までずっと虐げられるなんて…。
さらに東北大震災…。
なんでなの?
まるで神は、結局長州に味方しているよう…。
生麦事件でイギリス人を切ってしまった武士達は死刑を命じられたそうで。で、せめて切腹にさせてくれと言う武士達は、切腹する際に、自分の内臓をイギリス人に向かって投げつけて死んでいったらしく。それを目の当たりにしたイギリス人がビビッて、「もういい」と言ったとかいうエピソードが印象的だったので覚えているのでした。
当時の私は、さすが日本の武士、イギリス人を黙らせた偉いぞ、武士の根性はすごい、内臓を投げつける精神力すげー みたく思って、小学生らしく、武士はヒーローでした。
欧米では日本よりずっと自殺が忌み嫌われるものであって。”日本人の自殺率が高いのは、武士道の精神のせいだ、武士道は気持ちわるい”的な思いがあるようで。日本兵の特攻隊にも、武士道の切腹と似た精神があったかもしれません。日本兵も同じように気味悪がられていますもんね。
時代、だなあと思います。死が遠いものであった小学生の頃は、切腹してこそ武士だ、負け戦でも仁を通せ的なことに憧れていたし、欧米人に武士道がわかってたまるか的な思いもあったりしました。
明治維新を敗者の視点で書いたといわれている本の作者は、母親から「自害も覚悟していなさい」と言われて育ったとか。これも、真面目で純粋な人であったが故の武士道精神だったのだろうな、と思います。
平和な時代の「非武装であれ。軍事力を持つな」も真面目で純粋な人が思う事。内容的に全てが間違っているわけではないのですよね。
真面目で純粋な思いだけでは、力尽きて果ててしまってからしか、「立派な思いだけでは人間は自身を満足させることができない」事に気づく事ができないのかも、と思います。
力尽きて果ててしまえば、どんなに立派な思いや目的があっての行動であったとしても、不利益を被ったことを人は恨んでしまうから。
ペルーでの日本大使公邸人質事件の際、日本人を助けるために突入したペルー人警察は全員、遺書を書いた上での上からの指令だったそうです。日本人と揉めるわけにいかない、遺書を書いた上で助けに行ってくれと。結果的にはテロリスト以外死亡者が出なかったからよかった。
だから、もう忘れ去られていて、ネットでもよっぽど検索しないと出てこない事件。死を覚悟してでも、成し遂げれば、目的を成し遂げることが出来れば、恨みにもならない出来事なのかもと思います。だれかが死んでいたら、「金持ち日本人を救出するためにペルー人は犠牲になった」くらいのことは思われていたかもしれないし。
逃げ場がないくらい真面目に純粋に生きてしまうことが悪いわけじゃないけど。その時代だから仕方ないことがあると思うけど、人の限界って案外もろいと私は思う。小学生の頃に憧れたほど、実際に武士道は綺麗なものじゃなくて、きつくて無理があるような気がする。限界を超えるような。
だったら、ちょっとくらい緩いまま、臨機応変に生きた方が、人は時代を恨まなくて済むんじゃないかなーと。
今の時代で言えば、軍備を持つということは、そういうことなのだろう、と。
自分の家族や自分自身の死を目の前にしてしまえば、「軍備など持つべきじゃない」なんていう理想論は死に絶えた後の恨み言に変化するだけだろ、と思って。選挙を目の前にして綺麗事言えるほど平和な時代は今はもうない、と思うのでした。
東北とは、そういう土地だ、としか言いようがなく、それは人智で測れるようなことではない。とはいえ、
やはり、割り切れない思いは当然残る。私は人間ですからね。
それにしても……ホント、長いわ!(笑)