京都入りするに先立ち、容保公は田中土佐らを先発させ、情勢の視察に当たらせます。
市井の人々にまで攘夷を望む声は大きい。神国日本に夷狄を入れてはならぬという思想は庶民にも浸透していたようです。
孝明天皇もまた攘夷論者であり、勅許なしにアメリカと条約を結んだ幕府に対し、深い不信感を抱いている。しかし一方で、公家と武家とが手を結びあって国政に取り組むべき(公武一和、公武合体)だという姿勢は、いささかも変えてはおられない。
こうした点を鑑み、容保公は幕府に建言書を提出します。
その主な内容は以下のとおり。
1.夷人の無礼や驕慢に毅然とした態度を示し、江戸府内の居住を制限する。
2.すでに開港した三港(長崎、横浜、箱館)はそのままとし、その他の条約で定められた兵庫、新潟の開港と江戸、大阪の開市は延期するよう外国と交渉する。
3.朝廷より江戸へ下る勅使の待遇を改め、礼節をもって迎えること。
(wikipediaより引用)
現実問題として、いまさら攘夷など不可能なことはわかりきっていること。しかし天子様や市井の声を無下に葬り去るわけにもいかない。ここは時間をおいて段階的に理解を求めていく他はない。
「義」と「理」のバランスを良く弁えた、見事な卓見だと思いますね。いかにすれば朝廷と幕府の仲を取り持ちつつ、現実に対処していけるか。
幕府のためは朝廷のためであり、それは市井の人々のためにも繋がる。容保公は常にこの点を中心に据えて、筋の通った考えを展開させていく。
この容保公の建白を幕府は採用し、開港を5年延期させることに成功します。また各国公使館を品川の御殿山に集中して移転させ、江戸居住を制限させました。
勅使三条実美はこれに好感をもって帰京し、孝明天皇はこの建議書のことを聞くや「中正(中道にして公平)なる卓見である」といたくお喜びになられたそうな。
この時からすでに、容保公は孝明天皇の大の「お気に入り」となったようです。
文久2年、会津藩兵約一千を引き連れ、容保公は京都入りを果たします。沿道にはこの評判の高い、美形の大名を一目見たいと、京雀たちが列をなしたとか。
容保公は宿舎に入る前に、一旦本禅寺を休息所にして旅装を解き、礼服に着替えると関白近衛邸にて天機(天皇の御機嫌)を伺い着任の挨拶をします。そうして後、宿舎に充てられた金戒光明寺にはいりました。
この一連の行動を京雀たちは「折り目正しい」と好感をもって迎えたようです。
翌文久3年(1863)、容保公は御所に参内し、小御所にて孝明天皇に初めて拝謁します。孝明帝は容保公に天拝と緋の御衣を賜り、「陣羽織か直垂に作り直すが良い」と詔なされました。これは前年の、勅使の待遇改善に尽力した功に対する褒章でした。
武士が天皇より御衣を賜るなど前例がなく、前代未聞の大変な栄誉でした。容保公はこれにいたく感激を覚え、さっそく陣羽織に改めると写真を撮り、会津にいる姉の照姫のもとへ書状とともに送りました。
その時の写真がコチラ。↓

イケメンですねえ。
なにやら子供のようにはしゃぐ容保公の姿が見えるようです(笑)
容保公は公卿たちの薄禄と窮乏の改善にも手を掛けています。皇室の御料は戦国時代以来定額のままで、諸物価の高騰についていけず、その窮乏状態は目に余るものがありました。江戸幕府海部以来、そこに初めて手を加えたのが容保公だったのです。
公卿のなかには窮乏の余り内職で生計を立てる他ない者達も多く、このような不平不満が尊攘激派テロリストと結びつく原因ともなっているわけで、容保公はこうした点から改善していかなければならないと考えたようです。
容保公は幕府に対し、皇室御料の改善と定額制見直しを建議します。また天皇の食卓に関しても、出される魚はとても食べられるような品質のものではなく、天皇は箸をつけるマネをするだけというしきたりでした。これを聞くや容保公は大阪湾より新鮮な魚を直送させ、天皇の御膳に乗せます。
孝明天皇は「これは肥後の魚か、肥後の魚か」と繰り返しいたく喜ばれ、ほぼ食されたというのに「次の食事の時に続きを食すのでそのまま出すように」と名残惜し気であられたといいます。本当に嬉しかったのでしょうね。
口先だけで「尊王」を叫ぶものは多かったけれども、この容保公のように、皇室や公卿らの日常生活の刷新改善にまで取り組んだ方は、おそらく一人もいなかった。
もちろんそれは、京都守護職という強い立場にあったからこそ、ということは言えるでしょう。それにしても、天皇の日頃の生活にまで心を配った者が、容保公以前にはいなかったというのは、驚きでもあります。
「私心がない」という言葉は、みだりに使うべきではないと私は考えます。実際私心の無い人など、皆無に近いといっていいでしょう。
しかし少なくとも、容保公の皇室を慮る気持ちには、本物の思いやりがあった。そこに「私心」はなかった。
と、敢えて断言させていただきます。
そんな容保公には、「理想主義者」としての一面もありました。
それはまた、次回。
続く。
※孝明天皇のおっしゃった「肥後」とは肥後守、つまり松平肥後守容保ということです。「この魚は容保が取り寄せたのか?」と繰り返し訊ねたということです。












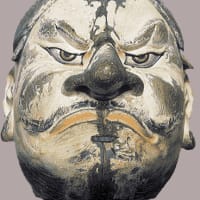







※孝明天皇のおっしゃった「肥後」とは肥後守、つまり松平肥後守容保ということです。「この魚は容保が取り寄せたのか?」と繰り返し訊ねているということです。