時の大老・井伊直弼が調印した日米修好通商条約は、天皇の勅許を得ないままの調印でした。外国との条約調印は、天皇の勅許を得ることが基本ではあったものの、それは絶対的なものではなく、この調印が必ずしも強引だったわけではないようです。
しかし世の攘夷派が激高したのもまた事実。徳川御三家の一翼である水戸の前藩主徳川斉昭などが激しく幕府を批判します。
安政5年(1858)、攘夷論者であった時の孝明天皇が、この水戸藩に対し、幕府を飛び越えて直接勅書を送るという挙にでられました。
これを、「戊午の密勅」といいます。
その内容は、
○勅許なく日米修好通商条約に調印したことへの呵責と、詳細な説明の要求。
○御三家および諸藩は幕府に協力して公武一和の実をなし、幕府は攘夷推進の幕政改革を推進せよとの命令。
○上記二つの内容を諸藩に廻達せよという副書。
(wikipediaより)
幕府の頭を飛び越えてこのようなことがなされたのでは、幕府の権威の失墜に繋がる。幕府は水戸藩に対しこの勅書を幕府に返却するよう求めます。
朝廷に返却するよう求めるのではなく、幕府に返却するよう求めたのは、直接朝廷に返却したのでは失礼にあたるからで、幕府もこの対応には相当苦慮したようです。
水戸藩内でも、これを返却すべきかしないかで反論が割れ、血を見る事態にまで発展します。いずれにしろ江戸幕藩体制確立以来250年、天皇が政治に口を出すなど絶えてなかったことで、前代未聞でした。
井伊直弼は幕府の威信を回復するため、攘夷派や反体制的と見做された者達を次々と捕縛させ、その数百余名に上ったとか。徳川斉昭も幕府に反抗したということで、水戸での永蟄居を命じられます。
世に言う「安政の大獄」です。
万延元年(1860)、水戸脱藩浪士に一部薩摩藩士が加わり、江戸城桜田門外にて大老・井伊直弼が暗殺されたテロ事件「桜田門外の変」が発生します。幕府老中・久世広周、安藤信正はこれ以上の幕府の権威失墜を防ぐため、水戸藩を厳しく処断しようとします。
戊午の密勅の断固たる返却と、水戸藩取り潰し。あるいは同じ御三家である尾張藩と紀州藩に兵を出させることも検討されたようです。
これに反対の意見を述べたのが容保公でした。
容保公は、畏れ多くも天子様の覚え目出度い水戸藩を簡単に処分するのは、天子様の御勘気を被ることに成り兼ねず、さらに水戸藩は御三家、つまり将軍家の御身内であるということ。それと事件を起こしたのは脱藩した浪士であって、水戸藩が直接関与したわけではないということ。
これをもって、水戸藩には寛大な処置をとるべきであるという意見を上申したのです。
まさしく「義」と「理」のバランスがよく取れた意見であり、それでも老中らは厳正なる処罰を加えようとしますが、将軍・徳川家茂が容保の意見を通し、採用します。
将軍家茂は、容保公に対し感謝の意を示したとか。
『京都守護職始末』(元会津藩士で陸軍少将の山川浩による著作)によれば、容保公はさらに戊午の密勅を返還させるため、家臣の秋月悌次郎らを水戸に派遣し、説得に務め、密勅の返却を成功させたとあるようですが、これには異論も多く、密勅は返却されることなくいやむやにされ、水戸のどこかに保管されたままのようです。
いずれにしろこの件によって、容保公の幕府内における発言力が強くなっていきます。こうして将軍から信頼された容保公は、文久2年(1862)将軍家茂より、「折々登城し幕政の相談にあずかるように」と命ぜられ、幕政へ参画することになるのです。
将軍はじめ幕閣より強い信頼を得るようになったわけですが、それは容保公の生真面目さと謹厳実直さ故の事、しかも会津藩の武威は非常に高い。幕府としてはこのような人物を放っておく手はなかったでしょう。
しかしこういう方は、時に「利用」もされやすい。
同じく文久2年、容保公に大いなる運命の時が訪れます。
「京都守護職」への就任要請です。
続く。












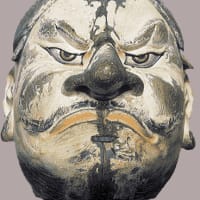







容保公を安易にバカ殿呼ばわりする記述もたまに見ますが、他にバカ殿は沢山いただろーって思います。
斉昭公は、現代で言えば短命の会社を築いたワンマン社長のようですし、まぁ、でも永蟄居の末無くなったから、少し可哀想ですが、でもこっちの方が少しワガママで自分の思惑で生きていたように見えます。
長い天下泰平に少しずつ溜まった膿が放出している中で、容保公は己の真面目さに忠実で真剣に生きて来たこと、また詳しく読めることを嬉しく思います。