会津藩は徳川幕府の「藩屛」であることを国是としておりました。
いざとなれば徳川幕府、徳川宗家を守るために先頭に立って戦う。そこに存在意義を見出しておりました。
会津藩家老(後に藩大老にまで昇進)・田中玄宰(はるなか)の軍制改革は、会津藩がいつでも速やかに出陣できるような体制を整え、より実践的な軍制を整えて非常時に対処できるような体制を作り上げるためでした。
新たな軍制を整える過程で、兵の数を増やすために新人(?)藩士を採用していく。当時の武士は基本的に役人です。つまり公務員ですから、その俸給は税金から支払われることになります。人が増えれば人件費も増える。それを補うためにどうするか?
当時は自然災害や飢饉等で税収は減少しており、藩の総人口も減少していました。またこのような世相が続けば、犯罪が増え、人々は子供を作ることを控えるようになり、場合によっては生まれたばかりの子供を「間引く」というような、悲惨な事態も頻発するようになる。
このような時期に安易に年貢の額を増やせば、庶民の心は離れ、国内は混乱しかねない。会津藩は年貢額を引き上げるようなことをせず、藩士への俸給の払い方に工夫を加えます。要するに公務員給与を減らしたわけです。
藩主自らも率先して生活費を切り詰め、耐乏生活に臨み、藩士たちに範を示す。そうして溜めた資金の一部を、庶民が安心して子供を産めるよう、「育児手当」として庶民に支給し、間引きなどの悪習を無くそうと努めました。
人口が減少すればその分田畑を耕作する者の数も減り、収穫高が減り、税収も減る理屈。さらに犯罪が増えれば捕縛される者も増え、その分耕作者が減り、益々税収は減っていく。玄宰はこれに対処するため、法律を改革し、それまで懲役刑や追放刑であったものを罰金刑に改め、ただ単に懲罰を加えるだけではなく、「説諭」をすることで社会復帰に手を貸し、最終的には死刑を廃止するまでに至ります。
もちろん、懲役刑や追放刑がなくなったわけではありませんが、刑罰の内容をかなり緩やかにしたことは確かで、それでも現在の視点から見ればかなり残酷と云っていい刑罰もあるものの、死刑廃止に至ったというのは、良き煮付け悪しきにつけ画期的ではありました。
そうしてできるだけ耕作者を土地に戻し、税収の減少に歯止めをかけたわけです。
その他、玄宰は地場産業の育成にも尽力し、現金収入の増益に務めました。「会津塗」や「会津清酒」、また「本郷焼」などの焼き物など、現代でも流通している会津の名産品はすべて、この玄宰の時代に整えられたものです。
また、会津の名物料理である鯉料理もまた、玄宰が鯉の養殖を奨励し、藩士や庶民に滋養をつけさせるために始めたことが発端となっています。
先の「什の掟」といい、会津の伝統といわれるものはほとんど皆、この玄宰の時代より始まったといっていいわけです。
しかしこの玄宰の思想の源流となっているものは、初代藩主・保科正之の思想であるわけで、会津藩というのは初代の思想を頑なに守り続けた藩であったということなのですねえ。
庶民に仁政を敷き、藩士には質素倹約を務めさせ、国を富ませることが、最終的には「国防」に繋がる。安易な苛斂誅求を行わず、寧ろ下々に手厚くあたるところから始めたところに、会津藩の「賢さ」があったといって良い。
実際これらの政策によって、会津藩の国庫は徐々に富んでいったようです。
文化3年(1806)、ロシアの軍勢が樺太(サハリン)の久春古丹にあった松前藩の陣屋を襲撃するという事件が起こります。これは前年、ロシアの使者が幕府に対し交易を求めたものを、幕府がにべもなく追い払ったことへの報復でした。
会津藩は直ちに軍の派遣を要請しますが、最初幕府はこれを渋っていました。しかしその後改めて会津藩や仙台藩などに幕府より出陣要請が下り、会津藩はおよそ千六百余りの軍勢を樺太に派遣しました。
軍が樺太に到着したとき、すでにロシア軍は去っており、幸い実戦には至りませんでしたが、こうして国防の最前線に立とうとする姿勢、これが会津藩の基本的なあり方でありました。
ですから、ある意味国家転覆を企む薩長と敵対するのは、理の当然であった、ということでしょう。
武家として武家らしくあろうとし、一途に美しくあろうとした会津藩はその武家社会の終焉とともに、滅びざるを得なかった……。時代の流れとは云え、
なんとも切ないことではあります。












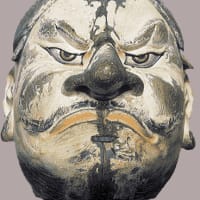







武士が本当に滅びたのは西南戦争の時という考え方もありますよね。
私が思うのは、武士の地位を自衛隊にすればよかったのにな~なんて都合の良い話です。徴兵制よりかいいんじゃないかしらん、みたいな。適材適所というか。
文化とか文明というのは、表面のかたちは変わっても、その中心には変わらない芯というものがあって、武士道もそうした芯から立ち現れてきたものだと思う。文化文明を存続させるためには、この芯は絶対になくしちゃいけない。
今がその正念場、なのかも。