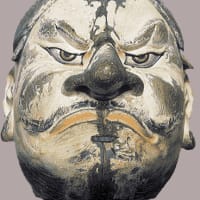というわけで、本日休載を撤回致します。
会津藩5代藩主・松平容頜(かたのぶ)の治世、会津藩家老に、田中玄宰(はるなか)という人物がおりました。
時は天明から寛政のころ、1700年代後半くらいと捉えておけばいいでしょう。この時代は飢饉が頻発し、特に東北諸藩の惨状はそれは酷いモノでした。
会津藩は社倉制度があって、飢饉に備えての備蓄米等が比較的充実しておりましたので、他藩に比べればまだましな方だったようですが、それでもやはり餓死者は出てしまう。
それに他藩から食い詰めた難民が大挙押し寄せてくる可能性もあって、それに対処し、藩内の治安を維持し、また藩士たちの士気を高めるためにも軍制の改革が必要だと、玄宰は考えたわけです。
それまで会津藩が採用していた軍学は、到底実戦に役立つようなものではなく、藩士たちの士気も低迷していました。これではいざというときにまったく役に立たず、徳川宗家をお守りするという会津藩の藩是が果たせない。
そこで、軍学をより実践的な長沼流軍学に改め、藩士たちの教練に務めました。
それまでの軍制は、戦国時代の遺風が残っているというのか、非常にのんびりとしたもので、例えば1万の軍勢があったとしても、大体その半分の5千は戦闘に参加しないで休んでいる、ただ戦局を眺めている。つまり実質5千の軍勢しかいないのと同じという風な、なんとも非合理的なものだったようです。
これを改め、銃隊、弓隊、槍隊。そして徒歩兵と騎馬兵とが有機的に連携し合って、全軍が常に動き、休んでいる者が一人もいないという風なかたちに換えていきました。
そうして、三の丸前の広場を練兵場として、全藩士に連日、武術の鍛錬を行わせました。さらには3年に一度、藩士がほぼ全員参加する総合操練を行うことで、いざとというとき藩士たちがすぐに動けるような体制をかたち作っていったのです。
この総合操練のことを「練り駆け」といい、指揮官の采配のもと、全軍が一丸となって一糸乱れぬ行動をとる。それは壮観なものだったようです。
文久3年、京都守護職の座にあった松平容保公は、この「練り駆け」を孝明天皇の天覧の下、2度ほど行い、天皇はいたくお喜びになられたそうです。この者達に任せておけば大丈夫と、孝明天皇もさぞやご安心なされたことでありましょう。
天皇の容保公に対する信頼は益々篤いものとなったことでしょう。
操練ではこの「練り駆け」の後に「追鳥狩」というのが行われます。これは数百羽の鳥を一斉に解放し、藩士たちはその鳥を打ち落とすための専用の棒を持って鳥を追うわけです。そうして一番最初に鳥を打ち落とした者は、その鳥を藩主に直接献上する栄に浴することが出来るとあって、藩士たちは勇躍、追鳥狩に参加しました。
あえなく鳥を落とせなかった者達は、次の操練には必ず落とすと、益々日々の鍛錬に励むようになるわけです。
こうして藩士全体の士気は、非常に高いものとなっていきました。
こうした会津藩の武威の高さが、京都守護職就任の一つの契機だったのだと思われ、親藩であったこと、それと容保公の人柄とを合わせて、「会津藩以外には任せられぬ」となったのでしょう。
武威を高めるのは、武門としては当然の務め。しかし江戸250年の泰平は、それすらも特異なこととしてしまっていたようです。
続きます。