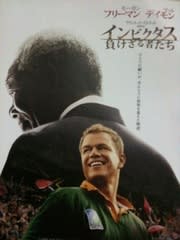
クリント・イーストウッドの新作、今回も「毎日1000円キャンペーン」中のワーナーシネマズ海老名で
見てきました。
しか~し、日本語タイトル「負けざる者たち」って、かなり苦しいタイトルやなぁ~。
調べてみたら「Invictus」とは1888年に発表されたウイリアム・アーネスト・ヘンリーの詩「不屈」で、
ラテン語のようです。
12歳で結核性関節炎、16歳で左下肢を切断、父の死の学業中断など、度重なる不幸に屈することなく
詩集を出版、新聞編集者となり、終生病と闘った方だそうです。
「Invictus」は結核入院中に書かれた詩で、病に屈っすることなく闘う壮絶な詩です。
最後の2行:
I am the master of my fate. 私がわが運命に支配者
I am the captain of my soul. 私がわが魂の指揮官 に、心の叫びが溢れています。
27年という気の遠くなるような投獄に耐え、折れそうなマンデラの心を支えたこの詩、
言葉の力ってすごいです。
因みに1995年の米オクラホマシティー連邦政府ビル爆破犯のティモシー・マクベイは
処刑される直前、このヘンリーの詩を書いたメモを刑務所長に手渡したそうです。
欧米では有名な詩なのでしょうね。
**********************
インビクタス 負けざる者たち
**********************
日本ではラグビーよりサッカーの方がメジャーなスポーツです。
ところが・・・
どうも英国では上流階級がラグビーを、労働者階級はサッカーという住み分けがあるようです。
以前英国かぶれの日本人(女性です)にサッカーの話をしたら
「あぁ、労働者階級のスポーツね。私はラグビーファンですから」っと言われてしまいました

何とタカビーなやっちゃ!英語で言うならスノビッシュですか!
南アではラグビーは白人のスポーツということで、アパルトヘイトの象徴だったようですね。
映画の中でも、マンデラの白人SPが黒人SPに
「サッカーは乱暴者がする紳士のスポーツ、ラグビーは紳士がする乱暴なスポーツ」といった
ジョーク?を言ってました。
オリンピックやサッカーワールドカップ、ワールドベースボールクラシックを見ればわかるように、
スポーツは国威を発揚し、人々の気持ちを一つにする大きな力を持っています。
銃を持たない戦争のようなものです。
卒業式で日の丸・君が代を拒否しても、オリンピックやワールドカップで国旗掲揚や国歌斉唱に
反対する人はいないどころか、旗を振り、顔に日の丸のペインティングまで。
誰もが一時的にせよ愛国者に変わります。スポーツの力もスゴイです。

<ラグビーで国を一つに>
1990年2月11日のマンデラ氏釈放から、今年はちょうど20年だったのですね。
当時、黒人側には白人に対する積年の恨みつらみがあり、白人側は黒人の仕返しが始まるのではと
戦々恐々。
マンデラ氏はスポーツの力を評価し、分裂しそうな状態の国民を一つにまとめる道具として
ラグビーワールドカップの自国開催を優勝で飾るべく、キャプテンフランソワにリーダーとしての姿勢を示し、
チームメンバーの名前を覚え一人一人に声をかける。

しかし、弱小チームから連勝し決勝戦で強豪ニュージーランドに勝利するって・・・、
実話なんだけれどもそんなことは可能なの?
どの程度のダメチームで、どれほどの特訓を積んだかは触れられていないので、何とも言えませんが、
世界で1位2位を争うレベルって「不屈」の精神論で押して成るものなんでしょうか?
「グラン・トリノ」「チェンジリング」でぐいぐい引き込まれ感動した経験から
ちょっと期待が大きすぎたかも?しれません。
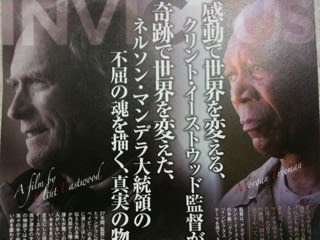
「負けざる者」はラグビーワールドカップ南ア代表を指すのではなくマンデラその人。
国のリーダーとはかくあるべきという、マンデラの信念・指導力・人望・不屈の精神に魅せられました。
ただ家族は大変だろうなぁ~。
身内ということで逮捕されたり、息子は事故(おそらく)に見せて殺されたりでは、
いくら反アパルトヘイト運動の意義や新しい国家のためにとはいえ「何故あなたじゃなきゃダメなの?」
とか「子供の身の安全も考えて」となりますよね。
闘士は孤独。 家族の話はタブーというのも無理からぬこと。
「危険を覚悟しなければ、指導者の資格は無い」
「赦しが魂を自由にする。赦しこそ恐れを取り除く最強の武器なのだ」
「変わるべき時に私自身が変われないなら、人々に変化を求められません」
こういう人が出ないと国は変わらへんなぁ~。
「人を呪わば穴二つ」
「憎しみは憎しみの連鎖を生むだけ」
ガンジーにキング牧師、マンデラ、世の中を変えるのは押さえつける力ではなく非暴力による赦しでしょうか。
新興国を示すBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の最後のSを大文字にして
南アフリカを入れようなんて動きがあるほど、20年後の現在南アの経済は好調らしい。
今年の6月はラグビーではなくサッカーのワールドカップ南アフリカ開催が控えてますが
南アは強いんでしょうか?
サムライブルー(最近はこう呼ぶんですか?)がんばれ!
もう一つヘンリーの名言をご紹介。
「人生は、私たちが人生とは何かを知る前にもう半分過ぎている。」
厳しい言葉やなぁ。
エンディング曲は一瞬「オーシャンズ」に続いてこれも平原綾香?と思っちゃいました

***** 見た 映画 *****
2月 8日 「インビクタス 負けざる者たち」@ワーナーマイカルシネマズ海老名
2月 9日 「マンデラの名もなき看守」DVD

「クララ・シューマン」DVD シューマンと妻クララ、そしてブラームスとの物語
2月11日 「ママ男 MAMA'S BOY」DVD
ジョン・へダー、ダイアン・キートン主演 マザコン男の自立話
「チャーリー・バレットの男子トイレ相談室 CHARLie BARTLeTT」DVD
アントン・イエルチェン、ロバート・ダウニーJr主演
2月12日 「クォ・ヴァディス QUO VADIS」DVD ネロ皇帝時代のローマ、キリスト教徒迫害を描く
1951年作品 ロバート・テイラー、デボラ・カー、ピーター・ユスティノフ主演
「ジャージの二人」DVD 堺雅人主演
2月13日 「そして、私たちは愛に帰る」DVD ドイツ・トルコを舞台に3組の親子を描く
見てきました。
しか~し、日本語タイトル「負けざる者たち」って、かなり苦しいタイトルやなぁ~。
調べてみたら「Invictus」とは1888年に発表されたウイリアム・アーネスト・ヘンリーの詩「不屈」で、
ラテン語のようです。
12歳で結核性関節炎、16歳で左下肢を切断、父の死の学業中断など、度重なる不幸に屈することなく
詩集を出版、新聞編集者となり、終生病と闘った方だそうです。
「Invictus」は結核入院中に書かれた詩で、病に屈っすることなく闘う壮絶な詩です。
最後の2行:
I am the master of my fate. 私がわが運命に支配者
I am the captain of my soul. 私がわが魂の指揮官 に、心の叫びが溢れています。
27年という気の遠くなるような投獄に耐え、折れそうなマンデラの心を支えたこの詩、
言葉の力ってすごいです。
因みに1995年の米オクラホマシティー連邦政府ビル爆破犯のティモシー・マクベイは
処刑される直前、このヘンリーの詩を書いたメモを刑務所長に手渡したそうです。
欧米では有名な詩なのでしょうね。
**********************
インビクタス 負けざる者たち
**********************
日本ではラグビーよりサッカーの方がメジャーなスポーツです。
ところが・・・
どうも英国では上流階級がラグビーを、労働者階級はサッカーという住み分けがあるようです。
以前英国かぶれの日本人(女性です)にサッカーの話をしたら
「あぁ、労働者階級のスポーツね。私はラグビーファンですから」っと言われてしまいました


何とタカビーなやっちゃ!英語で言うならスノビッシュですか!
南アではラグビーは白人のスポーツということで、アパルトヘイトの象徴だったようですね。
映画の中でも、マンデラの白人SPが黒人SPに
「サッカーは乱暴者がする紳士のスポーツ、ラグビーは紳士がする乱暴なスポーツ」といった
ジョーク?を言ってました。
オリンピックやサッカーワールドカップ、ワールドベースボールクラシックを見ればわかるように、
スポーツは国威を発揚し、人々の気持ちを一つにする大きな力を持っています。
銃を持たない戦争のようなものです。
卒業式で日の丸・君が代を拒否しても、オリンピックやワールドカップで国旗掲揚や国歌斉唱に
反対する人はいないどころか、旗を振り、顔に日の丸のペインティングまで。
誰もが一時的にせよ愛国者に変わります。スポーツの力もスゴイです。

<ラグビーで国を一つに>
1990年2月11日のマンデラ氏釈放から、今年はちょうど20年だったのですね。
当時、黒人側には白人に対する積年の恨みつらみがあり、白人側は黒人の仕返しが始まるのではと
戦々恐々。
マンデラ氏はスポーツの力を評価し、分裂しそうな状態の国民を一つにまとめる道具として
ラグビーワールドカップの自国開催を優勝で飾るべく、キャプテンフランソワにリーダーとしての姿勢を示し、
チームメンバーの名前を覚え一人一人に声をかける。

しかし、弱小チームから連勝し決勝戦で強豪ニュージーランドに勝利するって・・・、
実話なんだけれどもそんなことは可能なの?
どの程度のダメチームで、どれほどの特訓を積んだかは触れられていないので、何とも言えませんが、
世界で1位2位を争うレベルって「不屈」の精神論で押して成るものなんでしょうか?
「グラン・トリノ」「チェンジリング」でぐいぐい引き込まれ感動した経験から
ちょっと期待が大きすぎたかも?しれません。
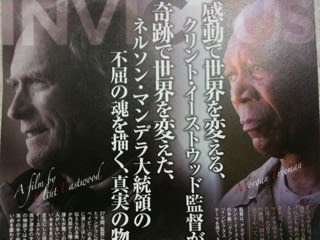
「負けざる者」はラグビーワールドカップ南ア代表を指すのではなくマンデラその人。
国のリーダーとはかくあるべきという、マンデラの信念・指導力・人望・不屈の精神に魅せられました。
ただ家族は大変だろうなぁ~。
身内ということで逮捕されたり、息子は事故(おそらく)に見せて殺されたりでは、
いくら反アパルトヘイト運動の意義や新しい国家のためにとはいえ「何故あなたじゃなきゃダメなの?」
とか「子供の身の安全も考えて」となりますよね。
闘士は孤独。 家族の話はタブーというのも無理からぬこと。
「危険を覚悟しなければ、指導者の資格は無い」
「赦しが魂を自由にする。赦しこそ恐れを取り除く最強の武器なのだ」
「変わるべき時に私自身が変われないなら、人々に変化を求められません」
こういう人が出ないと国は変わらへんなぁ~。
「人を呪わば穴二つ」
「憎しみは憎しみの連鎖を生むだけ」
ガンジーにキング牧師、マンデラ、世の中を変えるのは押さえつける力ではなく非暴力による赦しでしょうか。
新興国を示すBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の最後のSを大文字にして
南アフリカを入れようなんて動きがあるほど、20年後の現在南アの経済は好調らしい。
今年の6月はラグビーではなくサッカーのワールドカップ南アフリカ開催が控えてますが
南アは強いんでしょうか?
サムライブルー(最近はこう呼ぶんですか?)がんばれ!

もう一つヘンリーの名言をご紹介。
「人生は、私たちが人生とは何かを知る前にもう半分過ぎている。」
厳しい言葉やなぁ。
エンディング曲は一瞬「オーシャンズ」に続いてこれも平原綾香?と思っちゃいました

***** 見た 映画 *****
2月 8日 「インビクタス 負けざる者たち」@ワーナーマイカルシネマズ海老名
2月 9日 「マンデラの名もなき看守」DVD

「クララ・シューマン」DVD シューマンと妻クララ、そしてブラームスとの物語
2月11日 「ママ男 MAMA'S BOY」DVD
ジョン・へダー、ダイアン・キートン主演 マザコン男の自立話
「チャーリー・バレットの男子トイレ相談室 CHARLie BARTLeTT」DVD
アントン・イエルチェン、ロバート・ダウニーJr主演
2月12日 「クォ・ヴァディス QUO VADIS」DVD ネロ皇帝時代のローマ、キリスト教徒迫害を描く
1951年作品 ロバート・テイラー、デボラ・カー、ピーター・ユスティノフ主演
「ジャージの二人」DVD 堺雅人主演
2月13日 「そして、私たちは愛に帰る」DVD ドイツ・トルコを舞台に3組の親子を描く










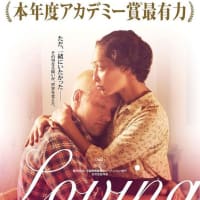









映画の中のエピソードが実際にもそのまま多くあってほしいと思いました。
ところで本題とは別なんですが、
>「クォ・ヴァディス QUO VADIS」DVD
こういうのがあったんですね。
実は昔、原作を読んだことがあります(とても長く複雑で文庫3巻!)。 本当に衝撃的な作品でした。
この世界が映像化ってまるで不可能と思っていたので、この情報はびっくりです。 あったら観てみたいものです(ちょっと観るのが怖い気もしますが)
でも、我々の心の持ちようで、変わり得るんだ!ということも併せて感じました。
ガンジーの第一歩も、南アからでしたね。
まさか「クォ・ヴァディス」に反応していただけるとは思っていませんでした。
文庫3巻読まれたのですね!映画も168分です。CGもない1951年製作ですがカラーでなかなか迫力あります。以前「ローマ帝国に挑んだ男 パウロ 2000」で書いた時に、友人がDVDを貸してくれました。
「水野晴郎のDVDで観る世界名作映画」の一本で最近売られているシリーズの中のものだと思います。
映画の中に素晴らしい言葉がたくさんありましたね。
日本の政治家にはリーダーたる政治家の品格をマンデラから学んで欲しいもんです。
ガンジーの弁護士としての仕事は南アからだったのですね。御指摘ありがとうございました。
おバカコメでおもしろおかしく コメしようとしたのに ryokoさんの感想レビュみてたら できませんね・・・
言葉の力・・・ひらめき・・・今以上の力を引き出すには・・・
マンデラの難しい精神論や名言がいっぱいでしたが それを貫くのは たいへんでしょうね。
相手を許すこと・・・寛容・・・・魂を自由にする・・・
重いですね。
少しずつ変わっていった南アフリカですが いまなお貧困や治安は 悪い地域は根強いようです。
大統領になったからといって ラグビーのチーム名やユニフォームを強引に変えようとはせず! チームはそのまま継承。
黒人の警護係りが人手が足りないから増員を要請したら 白人が新たに警護係りにきたことでも摩擦がありましたが
マンデラは”虹の国”をつくるためには混成チームでないと 国民に理念を理解してもらえないと信念を貫きとおした姿はすばらしかったです
ボク、心の中で ポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーの「エボニー&アイボリー」が流れました(→言わずと知れた白人と黒人の調和のシンボル曲!)
https://www.youtube.com/watch?v=TZtiJN6yiik
反応が遅くて申し訳ありません。
アメリカで頻発する事件を見ていても、人種の問題は難しいですね。マンデラはまさに「不屈の人」。建国に尽力なさいましたが、現状はどうなのでしょうね?
マンデラさんの葬儀では、手話通訳の方の滅茶苦茶なおじさん報道や、マンデラ像制作に関しても驚くような報道があったりして…亡くなってもなおマンデラさん絡みの話題は尽きませんでしたね。
「エボニー&アイボリー」私もこの曲好きです。
映像のふたり、若~い!です。