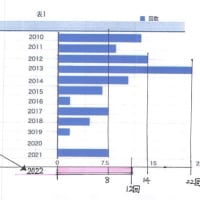終活とは一般的には持ち物の整理を示すことが多いが、死を迎える心境に一歩一歩近づいて行くのも終活の一つ、と考える。
私は最近、和歌や短歌の世界、人生最後の言葉等にも収集のジャンルを広げている。
論語の一節に、「鳥のまさに死なんとするや、その鳴くこと哀し。人のまさに死なんとするや、その言ふこと善し。(泰伯第八)」とある。
自分の死に臨んでの人生の回顧や新たな心境の発見が最後の言葉となっている。死という極限の状況の中でどのように生と対峙し、それをどう表現したかが、残されたそのことばから感じ取れる。
辞世の句は7世紀頃に死を迎えた人によって作られるようになった、とされる。江戸時代にもその伝統は継承されて、特に刑に臨んだ際の詩は辞世の句の主流をしめてきた。そこには無念の境地、時には諦観が込められている。
明治維新前夜に捕縛さて落命した志士達が獄中で多くの句を読んだ。いま、遅まきながら、司馬遼太郎の長編「竜馬がゆく」を読み始めた。この作品では数多くの幕末の士が登場するが、辞世の歌をも紹介されているはずであり、それらを読むのを楽しみにしている。
戦没学徒の遺書を所収した「きけわだつみのこえ」は若い時に読んだ。死に臨んでの叫びが記録されており、当時も深い感動を得たが,当時はざっと読み終えた、に近い。最近、再度手に取って読み直している。若くして前途を絶たれた彼らの心中は、いかばかりであったことか。私は高齢まで生きて結果的に終活を考えねばならない歳になったが、今はより深く、彼らの心情を感取れる様になっている。
心から搾り出た句に優劣はつけたくないが、私が最も感じっている辞世の句は、以下である。
■風さそふ 花よりもなほ我はまた 春の名残をいかにとやせん 浅野長矩
江戸城、松の廊下における吉良上野介刃傷事件は1701年3月に起きた。時に長矩35歳だった。
俗説がいっぱいあるから真実との区別は私にはつかないが、浅野による度重なるいじめを受けた長矩が怒り心頭に達し吉良を斬りつけ、即日切腹となった。長矩は無念の遺言すらできず「ふしぎに存ずべく候」とだけ言った、と言う。お上側の対応が通常例とひどく違っていたのだろう。無念の思いは一入だったにちがいない。
無念の思いを託した一首、なかなかである。風に吹かれて散る花も名残おしいだろうが、それよりなお無念を感じる私は、一体どうしたらいいのか??美しい辞世である。長矩は刀を抜いた時点で死を意識しただろうが、一方的になされた突然の切腹の裁断にも納得できなかったのだろう。死を数時間後に迎えた人間がこのような形で心境を吐露できたなど、信じ難い。
歌人の永田和宏氏は「短歌はその短さゆえに、ある瞬間の心の動きを言葉で定着するという点において、他の文芸の追随を詐さない」(一部改変)、と述べている。その通りだと思う。
私は最近、和歌や短歌の世界、人生最後の言葉等にも収集のジャンルを広げている。
論語の一節に、「鳥のまさに死なんとするや、その鳴くこと哀し。人のまさに死なんとするや、その言ふこと善し。(泰伯第八)」とある。
自分の死に臨んでの人生の回顧や新たな心境の発見が最後の言葉となっている。死という極限の状況の中でどのように生と対峙し、それをどう表現したかが、残されたそのことばから感じ取れる。
辞世の句は7世紀頃に死を迎えた人によって作られるようになった、とされる。江戸時代にもその伝統は継承されて、特に刑に臨んだ際の詩は辞世の句の主流をしめてきた。そこには無念の境地、時には諦観が込められている。
明治維新前夜に捕縛さて落命した志士達が獄中で多くの句を読んだ。いま、遅まきながら、司馬遼太郎の長編「竜馬がゆく」を読み始めた。この作品では数多くの幕末の士が登場するが、辞世の歌をも紹介されているはずであり、それらを読むのを楽しみにしている。
戦没学徒の遺書を所収した「きけわだつみのこえ」は若い時に読んだ。死に臨んでの叫びが記録されており、当時も深い感動を得たが,当時はざっと読み終えた、に近い。最近、再度手に取って読み直している。若くして前途を絶たれた彼らの心中は、いかばかりであったことか。私は高齢まで生きて結果的に終活を考えねばならない歳になったが、今はより深く、彼らの心情を感取れる様になっている。
心から搾り出た句に優劣はつけたくないが、私が最も感じっている辞世の句は、以下である。
■風さそふ 花よりもなほ我はまた 春の名残をいかにとやせん 浅野長矩
江戸城、松の廊下における吉良上野介刃傷事件は1701年3月に起きた。時に長矩35歳だった。
俗説がいっぱいあるから真実との区別は私にはつかないが、浅野による度重なるいじめを受けた長矩が怒り心頭に達し吉良を斬りつけ、即日切腹となった。長矩は無念の遺言すらできず「ふしぎに存ずべく候」とだけ言った、と言う。お上側の対応が通常例とひどく違っていたのだろう。無念の思いは一入だったにちがいない。
無念の思いを託した一首、なかなかである。風に吹かれて散る花も名残おしいだろうが、それよりなお無念を感じる私は、一体どうしたらいいのか??美しい辞世である。長矩は刀を抜いた時点で死を意識しただろうが、一方的になされた突然の切腹の裁断にも納得できなかったのだろう。死を数時間後に迎えた人間がこのような形で心境を吐露できたなど、信じ難い。
歌人の永田和宏氏は「短歌はその短さゆえに、ある瞬間の心の動きを言葉で定着するという点において、他の文芸の追随を詐さない」(一部改変)、と述べている。その通りだと思う。