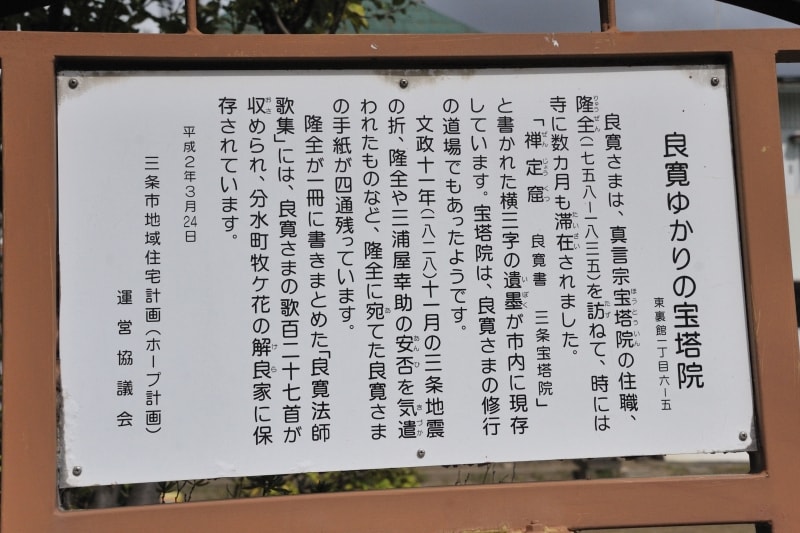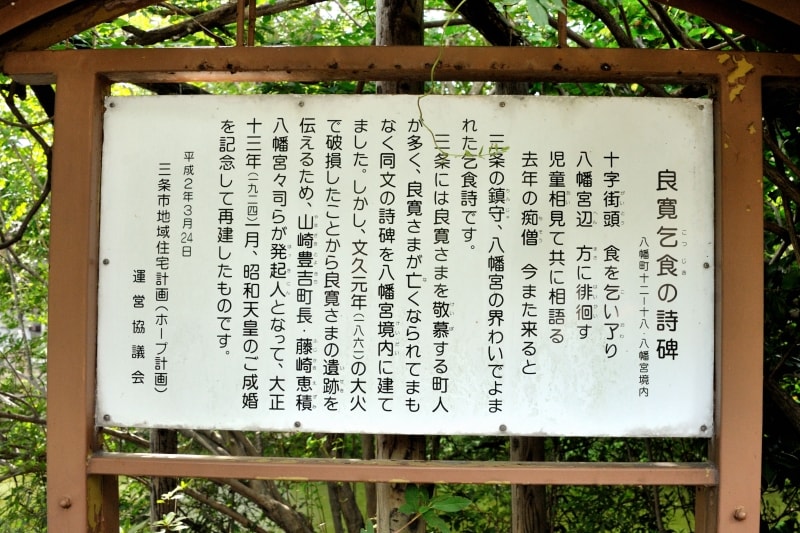20日のお彼岸の中日(春分の日)は、予期せぬ「なごり雪」で、家の中で過ごしてしまいました。
その翌日21日の午前、私は長岡市和島島崎の菩提寺「隆泉寺」に、お墓参りをしてきました。
いつ来ても、なんとなくうれしくなる「お墓参り」なのです。
ご先祖へのお参りであることの他に、ここには「良寛さまのお墓」もあるのです。
そして、いつもいつも代わり映えのしない「良寛さまゆかりの写真」などを撮っています。
今年も、同じことでした。そしてなんとなく満たされてしまっています。


訪れるたびに、「良寛さまの銅像やお墓」を撮っています。
「禅宗のお坊さん」であった良寛さまのお墓が「浄土真宗のお寺」にあるというのも、何と言うかいい感じに思われます。
たぶん、最後まで良寛さまを面倒見られた「木村家」の菩提寺にお墓があると言うことでしょう。
おそらくそのことは、良寛さまも「お願いします」ということであったろうと思います。
「良寛さま」というのは、そういう「おおらかな、とらわれのない人柄」であったと思っています。



境内には戊辰戦争の戦火を逃れた「経蔵」が残っています。


お墓参りの後先に必ず通る「木村家」の裏を通る道、そこに「良寛さま」が最晩年を過ごされた「終焉の地」の碑があります。
ここには「貞心尼と語り明かした」庵があったのだ、そう思うと胸に迫るものがあります。

その翌日21日の午前、私は長岡市和島島崎の菩提寺「隆泉寺」に、お墓参りをしてきました。
いつ来ても、なんとなくうれしくなる「お墓参り」なのです。
ご先祖へのお参りであることの他に、ここには「良寛さまのお墓」もあるのです。
そして、いつもいつも代わり映えのしない「良寛さまゆかりの写真」などを撮っています。
今年も、同じことでした。そしてなんとなく満たされてしまっています。


訪れるたびに、「良寛さまの銅像やお墓」を撮っています。
「禅宗のお坊さん」であった良寛さまのお墓が「浄土真宗のお寺」にあるというのも、何と言うかいい感じに思われます。
たぶん、最後まで良寛さまを面倒見られた「木村家」の菩提寺にお墓があると言うことでしょう。
おそらくそのことは、良寛さまも「お願いします」ということであったろうと思います。
「良寛さま」というのは、そういう「おおらかな、とらわれのない人柄」であったと思っています。



境内には戊辰戦争の戦火を逃れた「経蔵」が残っています。


お墓参りの後先に必ず通る「木村家」の裏を通る道、そこに「良寛さま」が最晩年を過ごされた「終焉の地」の碑があります。
ここには「貞心尼と語り明かした」庵があったのだ、そう思うと胸に迫るものがあります。