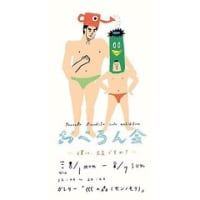大師といえば弘法大師、道心といえば苅萱道心。
と言われるほど、戦後のある時期までは苅萱道心の
話は誰でも知っていたって読んで驚く。
三野恵さんが「苅萱道心と石童丸のゆくえ」で
書いてはる。苅萱道心は忘れられつつあるのでは。

基本は仏教の教えを語るもので、室町の末期に
謡曲や説教節などの語り芸能として成立。
能や琵琶にも取り入られているそうだ。
以来江戸から明治・大正・昭和へと、
絵解き、浄瑠璃、歌舞伎、戯作、講談、
浪曲から小説、絵本、はては漫画まで、
さまざまな形でそして内容も変化しながら
語り継がれてきたらしいんだね。

高野山に世を逃れた苅萱を息子の石童丸が探し歩いて
再会するという話で、息子とわかっても知らないふりを
するとか、死ぬ間際に父であることを明かすとか
色んなバリエーションがある。
歌舞伎ひとつとっても、江戸時代の外題(作品)に対して
明治政府が史実に基づくように、とか歌舞伎めいた
所作を禁止した(明治5年)影響で苅萱道心の
物語も変化するっていうところだけでも面白い。
小説が登場し、表現もまた登場人物の性格付けも
変わってくるなど、伝統というか息の長い話は
興味がつきない。
☆
苅萱堂というお寺さんが高野山に実際あって、
苅萱道心が修行をした、っていう本山の説明を
読むに至っては、なにこれって実話だったのかと
知らないことだらけw
でもなぜ、苅萱道心の話は消えつつあるのだろう?
三野恵さんはそれには触れていない。
と言われるほど、戦後のある時期までは苅萱道心の
話は誰でも知っていたって読んで驚く。
三野恵さんが「苅萱道心と石童丸のゆくえ」で
書いてはる。苅萱道心は忘れられつつあるのでは。

基本は仏教の教えを語るもので、室町の末期に
謡曲や説教節などの語り芸能として成立。
能や琵琶にも取り入られているそうだ。
以来江戸から明治・大正・昭和へと、
絵解き、浄瑠璃、歌舞伎、戯作、講談、
浪曲から小説、絵本、はては漫画まで、
さまざまな形でそして内容も変化しながら
語り継がれてきたらしいんだね。

高野山に世を逃れた苅萱を息子の石童丸が探し歩いて
再会するという話で、息子とわかっても知らないふりを
するとか、死ぬ間際に父であることを明かすとか
色んなバリエーションがある。
歌舞伎ひとつとっても、江戸時代の外題(作品)に対して
明治政府が史実に基づくように、とか歌舞伎めいた
所作を禁止した(明治5年)影響で苅萱道心の
物語も変化するっていうところだけでも面白い。
小説が登場し、表現もまた登場人物の性格付けも
変わってくるなど、伝統というか息の長い話は
興味がつきない。
☆
苅萱堂というお寺さんが高野山に実際あって、
苅萱道心が修行をした、っていう本山の説明を
読むに至っては、なにこれって実話だったのかと
知らないことだらけw
でもなぜ、苅萱道心の話は消えつつあるのだろう?
三野恵さんはそれには触れていない。