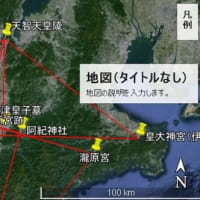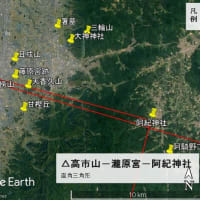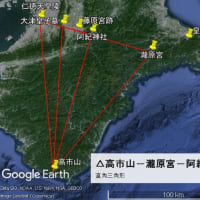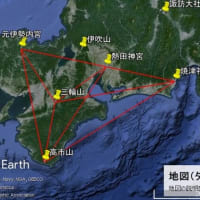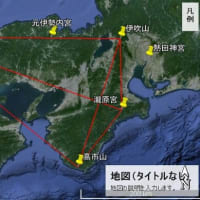ちょっと、思いつきました。脈絡ないかもしれませんが、ご勘弁のほど。
現在の日本書紀の骨格は720年にできたものでしょう。
ですが、それ以前にも、変化する前の日本書紀はあり、以後にも日本書紀は変化しているはずです。
645年の乙巳の変・大化の改新は720年以前に構想されていたとすると、現在の日本書紀とはずいぶんと違っていたと想像します。
まず、天武天皇時代に出来上がっていた日本書紀があったはずです。
672年に天武政権ができたとし、日本書紀の構想を練ったとして、720年に出来上がったとすると、あまりに時間がかかりすぎです。
日本書紀の編纂にもっと緊急性があった場合があるはずです。
それは、663年の白村江の戦いに参戦した日本のその時の政権は、それ以前の政権と違っていたことを示したい場合です。
そして、天武政権は、その白村江の戦いを主導した政権を滅ぼして、新たに樹立された政権とする場合です。
おそらく、645年~672年は正統性のない政権が日本を牛耳っていたことにしたかったんではないかと考えます。
そうでないと、唐は白村江の戦いの責任追及し、そのままの政権ならば、現状の変更を要求するでしょう。
その辺は、その時のアジアの情勢もあったでしょうし、唐は日本に対し、それほど根本的な要求をしなかったように思えます。日本を利用するという思惑の方が勝っていたように思えます。
あくまで空想ですが、663年の白村江の敗戦の影響は大きいものでした。
天武天皇の立場でみると、白村江の戦いに出陣したかどうか、責任のある立場だったかどうか、はっきりわかりませんが、もし王権が続いていたとすると、乙巳の変を創りださないと、白村江の戦いにも、同じ王権が続いたことになってしまいます。
《天武天皇(大海人皇子)は参戦したと思いますが》
663年白村江の戦いでは、唐にたてついたけれども、その政権はずっと以前から続いた政権ではなく、645年に日本国内でクーデターがあり、その政権が主導して白村江に参戦したものだった、ということにしました。
そして、その645年に成立した政権は672年に壬申の乱で、元の王権に戻ったか、新王権になり、親唐であることにしたかった、ものではないでしょうか。
663年日本が白村江に参戦したわけは、645年~672年の間は日本の政権は反唐で百済系の政権になっていて、百済復興を狙い参戦したのは、そのためだった、ということにしたかった、のです
645年~672年は百済系の王権であれば白村江の参戦は致し方なかったことになりえます。
そして、豊璋(百済王)は、落雷のために落馬して、数か月後亡くなります。
これは天武天皇の画策かもしれず、同時に唐の要求だった可能性もあります。
(現在の日本書紀では、豊璋は白村江から高句麗方面に逃亡したとされています)
以前にも考えましたが、唐の要求の最重要なものは日本にいる「百済の王家」を滅ぼすことです。
唐の使者としては、多くの贈り物ももらいますし、その他のことは目をつぶるが、「百済王家」だけは滅ぼせ、が唐の要求だったはずです。
これ幸いに豊璋は落雷で馬から落ち、その怪我がもとでなくなります。(薬狩りなどやるような時期ではないと思えますし、天武天皇が追い込んだ可能性があります)
不比等は、名前を変え、かくまわれて生き延びますが、豊璋は病床で『百済復興』を、不比等に遺言として残したでしょう。
(藤原は不死・韓でしょう)
ところが年月が経ち、今度は天武系が危うくなってきます。ついには滅びます。
すると厄介なことになります。
初めは、蘇我氏の正統な政権が645年乙巳の変のクーデターで転覆され、百済系の政権に変わったものが、672年壬申の乱で再び正統性を持つものに変わった、だったはずです。
それが、645年の乙巳の変は正統なものであり、蘇我氏が正統ではなかった。しかし、672年に正統な天智の後継の大友皇子が破れ、正統といえなくもないが純粋に正統とはいえない天武天皇が王権を担ったというふうに変えられた。
天武天皇が日本書紀の編纂を命じたことになっていますから、天武天皇に正統性がないとなるとおかしいはずです。
ですから、なんとなく天武系の正統性は否定されているように記述されることになります。
変の後、私邸に戻った古人大兄皇子は「韓人が鞍作臣(入鹿)を殺害した」と
発言しますが、これは、最初からの構想に入っていたのではないでしょうか。
「乙巳の変」で生まれた政権は百済主導のものだったことになるからです。
また、後の構想になっても、消すことはなかったのは、後に百済系の王権になったからでしょう。
乙巳の変は架空のもので、ローマの「カエサル暗殺」をモチーフとしていると思えます。
何かクーデターが起きたことにしたいとして、どんな物語を選ぶかというとき、参考にしたのは『カエサル暗殺』でした。
以前にも書きましたが、「古人大兄皇子」は「ブルータス」から創られた名前にみえます。
「古人太子・ふるひとひつぎのみこ」とのことですが、まるっきり「ブルータス」です。
http://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_25.html
▼日本書紀 巻第二十五 孝徳天皇紀
市秦造田來津、謀反。或本云、古人太子。或本云、古人大兄。此皇子、入吉野山、故或云吉野太子。
その後の古人大兄皇子の行動はブルータスとそっくりです。
しかし、このエピソードが記述されているのは『カエサル暗殺』を選んだからです。
『カエサル暗殺』が選ばれた理由ではありません。
検索を続けていて、「乙巳の変」を記述するのに『カエサル暗殺』が選ばれた理由は、これではないかと思われるものがありました。
恥ずかしながら知りませんでしたので、ビックリポンでした。
しかし、有名なことのようです。
http://www.jiten.info/dic/rome/gaius_julius_caesar.html
カエサルは、女神ウェヌス(ヴィーナス)の後裔であることを誇りとするパトリキ系の名門の出。 ただカエサル家自体は名士の祖先がおらず、第一級の名門には属さなかった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%8C%E3%82%B9
アンキセスとの間の子アイネイアースはローマ建国の祖にして、ガイウス・ユリウス・カエサルの属するユリウス氏族の祖とされた。ここからカエサルはウェヌスを祖神として、彼女を祀る為の壮麗な神殿を奉献したという。 また、カエサルの祖神として軍神ともされた。
カエサルは女神ウェヌス(ヴィーナス)の子孫だ、ということになっているようです。
これが選ばれた理由ではないでしょうか。
日本の場合は「女王・卑弥呼の子孫」ということになります。
現在の日本書紀の骨格は720年にできたものでしょう。
ですが、それ以前にも、変化する前の日本書紀はあり、以後にも日本書紀は変化しているはずです。
645年の乙巳の変・大化の改新は720年以前に構想されていたとすると、現在の日本書紀とはずいぶんと違っていたと想像します。
まず、天武天皇時代に出来上がっていた日本書紀があったはずです。
672年に天武政権ができたとし、日本書紀の構想を練ったとして、720年に出来上がったとすると、あまりに時間がかかりすぎです。
日本書紀の編纂にもっと緊急性があった場合があるはずです。
それは、663年の白村江の戦いに参戦した日本のその時の政権は、それ以前の政権と違っていたことを示したい場合です。
そして、天武政権は、その白村江の戦いを主導した政権を滅ぼして、新たに樹立された政権とする場合です。
おそらく、645年~672年は正統性のない政権が日本を牛耳っていたことにしたかったんではないかと考えます。
そうでないと、唐は白村江の戦いの責任追及し、そのままの政権ならば、現状の変更を要求するでしょう。
その辺は、その時のアジアの情勢もあったでしょうし、唐は日本に対し、それほど根本的な要求をしなかったように思えます。日本を利用するという思惑の方が勝っていたように思えます。
あくまで空想ですが、663年の白村江の敗戦の影響は大きいものでした。
天武天皇の立場でみると、白村江の戦いに出陣したかどうか、責任のある立場だったかどうか、はっきりわかりませんが、もし王権が続いていたとすると、乙巳の変を創りださないと、白村江の戦いにも、同じ王権が続いたことになってしまいます。
《天武天皇(大海人皇子)は参戦したと思いますが》
663年白村江の戦いでは、唐にたてついたけれども、その政権はずっと以前から続いた政権ではなく、645年に日本国内でクーデターがあり、その政権が主導して白村江に参戦したものだった、ということにしました。
そして、その645年に成立した政権は672年に壬申の乱で、元の王権に戻ったか、新王権になり、親唐であることにしたかった、ものではないでしょうか。
663年日本が白村江に参戦したわけは、645年~672年の間は日本の政権は反唐で百済系の政権になっていて、百済復興を狙い参戦したのは、そのためだった、ということにしたかった、のです
645年~672年は百済系の王権であれば白村江の参戦は致し方なかったことになりえます。
そして、豊璋(百済王)は、落雷のために落馬して、数か月後亡くなります。
これは天武天皇の画策かもしれず、同時に唐の要求だった可能性もあります。
(現在の日本書紀では、豊璋は白村江から高句麗方面に逃亡したとされています)
以前にも考えましたが、唐の要求の最重要なものは日本にいる「百済の王家」を滅ぼすことです。
唐の使者としては、多くの贈り物ももらいますし、その他のことは目をつぶるが、「百済王家」だけは滅ぼせ、が唐の要求だったはずです。
これ幸いに豊璋は落雷で馬から落ち、その怪我がもとでなくなります。(薬狩りなどやるような時期ではないと思えますし、天武天皇が追い込んだ可能性があります)
不比等は、名前を変え、かくまわれて生き延びますが、豊璋は病床で『百済復興』を、不比等に遺言として残したでしょう。
(藤原は不死・韓でしょう)
ところが年月が経ち、今度は天武系が危うくなってきます。ついには滅びます。
すると厄介なことになります。
初めは、蘇我氏の正統な政権が645年乙巳の変のクーデターで転覆され、百済系の政権に変わったものが、672年壬申の乱で再び正統性を持つものに変わった、だったはずです。
それが、645年の乙巳の変は正統なものであり、蘇我氏が正統ではなかった。しかし、672年に正統な天智の後継の大友皇子が破れ、正統といえなくもないが純粋に正統とはいえない天武天皇が王権を担ったというふうに変えられた。
天武天皇が日本書紀の編纂を命じたことになっていますから、天武天皇に正統性がないとなるとおかしいはずです。
ですから、なんとなく天武系の正統性は否定されているように記述されることになります。
変の後、私邸に戻った古人大兄皇子は「韓人が鞍作臣(入鹿)を殺害した」と
発言しますが、これは、最初からの構想に入っていたのではないでしょうか。
「乙巳の変」で生まれた政権は百済主導のものだったことになるからです。
また、後の構想になっても、消すことはなかったのは、後に百済系の王権になったからでしょう。
乙巳の変は架空のもので、ローマの「カエサル暗殺」をモチーフとしていると思えます。
何かクーデターが起きたことにしたいとして、どんな物語を選ぶかというとき、参考にしたのは『カエサル暗殺』でした。
以前にも書きましたが、「古人大兄皇子」は「ブルータス」から創られた名前にみえます。
「古人太子・ふるひとひつぎのみこ」とのことですが、まるっきり「ブルータス」です。
http://www.seisaku.bz/nihonshoki/shoki_25.html
▼日本書紀 巻第二十五 孝徳天皇紀
市秦造田來津、謀反。或本云、古人太子。或本云、古人大兄。此皇子、入吉野山、故或云吉野太子。
その後の古人大兄皇子の行動はブルータスとそっくりです。
しかし、このエピソードが記述されているのは『カエサル暗殺』を選んだからです。
『カエサル暗殺』が選ばれた理由ではありません。
検索を続けていて、「乙巳の変」を記述するのに『カエサル暗殺』が選ばれた理由は、これではないかと思われるものがありました。
恥ずかしながら知りませんでしたので、ビックリポンでした。
しかし、有名なことのようです。
http://www.jiten.info/dic/rome/gaius_julius_caesar.html
カエサルは、女神ウェヌス(ヴィーナス)の後裔であることを誇りとするパトリキ系の名門の出。 ただカエサル家自体は名士の祖先がおらず、第一級の名門には属さなかった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%8C%E3%82%B9
アンキセスとの間の子アイネイアースはローマ建国の祖にして、ガイウス・ユリウス・カエサルの属するユリウス氏族の祖とされた。ここからカエサルはウェヌスを祖神として、彼女を祀る為の壮麗な神殿を奉献したという。 また、カエサルの祖神として軍神ともされた。
カエサルは女神ウェヌス(ヴィーナス)の子孫だ、ということになっているようです。
これが選ばれた理由ではないでしょうか。
日本の場合は「女王・卑弥呼の子孫」ということになります。