
先日このブログでもご紹介させていただいた
解説と実演で知る<日本舞踊と邦楽の世界> 坂東三津五郎がひもとく“日本舞踊” click
click
に行ってきました。
私は日本の伝統文化は華道だけは極めていますが日本舞踊は習っていないので子供の頃から憧れでした。
ブロ友さんには日本舞踊の名取の方もいて、絢爛豪華な衣装の発表会の写真をブログで拝見する度、素敵

 とうっとりしていました。
とうっとりしていました。
歌舞伎役者でもあり日本舞踊の家元でもある坂東三津五郎さんがひもとく「日本舞踊」。に、B-Promotion様ご招待いただきました。
場所は古きよき日本の江戸文化を継承する地、両国の江戸東京博物館内にあるホールです。

 東京都江戸東京博物館ホール JR両国駅西口からすぐ。
東京都江戸東京博物館ホール JR両国駅西口からすぐ。


マスコットキャラクターギボちゃんと写真も撮れます。

お土産物屋さんやら、いろいろとあって楽しい場所なのです。


歌舞伎大好き!な私は歌舞伎役者でもあり日本舞踊の家元でもある坂東三津五郎さんの解説を聞けるなんてしあわせ~。




日本の伝統芸能を継承する活動を続けている「東京発・伝統WA感動」さんは、いつも素敵なイベントを開催されています。
今回のイベントは日本舞踊の基礎から、歌舞伎舞踊の動き・衣裳つけ・化粧までを、実演付きでレクチャーするというワークショップ形式の公演。
 一部は日本舞踊家の化粧する様子をから見せていただきました。
一部は日本舞踊家の化粧する様子をから見せていただきました。
歌舞伎独特の隈取かとおもっていたら、日本舞踊でも隈取をするそうで、隈取の色にいろんな意味があるそうです。初めて知るなるほど! の知識。
の知識。
江戸時代、歌舞伎とともに発展したのが、日本舞踊の一つ、歌舞伎舞踊。
歌舞伎役者さんでもあり、日本舞踊の家元である坂東三津五郎さんのお話がとても楽しくて、わかりやすくてグイグイ引き込まれました。

舞台で実際に衣装を着付ける様子や帯を締める様子もみせていただきましたが軽めの衣装と帯でも3人がかり。。。すごい。
日本舞踊の衣装は相当重いのでは?と思っていましたが、帯を締めるのに5人がかりの衣装もあるそうで、演じる技術だけでなく体力もいることを改めて感じました。
 二部では坂東以津緒さんが子供、夫、妻、祖母と4役を一人で演じ分ける坂東流のお家芸とも言える清元『流星』の一部を見せていただきました。
二部では坂東以津緒さんが子供、夫、妻、祖母と4役を一人で演じ分ける坂東流のお家芸とも言える清元『流星』の一部を見せていただきました。
見せるというよりも魅せる。観るというより魅せられる。
魅力的な舞は美しい衣装の重さも感じさせず、まさにしなやかで艶やかな日本の伝統芸術の 粋
粋 を感じました。
を感じました。
日本舞踊のしなやかな品のある美しい動きが品のよい立ち居振る舞いが身につくので、日本舞踊は憧れでした。自分に女の子が生まれたら習わせたいとも思っていました。
その夢はいつできるかわかりませんが孫に託します。(笑)
 東京発・伝統WA感動
東京発・伝統WA感動  click
click
東京発・伝統WA感動」は年間を通じて様々なプログラムが実施されます。
10月11日(木)に開催される「三弦 海を越えて ―アジアから日本へ―」の公演は、ちょっと気になる内容となっています。
日本の伝統音楽において重要な役割を果たしているのが、三味線、箏、胡弓などの弦楽器。
中近東に端を発し、アジアにもたらされた三弦は、琉球で三線となり、16世紀後半に堺に伝来して以後、三味線としての様々な工夫・改良を経て、豊かな魅力を湛える音楽を生み出したのだそうです。
 「三弦 海を越えて ―アジアから日本へ―」
「三弦 海を越えて ―アジアから日本へ―」  詳細クリック
詳細クリック
義太夫節「ひらかな盛衰記 逆櫓の段」 浄瑠璃:豊竹咲甫大夫、三味線:鶴澤清志郎
地歌「黒髪」 三弦:藤井昭子
長唄「越後獅子」 唄:今藤長一郎、三味線:杵屋栄八郎、囃子:藤舎呂英
<休憩>
【第二部】
中国の三弦
琉球古典音楽と舞踊 三線:比嘉康春、立方:志田真木 ほか
モンゴルの三弦
中国大三弦 費堅蓉(フェイ・ジェンロン)
津軽三味線 小山豊
中国大三弦と津軽三味線のセッション
解説:大城學(琉球大学教授)、司会:葛西聖司














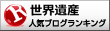











![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46c9f17b.96636b97.46c9f17c.83c810c6/?me_id=1423177&item_id=10000027&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftwgtea%2Fcabinet%2Fimgrc0120778920.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)










