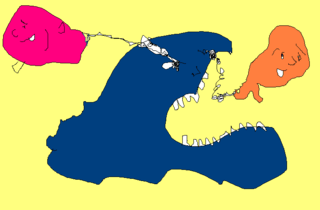
■村上春樹「エルサレム賞」受賞スピーチで感じたこと
村上春樹「エルサレム賞」授賞式講演、やっと全文を読むことができて、すごく感動した。
示唆に富むスピーチで、素晴らしいと思った。
何度も読み返すと、自分の心が震えた。
一度読んだだけでは、自分にはわからなかった。
日本の報道では、「村上春樹さんがエルサレムで反戦を主張した。イスラエル政府の爆撃攻撃を批判した。」というような数十秒の報道にとどまっていた。
彼の発言が正確に届くのは、その場にいた人々だけである。それは村上春樹の熱気や表情や間の取り方・・全てを感じ、同じ時間と空間を共有できる一期一会のものだけが共有できるかけがえのないもの。
村上春樹の言葉は、日本の報道「システム」にとって都合がいいものとして切り張られ加工される。
報道「システム」は、経済「システム」、政治「システム」・・・色々な「システム」同士が、ガチガチに固定化した「システム」同士で依存して、ベッタリはがれなくなっている。
そういう、高く堅固な壁である「システム」の前で、ぶつかって壊れる卵があるとしたら、村上春樹は常に卵側に立つと言った。
村上春樹の発言は示唆に富み、かなり重要だと感じた。
ココで日本語訳全文、ココで英語全文を読めるので是非読んでみてほしい。
以下に、47NEWSから抜粋して引用。
■村上春樹「エルサレム賞」受賞スピーチより抜粋
===================================
In most cases, it is virtually impossible to grasp a truth in its original form and depict it accurately. This is why we try to grab its tail by luring the truth from its hiding place, transferring it to a fictional location, and replacing it with a fictional form.
多くの場合、真実の本来の姿を把握し、正確に表現することは事実上不可能です。だからこそ、私たちは真実を隠れた場所からおびき出し、架空の場所へと運び、小説の形に置き換えるのです。
===================================
⇒
真実とは何か、事実とは何か。
物事は、百の視点があれば百の解釈が存在する。
それは、百人の人がいれば、百の自意識があり、人間自体が自意識を中心に世界を自由に解釈しながら生きているから、そこからは逃れられない。
自意識過剰で、自分の都合に応じて世界を解釈しようとすれば、真実や事実は無限に発散していく。
ただ、できる限り自意識を無くそうと努力して世界をとらえようとすれば、真実や事実はある一点に収束していくかもしれない。
真実や事実というものは、そんなあやふやなものだからこそ、村上春樹は架空の隠れた場所で小説という物語を書くという。
===================================
“Between a high, solid wall and an egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg.”
Yes, no matter how right the wall may be and how wrong the egg, I will stand with the egg. Someone else will have to decide what is right and what is wrong; perhaps time or history will do it. But if there were a novelist who, for whatever reason, wrote works standing with the wall, of what value would such works be?
「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」ということです。
そうなんです。その壁がいくら正しく、卵が正しくないとしても、私は卵サイドに立ちます。他の誰かが、何が正しく、正しくないかを決めることになるでしょう。おそらく時や歴史というものが。しかし、もしどのような理由であれ、壁側に立って作品を書く小説家がいたら、その作品にいかなる価値を見い出せるのでしょうか?
===================================
⇒
善悪とは、究極的には誰が決めるのだろうか。道徳?倫理?法律?習慣?・・・・無数の基準がある。
そしてそれは時代や歴史にさらに影響をうける可変的なもの。
今日の正しいことは、法律が変われば明日に正しくないことになるかもしれない。
戦争で殺人が肯定されることと同じだろう。
村上春樹は、ここではまず正しさや善悪の議論は置いときましょうと言っている。
善悪の判断基準はさておき、現実世界では結果的に<強者と弱者>というものが生まれてしまう。
村上春樹は小説家なので、<強者と弱者>とは表現せず、あえて<壁と卵>というものに変換させて語る。
これは、<強者と弱者>に対する、僕らの自意識や固定観念を取り払うための前準備だとも言える。
===================================
What is the meaning of this metaphor? In some cases, it is all too simple and clear. Bombers and tanks and rockets and white phosphorus shells are that high wall. The eggs are the unarmed civilians who are crushed and burned and shot by them. This is one meaning of the metaphor.
この暗喩が何を意味するのでしょうか?いくつかの場合、それはあまりに単純で明白です。爆弾、戦車、ロケット弾、白リン弾は高い壁です。これらによって押しつぶされ、焼かれ、銃撃を受ける非武装の市民たちが卵です。これがこの暗喩の一つの解釈です。
===================================
⇒
<壁と卵>を表層的に解釈すると、
「はいはい。壁と卵って、国家権力で行われる戦争と、無力な市民のことね。つまり、反戦をかっこつけて言ってるだけね。平和が一番ってことね。基本的人権!戦争反対!世界平和!って記事に書いとけばいいんでしょ。」
と安易に解釈してしまう。
マスコミはここだけしか書かない傾向にあって、僕らもここしか読めない傾向にあって、それだけで村上春樹の発言が終わりになってしまう傾向にある。
実際、わしも普通に仕事をして、生活して、テレビ見て・・の日常の生活では、マスコミが流す表層的な報道までしか到達できなかった。
実は、村上春樹はそうとしか書けなくなる傾向にある報道やマスコミ「システム」自体をも批判しているかもしれない。
===================================
But this is not all. It carries a deeper meaning. Think of it this way. Each of us is, more or less, an egg. Each of us is a unique, irreplaceable soul enclosed in a fragile shell. This is true of me, and it is true of each of you. And each of us, to a greater or lesser degree, is confronting a high, solid wall. The wall has a name: it is “The System.” The System is supposed to protect us, but sometimes it takes on a life of its own, and then it begins to kill us and cause us to kill others--coldly, efficiently, systematically.
しかし、それだけではありません。もっと深い意味があります。こう考えてください。私たちは皆、多かれ少なかれ、卵なのです。私たちはそれぞれ、壊れやすい殻の中に入った個性的でかけがえのない心を持っているのです。わたしもそうですし、皆さんもそうなのです。そして、私たちは皆、程度の差こそあれ、高く、堅固な壁に直面しています。その壁の名前は「システム」です。「システム」は私たちを守る存在と思われていますが、時に自己増殖し、私たちを殺し、さらに私たちに他者を冷酷かつ効果的、組織的に殺させ始めるのです。
===================================
⇒
村上春樹ははっきり主張している。
戦争の真っただ中にあるエルサレムで、弱い卵である自分が、戦争やマスコミや国家や宗教・・・のように高くそびえる壁の前で、その壁(「システム」)自体を意識しないといけないと主張する。
僕らは、そういう「システム」の中に生きている。
僕らは、そういう高い壁の「システム」にいる、弱い卵の存在である。
僕ら人間が、そういう壁(「システム」)と違うのは、僕らはそれぞれが唯一無二(unique・irreplaceable)の存在であり、色んな欲望や自意識や都合や集団の論理に影響されて『私が私である』壊れやすい殻の中にいて(enclosed in a fragile shell)、それいで『魂・たましい・心』(soul)を持つ存在なのであると!
自分の中で、壊れやすい卵とは、ちょい前に書いた『私が私であること』(2009/02/19)を想起させる暗喩表現に思えた。
===================================
I have only one reason to write novels, and that is to bring the dignity of the individual soul to the surface and shine a light upon it. The purpose of a story is to sound an alarm, to keep a light trained on the System in order to prevent it from tangling our souls in its web and demeaning them. I truly believe it is the novelist’s job to keep trying to clarify the uniqueness of each individual soul by writing stories--stories of life and death, stories of love, stories that make people cry and quake with fear and shake with laughter. This is why we go on, day after day, concocting fictions with utter seriousness.
私が小説を書く目的はただ一つです。個々の精神が持つ威厳さを表出し、それに光を当てることです。小説を書く目的は、「システム」の網の目に私たちの魂がからめ捕られ、傷つけられることを防ぐために、「システム」に対する警戒警報を鳴らし、注意を向けさせることです。私は、生死を扱った物語、愛の物語、人を泣かせ、怖がらせ、笑わせる物語などの小説を書くことで、個々の精神の個性を明確にすることが小説家の仕事であると心から信じています。というわけで、私たちは日々、本当に真剣に作り話を紡ぎ上げていくのです。
===================================
⇒
村上春樹は、あえて「システム」の善悪は問わないように注意を払いながら表現している。
なぜなら、『善悪』は、時代や国や文化や・・・色々なもので変化しうる固定化されたものではないから。そういう善悪を、固定化されたものとして基準に据えること自体が、かなり危険であることを本能的に経験的に知っているからだろう。
そして、「システム」の善悪よりも、「システム」により僕らの『魂・たましい・心』(soul)が奪われることに注意せよと喚起を促している。
暗喩である高い壁=「システム」(国家、経済、宗教、マスコミ・・・・・)と対峙する時、一番の判断の基準になる拠り所は、僕らの『魂・たましい・心』(soul)である。
それは、誰かが意図を持ってつくった『善悪』の基準よりも、自分がより信頼できるものなのかもしれない。
そういう意味で、僕らの寄る辺・基準というものは、自分の中に既に存在していると言える。
ただ、それが何なのかは、壊れやすい殻をまとった卵である自分を、じっくり見つめて考えないといけない。
===================================
He was praying for all the people who died, he said, both ally and enemy alike. Staring at his back as he knelt at the altar, I seemed to feel the shadow of death hovering around him.
父は、敵であろうが味方であろうが区別なく、「すべて」の戦死者のために祈っているとのことでした。父が仏壇の前で正座している輝くような後ろ姿を見たとき、父の周りに死の影を感じたような気がしました。
===================================
===================================
My father died, and with him he took his memories, memories that I can never know. But the presence of death that lurked about him remains in my own memory. It is one of the few things I carry on from him, and one of the most important.
父は亡くなりました。父は私が決して知り得ない記憶も一緒に持っていってしまいました。しかし、父の周辺に潜んでいた死という存在が記憶に残っています。以上のことは父のことでわずかにお話しできることですが、最も重要なことの一つです。
===================================
⇒
ここで、父の死の話が挿入されていた。
村上春樹の父も死んだ。父が持っていた記憶も消えた。
だが、父の周辺に潜んでいた死という存在( the presence of death that lurked about him)は、村上春樹の記憶として伝承され、村上春樹が生きている限りは変容しながらも生き続ける。
そして、その話を聞いた「わたし」も、このブログを読んでいる「あなた」にも、その記憶は無意識下に伝えられ、別の層に沈殿しながら、変容して生き続けていく。
村上春樹の父の祈りの対象は、敵とか味方を越えて、死んでいった全ての人に向けられていた。
===================================
I have only one thing I hope to convey to you today. We are all human beings, individuals transcending nationality and race and religion, and we are all fragile eggs faced with a solid wall called The System. To all appearances, we have no hope of winning. The wall is too high, too strong--and too cold. If we have any hope of victory at all, it will have to come from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others’ souls and from our believing in the warmth we gain by joining souls together.
Take a moment to think about this. Each of us possesses a tangible, living soul. The System has no such thing. We must not allow the System to exploit us. We must not allow the System to take on a life of its own. The System did not make us: we made the System.
That is all I have to say to you.
今日、皆さんにお話ししたいことは一つだけです。私たちは、国籍、人種を超越した人間であり、個々の存在なのです。「システム」と言われる堅固な壁に直面している壊れやすい卵なのです。どこからみても、勝ち目はみえてきません。壁はあまりに高く、強固で、冷たい存在です。もし、私たちに勝利への希望がみえることがあるとしたら、私たち自身や他者の独自性やかけがえのなさを、さらに魂を互いに交わらせることで得ることのできる温かみを強く信じることから生じるものでなければならないでしょう。
このことを考えてみてください。私たちは皆、実際の、生きた精神を持っているのです。「システム」はそういったものではありません。「システム」がわれわれを食い物にすることを許してはいけません。「システム」に自己増殖を許してはなりません。「システム」が私たちをつくったのではなく、私たちが「システム」をつくったのです。
これが、私がお話ししたいすべてです。
===================================
⇒
村上春樹は再度語った。
僕ら全員が卵であると。弱い卵であり、常に壊れやすい。
ぶつけられて壊れてしまう壁は、
広く言えば、時代や国家や社会や世界。
狭く言えば、職場の論理や世間。
色々な壁(「システム」)を前に、途方もなく何もできず、ただ壊れてしまうだけの存在かもしれない。
「私が私である」ことが困難であるかもしれない。
ただ、僕らがそうして途方に暮れた時、
「他者の独自性やかけがえのなさを、さらに魂を互いに交わらせることで得ることのできる温かみを強く信じる」
(it will have to come from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others’ souls and from our believing in the warmth we gain by joining souls together.)
ことが、全ての出発点になるのではないかと。
そういう温かみを持つ心を持つ点で、僕らは壁「システム」と違う、唯一無二のユニークな存在であるのではないかと。
言葉でまとめると、単純かもしれないけれど・・。
マスコミも、資本主義という「システム」に支えられ、内容の質よりも、売れないといけない、広く受け入れられないといけない、批判が出ないようにつくらないといけない、偉い政治家や実業家の顔色をうかがわないといけない・・・そんな複雑な「システム」で成立しているんだろう。
でも、その「システム」を作っている個人個人は、壊れやすい卵である生きた心(living soul)を持った人間であって、決して心ない「システム」から自動的に「システム」が生まれてくるわけではないと思う。
■僕らは「高い壁」でもあり、「卵」でもある
さらに言えば、僕らは、そういう高い壁(「システム」)と、卵の存在を、常に往復しながら振幅運動しながら生きている存在でもある。
いつのまにか自分が高い壁(「システム」)の側にいるとき、常に弱く壊れやすい卵、心を持つ卵の存在であるはずだった自分自身をも意識しないといけないのかもしれない。
村上春樹は、むしろ、卵側につくように意識しなければ、システムの中に埋没して心を失ってしまう(「忙しい」という漢字の語感でもある)と言っているようにも聞こえてくる。
村上春樹が戦争中のエルサレムで言っているのは、単なる反戦だけに限定されたものではない。
村上春樹は殺されるかもしれないリスクを冒してスピーチを行った。
そんな彼の覚悟や思いを、ちゃんと受け取りたい。
僕らは弱い卵である。高い壁の前では無力な存在であるが、『魂・たましい・心』(soul)を持つ点で、高い壁とは異なる。
ただ、弱い卵であるはずの自分自身が、知らないうちに色んな高い壁(「システム」)の中に安住して、そのシステムの中から別の弱い卵を壊しているかもしれない。
そんな「卵」でありながら、「高い壁」にもなりうる僕らへのメッセージでもあるとも、感じられたのです。
村上春樹「エルサレム賞」授賞式講演、やっと全文を読むことができて、すごく感動した。
示唆に富むスピーチで、素晴らしいと思った。
何度も読み返すと、自分の心が震えた。
一度読んだだけでは、自分にはわからなかった。
日本の報道では、「村上春樹さんがエルサレムで反戦を主張した。イスラエル政府の爆撃攻撃を批判した。」というような数十秒の報道にとどまっていた。
彼の発言が正確に届くのは、その場にいた人々だけである。それは村上春樹の熱気や表情や間の取り方・・全てを感じ、同じ時間と空間を共有できる一期一会のものだけが共有できるかけがえのないもの。
村上春樹の言葉は、日本の報道「システム」にとって都合がいいものとして切り張られ加工される。
報道「システム」は、経済「システム」、政治「システム」・・・色々な「システム」同士が、ガチガチに固定化した「システム」同士で依存して、ベッタリはがれなくなっている。
そういう、高く堅固な壁である「システム」の前で、ぶつかって壊れる卵があるとしたら、村上春樹は常に卵側に立つと言った。
村上春樹の発言は示唆に富み、かなり重要だと感じた。
ココで日本語訳全文、ココで英語全文を読めるので是非読んでみてほしい。
以下に、47NEWSから抜粋して引用。
■村上春樹「エルサレム賞」受賞スピーチより抜粋
===================================
In most cases, it is virtually impossible to grasp a truth in its original form and depict it accurately. This is why we try to grab its tail by luring the truth from its hiding place, transferring it to a fictional location, and replacing it with a fictional form.
多くの場合、真実の本来の姿を把握し、正確に表現することは事実上不可能です。だからこそ、私たちは真実を隠れた場所からおびき出し、架空の場所へと運び、小説の形に置き換えるのです。
===================================
⇒
真実とは何か、事実とは何か。
物事は、百の視点があれば百の解釈が存在する。
それは、百人の人がいれば、百の自意識があり、人間自体が自意識を中心に世界を自由に解釈しながら生きているから、そこからは逃れられない。
自意識過剰で、自分の都合に応じて世界を解釈しようとすれば、真実や事実は無限に発散していく。
ただ、できる限り自意識を無くそうと努力して世界をとらえようとすれば、真実や事実はある一点に収束していくかもしれない。
真実や事実というものは、そんなあやふやなものだからこそ、村上春樹は架空の隠れた場所で小説という物語を書くという。
===================================
“Between a high, solid wall and an egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg.”
Yes, no matter how right the wall may be and how wrong the egg, I will stand with the egg. Someone else will have to decide what is right and what is wrong; perhaps time or history will do it. But if there were a novelist who, for whatever reason, wrote works standing with the wall, of what value would such works be?
「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」ということです。
そうなんです。その壁がいくら正しく、卵が正しくないとしても、私は卵サイドに立ちます。他の誰かが、何が正しく、正しくないかを決めることになるでしょう。おそらく時や歴史というものが。しかし、もしどのような理由であれ、壁側に立って作品を書く小説家がいたら、その作品にいかなる価値を見い出せるのでしょうか?
===================================
⇒
善悪とは、究極的には誰が決めるのだろうか。道徳?倫理?法律?習慣?・・・・無数の基準がある。
そしてそれは時代や歴史にさらに影響をうける可変的なもの。
今日の正しいことは、法律が変われば明日に正しくないことになるかもしれない。
戦争で殺人が肯定されることと同じだろう。
村上春樹は、ここではまず正しさや善悪の議論は置いときましょうと言っている。
善悪の判断基準はさておき、現実世界では結果的に<強者と弱者>というものが生まれてしまう。
村上春樹は小説家なので、<強者と弱者>とは表現せず、あえて<壁と卵>というものに変換させて語る。
これは、<強者と弱者>に対する、僕らの自意識や固定観念を取り払うための前準備だとも言える。
===================================
What is the meaning of this metaphor? In some cases, it is all too simple and clear. Bombers and tanks and rockets and white phosphorus shells are that high wall. The eggs are the unarmed civilians who are crushed and burned and shot by them. This is one meaning of the metaphor.
この暗喩が何を意味するのでしょうか?いくつかの場合、それはあまりに単純で明白です。爆弾、戦車、ロケット弾、白リン弾は高い壁です。これらによって押しつぶされ、焼かれ、銃撃を受ける非武装の市民たちが卵です。これがこの暗喩の一つの解釈です。
===================================
⇒
<壁と卵>を表層的に解釈すると、
「はいはい。壁と卵って、国家権力で行われる戦争と、無力な市民のことね。つまり、反戦をかっこつけて言ってるだけね。平和が一番ってことね。基本的人権!戦争反対!世界平和!って記事に書いとけばいいんでしょ。」
と安易に解釈してしまう。
マスコミはここだけしか書かない傾向にあって、僕らもここしか読めない傾向にあって、それだけで村上春樹の発言が終わりになってしまう傾向にある。
実際、わしも普通に仕事をして、生活して、テレビ見て・・の日常の生活では、マスコミが流す表層的な報道までしか到達できなかった。
実は、村上春樹はそうとしか書けなくなる傾向にある報道やマスコミ「システム」自体をも批判しているかもしれない。
===================================
But this is not all. It carries a deeper meaning. Think of it this way. Each of us is, more or less, an egg. Each of us is a unique, irreplaceable soul enclosed in a fragile shell. This is true of me, and it is true of each of you. And each of us, to a greater or lesser degree, is confronting a high, solid wall. The wall has a name: it is “The System.” The System is supposed to protect us, but sometimes it takes on a life of its own, and then it begins to kill us and cause us to kill others--coldly, efficiently, systematically.
しかし、それだけではありません。もっと深い意味があります。こう考えてください。私たちは皆、多かれ少なかれ、卵なのです。私たちはそれぞれ、壊れやすい殻の中に入った個性的でかけがえのない心を持っているのです。わたしもそうですし、皆さんもそうなのです。そして、私たちは皆、程度の差こそあれ、高く、堅固な壁に直面しています。その壁の名前は「システム」です。「システム」は私たちを守る存在と思われていますが、時に自己増殖し、私たちを殺し、さらに私たちに他者を冷酷かつ効果的、組織的に殺させ始めるのです。
===================================
⇒
村上春樹ははっきり主張している。
戦争の真っただ中にあるエルサレムで、弱い卵である自分が、戦争やマスコミや国家や宗教・・・のように高くそびえる壁の前で、その壁(「システム」)自体を意識しないといけないと主張する。
僕らは、そういう「システム」の中に生きている。
僕らは、そういう高い壁の「システム」にいる、弱い卵の存在である。
僕ら人間が、そういう壁(「システム」)と違うのは、僕らはそれぞれが唯一無二(unique・irreplaceable)の存在であり、色んな欲望や自意識や都合や集団の論理に影響されて『私が私である』壊れやすい殻の中にいて(enclosed in a fragile shell)、それいで『魂・たましい・心』(soul)を持つ存在なのであると!
自分の中で、壊れやすい卵とは、ちょい前に書いた『私が私であること』(2009/02/19)を想起させる暗喩表現に思えた。
===================================
I have only one reason to write novels, and that is to bring the dignity of the individual soul to the surface and shine a light upon it. The purpose of a story is to sound an alarm, to keep a light trained on the System in order to prevent it from tangling our souls in its web and demeaning them. I truly believe it is the novelist’s job to keep trying to clarify the uniqueness of each individual soul by writing stories--stories of life and death, stories of love, stories that make people cry and quake with fear and shake with laughter. This is why we go on, day after day, concocting fictions with utter seriousness.
私が小説を書く目的はただ一つです。個々の精神が持つ威厳さを表出し、それに光を当てることです。小説を書く目的は、「システム」の網の目に私たちの魂がからめ捕られ、傷つけられることを防ぐために、「システム」に対する警戒警報を鳴らし、注意を向けさせることです。私は、生死を扱った物語、愛の物語、人を泣かせ、怖がらせ、笑わせる物語などの小説を書くことで、個々の精神の個性を明確にすることが小説家の仕事であると心から信じています。というわけで、私たちは日々、本当に真剣に作り話を紡ぎ上げていくのです。
===================================
⇒
村上春樹は、あえて「システム」の善悪は問わないように注意を払いながら表現している。
なぜなら、『善悪』は、時代や国や文化や・・・色々なもので変化しうる固定化されたものではないから。そういう善悪を、固定化されたものとして基準に据えること自体が、かなり危険であることを本能的に経験的に知っているからだろう。
そして、「システム」の善悪よりも、「システム」により僕らの『魂・たましい・心』(soul)が奪われることに注意せよと喚起を促している。
暗喩である高い壁=「システム」(国家、経済、宗教、マスコミ・・・・・)と対峙する時、一番の判断の基準になる拠り所は、僕らの『魂・たましい・心』(soul)である。
それは、誰かが意図を持ってつくった『善悪』の基準よりも、自分がより信頼できるものなのかもしれない。
そういう意味で、僕らの寄る辺・基準というものは、自分の中に既に存在していると言える。
ただ、それが何なのかは、壊れやすい殻をまとった卵である自分を、じっくり見つめて考えないといけない。
===================================
He was praying for all the people who died, he said, both ally and enemy alike. Staring at his back as he knelt at the altar, I seemed to feel the shadow of death hovering around him.
父は、敵であろうが味方であろうが区別なく、「すべて」の戦死者のために祈っているとのことでした。父が仏壇の前で正座している輝くような後ろ姿を見たとき、父の周りに死の影を感じたような気がしました。
===================================
===================================
My father died, and with him he took his memories, memories that I can never know. But the presence of death that lurked about him remains in my own memory. It is one of the few things I carry on from him, and one of the most important.
父は亡くなりました。父は私が決して知り得ない記憶も一緒に持っていってしまいました。しかし、父の周辺に潜んでいた死という存在が記憶に残っています。以上のことは父のことでわずかにお話しできることですが、最も重要なことの一つです。
===================================
⇒
ここで、父の死の話が挿入されていた。
村上春樹の父も死んだ。父が持っていた記憶も消えた。
だが、父の周辺に潜んでいた死という存在( the presence of death that lurked about him)は、村上春樹の記憶として伝承され、村上春樹が生きている限りは変容しながらも生き続ける。
そして、その話を聞いた「わたし」も、このブログを読んでいる「あなた」にも、その記憶は無意識下に伝えられ、別の層に沈殿しながら、変容して生き続けていく。
村上春樹の父の祈りの対象は、敵とか味方を越えて、死んでいった全ての人に向けられていた。
===================================
I have only one thing I hope to convey to you today. We are all human beings, individuals transcending nationality and race and religion, and we are all fragile eggs faced with a solid wall called The System. To all appearances, we have no hope of winning. The wall is too high, too strong--and too cold. If we have any hope of victory at all, it will have to come from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others’ souls and from our believing in the warmth we gain by joining souls together.
Take a moment to think about this. Each of us possesses a tangible, living soul. The System has no such thing. We must not allow the System to exploit us. We must not allow the System to take on a life of its own. The System did not make us: we made the System.
That is all I have to say to you.
今日、皆さんにお話ししたいことは一つだけです。私たちは、国籍、人種を超越した人間であり、個々の存在なのです。「システム」と言われる堅固な壁に直面している壊れやすい卵なのです。どこからみても、勝ち目はみえてきません。壁はあまりに高く、強固で、冷たい存在です。もし、私たちに勝利への希望がみえることがあるとしたら、私たち自身や他者の独自性やかけがえのなさを、さらに魂を互いに交わらせることで得ることのできる温かみを強く信じることから生じるものでなければならないでしょう。
このことを考えてみてください。私たちは皆、実際の、生きた精神を持っているのです。「システム」はそういったものではありません。「システム」がわれわれを食い物にすることを許してはいけません。「システム」に自己増殖を許してはなりません。「システム」が私たちをつくったのではなく、私たちが「システム」をつくったのです。
これが、私がお話ししたいすべてです。
===================================
⇒
村上春樹は再度語った。
僕ら全員が卵であると。弱い卵であり、常に壊れやすい。
ぶつけられて壊れてしまう壁は、
広く言えば、時代や国家や社会や世界。
狭く言えば、職場の論理や世間。
色々な壁(「システム」)を前に、途方もなく何もできず、ただ壊れてしまうだけの存在かもしれない。
「私が私である」ことが困難であるかもしれない。
ただ、僕らがそうして途方に暮れた時、
「他者の独自性やかけがえのなさを、さらに魂を互いに交わらせることで得ることのできる温かみを強く信じる」
(it will have to come from our believing in the utter uniqueness and irreplaceability of our own and others’ souls and from our believing in the warmth we gain by joining souls together.)
ことが、全ての出発点になるのではないかと。
そういう温かみを持つ心を持つ点で、僕らは壁「システム」と違う、唯一無二のユニークな存在であるのではないかと。
言葉でまとめると、単純かもしれないけれど・・。
マスコミも、資本主義という「システム」に支えられ、内容の質よりも、売れないといけない、広く受け入れられないといけない、批判が出ないようにつくらないといけない、偉い政治家や実業家の顔色をうかがわないといけない・・・そんな複雑な「システム」で成立しているんだろう。
でも、その「システム」を作っている個人個人は、壊れやすい卵である生きた心(living soul)を持った人間であって、決して心ない「システム」から自動的に「システム」が生まれてくるわけではないと思う。
■僕らは「高い壁」でもあり、「卵」でもある
さらに言えば、僕らは、そういう高い壁(「システム」)と、卵の存在を、常に往復しながら振幅運動しながら生きている存在でもある。
いつのまにか自分が高い壁(「システム」)の側にいるとき、常に弱く壊れやすい卵、心を持つ卵の存在であるはずだった自分自身をも意識しないといけないのかもしれない。
村上春樹は、むしろ、卵側につくように意識しなければ、システムの中に埋没して心を失ってしまう(「忙しい」という漢字の語感でもある)と言っているようにも聞こえてくる。
村上春樹が戦争中のエルサレムで言っているのは、単なる反戦だけに限定されたものではない。
村上春樹は殺されるかもしれないリスクを冒してスピーチを行った。
そんな彼の覚悟や思いを、ちゃんと受け取りたい。
僕らは弱い卵である。高い壁の前では無力な存在であるが、『魂・たましい・心』(soul)を持つ点で、高い壁とは異なる。
ただ、弱い卵であるはずの自分自身が、知らないうちに色んな高い壁(「システム」)の中に安住して、そのシステムの中から別の弱い卵を壊しているかもしれない。
そんな「卵」でありながら、「高い壁」にもなりうる僕らへのメッセージでもあるとも、感じられたのです。










読んだ後に、ああ、また自分が今少し変わろうとしているという感情の動きがああった。
そして、改めて、村上さん志高いなあって思った。ノーベル文学賞の候補にもあがっているけれど、人の幸福感とか、自我だとか、抽象的な難しいところを直接的ではなく、青春や人生にとけ込ませて描こうとしていて、いつもすごいと思う。
国を超えて読まれているのも、まさに彼が今回言っている共通性があるからだろうね。
さて、今回のメッセージでいえば、システムとは、本当は弱い卵を守るためや、効率化や合理化をしていくために、進む道を囲って示してくれているものだったはず。人類が歴史を経て得た、知恵。
だから、そのシステムは、その組織を維持するために卵たちを教育して、「あるべき姿」を示しマニュアル化したりもする。
システムに従っていれば幸せがある、逆らわなければ、うまくやっていける、日本でもそんな時代もかつてはあったし、いくつかの共産主義国家では、今もそう信じているところもある。
それでも、これだけボーダレスになりいろんな情報が飛び交うことで、何か違うぞと思い始めた人、外に飛び出したいと思う人がいろんなところで壁にぶつかりはじめている。
また、組織の力学というシステム維持装置が、教育という方法で卵たちを使って外側のシステムを攻撃したりもする。
システムをメンテナンスしている人にとっては、その方が好都合だから。
このシステムには、いなば君が書いているように、国家、地域社会、会社、家庭と社会学的な区分でいっても様々。
確かに、多くの場合、システムは文明の英知であり、利点が多い。
もしシステムがなければ、争いは更に増えるかも知れないし、帝国主義をはじめとする一部権力の支配が続いたり、個々人が好き勝手やり全体としての非効率を招くだろう。
しかし、一方で、そのシステムの論理に思考を預けることがいかに人をダメにするかも事実。
特に、宗教や民族などの理屈じゃないと思われるシステムが、もっとも壁としては高いような気がする。
会社は、淘汰という波にさらされ、変わらなければ消えていく運命にある。でも、宗教や民族のシステムは、根が深い。
********
私たちは皆、実際の、生きた精神を持っているのです。「システム」はそういったものではありません。「システム」がわれわれを食い物にすることを許してはいけません。「システム」に自己増殖を許してはなりません。「システム」が私たちをつくったのではなく、私たちが「システム」をつくったのです。
**********
この部分は、メッセージが強烈だね。
組織の論理に乗っかっている、あらゆるものへの問いかけが、柔らかいながらも強い。
春樹さんの文章と、いなば君の感想を読んで、脆弱な卵が、生卵のままフレッシュで生きていくために、「私が私であること」、それは「自分の頭で考え、思考停止しないこと」、「表現し、発信できること」そんな能力を伸ばしていきたいと感じ、こころが動いた。
勇気が出ました。非常感謝。
お恥ずかしい、全文初めて読んだ。
ホント、ニュースで編集された短いスピーチから受ける印象とは全然違った。
広く現代社会批判になってると思う。
…その部分を伝えられないテレビは、
やはり資本主義や大メディアという
ここで村上氏の批判する「システム」
の最たるものだからなのか!?
2つ、重要なメッセージを受けたと思う。
ひとつは、〈個〉の尊重。
ふたつめは、その批判する「システム」自体を作っているのも私たち自身だと言うこと。
魂というぷにょぷにょのかけがえない黄身も脆い卵の殻のようなものでかろうじて存在してるにすぎない。
そしてその前では、社会や組織やグローバル資本主義や…、それはまさしく壁のごとく強固で高くそびえ立つ。ぶつかればひとたまりもない…。
卵の比喩に乗るならば、
ぼくは、そんな脆弱な卵をなんとか割れないように工夫する、あの「卵パック」のようなものが何かつくれないかと思う。
例えば、まちや地域や、家族、仲間…。
そうすれば、壁はもしかしたら台風や津波から僕らを守ってくれる防波堤のような存在とポジティブに捉えられる。
問題は、そうした構造を自覚しないこと。自覚せず、壁にぶつかることを強いるようなもろもろの圧力。
昔、糸井さんが、「夢は小さい方がいい」って言っていたことがある。そういうことかもしれない。
大きな夢へ煽り、システムの壁へ突っ込むことを我々は強いられてはいないか?
ぼくは「距離をとれること」ってことが大切だと思う。
山崎正和さんなら、〈不即不離=つかずはなれず〉の関係っていうだろうし、
糸井さんなら、〈ほぼ〉とか言うのかな?
壁はある。それは、僕らが自然から自らの身を守るためにつくったものだ。しかし、今や、その壁/システム=社会や会社や組織や資本主義や…は、所与の自然物のように思われ、乗り遅れると人間失格…みたいなものになってしまう…
別に書いた中の
http://blog.livedoor.jp/daiyoji/archives/65175745.html
広井良典さんつながりで
内橋克人さんの『浪費なき成長』を読む。
そこには、Food,Energy,Careを可能な限り巨大システムに依存せず自ら顔の見える範囲内で自給していく「FEC自給圏」という構想が描かれている。それは「卵パック」のようなものなのかもしれない。
『気流の鳴る音』などの著作から、しばしば共同体主義者だと思われる見田宗介さんだが、かつて橋爪大三郎さんに、「見田さんは近代主義者ですよね」と評され、「よく分かってくれました」と応えていたのを思い出す。
徹底して個人主義的であろうとすればするほど、その条件に自覚的にならざるを得ない。村上春樹さんのスピーチからは、同様の決意のようなものを感じた。新作長編楽しみ!
http://www.shinchosha.co.jp/murakami/
『システムとは、本当は弱い卵を守るためや、効率化や合理化をしていくために、進む道を囲って示してくれているものだったはず。人類が歴史を経て得た、知恵。』
→
確かに、わしの文章ではその辺の前提はあんま書いてなかったね。今気づいた。
でも、文字数が1万文字に達してて、このブログだと追加補足できないのよね。
だから、このコメント欄のShin.K氏のコメントで補足になる。ありがと!
確かに、「システム」ってのは、本来は僕らの心を邪魔したり、僕らを不自由にする存在ではないはずだよね。「システム」がなければ、欲望丸出しで、暴力・盗難・殺戮・・・の嵐になるのかもしれない。そういう荒廃した世界では、ある秩序がおのずから生まれてくるのだろうか。
それが、「システム」といわれる国家や警察や法律や・・・そういうもの?
でも、ふと考えると、アマゾン奥地とかアフリカとか、日本で言えば縄文時代とか。
そういう原始的な生活している人たちが、必ずしも僕らと同じ文明をたどっているわけではないのも現実に並行して存在しているわけだし・・・。
そういう意味では、日本もアメリカも、原始社会よりも「システム」自体が肥大してきているから、そこを村上春樹は指摘しているのかなぁ。
国や文化が変われば、「システム」は全然違うし・・・・。この辺は比較文化論とかになる?
『システムに従っていれば幸せがある、逆らわなければ、うまくやっていける』
→これは、安住の世界のように思えるんだけど、現実的にはShin.K氏が指摘するような「思考停止」状態に陥りやすい。
そういう点では、常に幸せとは何かを思考し続けること、そういう車輪がグルグル回っている間が、実は「幸せ」な状態の本質の近くにいるのかもしれんね。
『組織の力学というシステム維持装置が、教育という方法で卵たちを使って外側のシステムを攻撃したりもする』
→組織の力学は、組織を維持するために力学が働くから、そこで回路が閉じちゃうんだよね。
そういう回路が閉じちゃう状態、世界に開かれていない状態って、内部の循環が悪くなって腐敗しちゃうことが多い。これは歴史も常に証明しているなぁ。
『宗教や民族などの理屈じゃないと思われるシステムが、もっとも壁としては高いような気がする。』
→理屈や論理って、普遍性を持つにはすごくいい手段になるんだけど、実際僕らが理屈や理論だけで行動しているわけではなく、そのときの感情や情動、そんなものに大きく支配されている現実を考えるとそう思える。
竹内整一先生の『「はかなさ」と日本人』を読んだ時も思ったけど、日本人の無常感とか、美意識とか、いかに自分にネッチリこびりついて、ほとんどアイデンティティーのようになっているかに意識させられた!これも、他の文化の人が見れば、「日本人の美意識って、理屈じゃ全然わからんなー」と思われちゃうんだろうしね。 実際、自分でも無常感とか、儚さへの美意識とか、理屈じゃよくわからんもん。
『春樹さんの文章と、いなば君の感想を読んで、脆弱な卵が、生卵のままフレッシュで生きていくために、「私が私であること」、それは「自分の頭で考え、思考停止しないこと」、「表現し、発信できること」そんな能力を伸ばしていきたいと感じ、こころが動いた。』
→同感!
自分が書いた卑近なブログ内容を引き合いに出すと、「私が私であること」っていうのは、弱く儚い卵である存在である「私」。時には色んなシステムの中にいることで、「虎の威を借るキツネ」状態になっている「私」。そういう色んな境界を揺れ動きながら存在している「私」が、どの振幅の揺れ幅までは「私」でいられるのか。弱くありながら同時に強くあり、卵でありながら同時に壁であれるのか、そういう自分の奥行とか空間のサイズを瞬間瞬間に認識していくことなのかもしれないなぁ。
この辺、なんか西田幾多郎とか、その辺をもう一回勉強したい気がしてきた。
いづれにせよ、Shin.k氏のコメントのおかげで、わしもまた色々考えとか理解が深まってきた。ありがとう!
>>>>>>>>>>>>>>>Is
『2つ、重要なメッセージを受けたと思う。
ひとつは、〈個〉の尊重。
ふたつめは、その批判する「システム」自体を作っているのも私たち自身だと言うこと。』
→
〈個〉の尊重とは、わしがブログで書いた言葉でいえば、
「私」は「私」であるし、「あなた」は「あなた」であってほしい
ということなのかも。つまりは同語反復の世界で、《ありのまま》とかそんな言葉になっちゃうのかな。
『ぼくは、そんな脆弱な卵をなんとか割れないように工夫する、あの「卵パック」のようなものが何かつくれないかと思う。例えば、まちや地域や、家族、仲間…。』
→
これは、村上春樹にかぶせた表現で、すごくイイね!
確かに、卵って1個1個で見かけるよりも、卵パックに入ってるものね!
個々として尊重される「個人」同士が、「自」と「他」が、どのようなつながりをもつのか。
そのひとつは、こういうブログのコメント欄の関係性も同じかもしれない。
ネット世界は時間とか空間の従来の意識を、かなり変えたし、新しい「自」と「他」の塩梅が、そこには存在すると思うし。
『大きな夢へ煽り、システムの壁へ突っ込むことを我々は強いられてはいないか?』
→
わしも、学校教師がいうところの「夢を持たないといけない」というのは、いつも壮大すぎて、距離感感じてたなぁ。その時その時に、自分のサイズっていうのがあって、自分のサイズを超える巨大な夢っていうのは、徐徐に自分を失うことにつながるからね。背伸びしたりとか無理したりとか、私が私でなくなるきっかけになりうるもの。
『Is氏:距離をとれること』
『山崎正和さん:〈不即不離=つかずはなれず〉の関係』
『糸井さん:〈ほぼ〉』
→
距離。「自」と「他」のいい塩梅の件だよね。
これは確かに永遠のテーマなのかも。
人間が自分一人で生きていくわけではない以上、その距離感っていうのは引力と斥力との絶妙なバランスで成立するわけだし。微妙に異なりながら、でも微妙に同期しながら、でも微妙にずれながら、でも微妙に重なりあっている距離感。そういうのがいい塩梅なのかなぁ。
『今や、その壁/システム=社会や会社や組織や資本主義や…は、所与の自然物のように思われ、乗り遅れると人間失格…みたいなものになってしまう…』
→
そこからはみ出る孤独感っていうのはあるね。特に若い時は、自意識過剰で自意識を作りまくり固めまくっている時期で、裏を返せばそれは自分に自信がないってことなんだろうけど、そういう時期の孤独感っていうのは、自分を見失いやすくなる。それは、弱く壊れやすい卵の比喩とも重なるかもしれんね。
『内橋克人さん:浪費なき成長』
『Food,Energy,Careを可能な限り巨大システムに依存せず自ら顔の見える範囲内で自給していく「FEC自給圏」という構想』
→
こういう概念は、誰が聞いても、大事!って思えるはずなんだけど、実際はなかなか実現しない。それを妨げてるものって何だろう?それが村上春樹が言うところの壁であり、心がない存在である「システム」ってことなんだろうか。
村上春樹さんの新作長編を読む前に、色々事前学習しとかんといかん!
村上作品、そろそろ本腰入れて読んでみようかな。
あ、その前にともこさんから薦められた山本七平とか池澤夏樹とか稲盛和夫さんの本も読まないといかんし。1日が24時間って全然たりないわー。 でも、幸せー!
会社組織のあり方もそうだろうなーと、個人的には思いました。
いくつもの卵が、自ら壁にぶつかっていき「自壊」する様はどんな組織でもあるのでしょうね。
本来あらゆる組織は、卵たる個人を守る、活かすためにあったはずなのですが、いつしか手段と目的が入れ替わる。単純な疎外論で、1000年以上前から指摘されてきた構図なのに、なぜか、現代においてもこの指摘はまだビビッドに見える。
それだけ、卵と壁の対立という構図は根が深い、あるいは人間の心性のあり方に深く関わっているということなのでしょう。
最初に会社の話をしましたが、そういう文脈で言えば、ピータードラッカーみたいな経営戦略の人たちの中にも、この問題意識を中心に据えていた人が多そうですね。
追記)しかしはるきの新作タイトルは「1Q84」ですか・・・ジョージオーエル、読んでみようかな~
http://www.amazon.co.jp/dp/4150400083
やっぱ、想像力とか妄想力を喚起させる作品ってのは、イイ作品の要素の一つだと思うね。
それは、文章がその中だけでこじんまりと完結されてないってことだし。
閉じられていない。開かれている。
しかも、個々人の姿勢や心理状況や年齢や・・いろんなものに応じて相互作用するってことだし。
ああいう風に政治的な場で、政治的な内容を暗に含みながら文学的に表現するってのは、相当にすごいよね。誰にでもできるものではないし、生半可な覚悟ではできないと思う。
色んな嫌がらせ受ける可能性もあるし。
でも、ああいう大人って、子供から見ても素直にかっこいい大人だと思う。
Rym氏が言うように、会社組織のあり方も、そうですよね。
今、このブログにもコメント書きこんでくれるともこさんから、山本七平『日本人と組織』っての借りて読んでるんだけど、この本も面白い!
日本の「会社 カイシャ」と、海外の色んな組織を比較しながら、日本人の組織を論じているのだけど、すごく刺激的!やっぱり自分は日本人なんだなぁと自覚してしまう。
そういう意味でも、会社組織一つ考えても日本と海外では様相が全く異なるんだろうけど、村上春樹が指摘するようなことは、日本の会社や組織にすごくよくあてはまると思ったね。
Shin.K氏も書いていたような、システムは僕らのためにでき始めたはずなのに、徐徐に脱線して違うものへ変質していく。
この辺は観念論的に、頭の中でこねくりまわすより、自分がいる組織や会社を例に考えてみると、色々イイとこも悪いとこも見えてくるし、そういう意味で村上春樹の発言は示唆に富むよね。
Rym氏が言うように、卵と壁の対立は根が深いんでしょうなー。
人類の歴史を見て、農耕文化が始まって、富や財産を貯蓄したり。そういう貯蓄を統合するためにシステムができたり。狩猟文化でもシステムはあったのかな?まあ、集団生活すると、必ずや生成してくるのかなぁ。
村上春樹の新作、「1Q84」なんですね! ジョージオーエルの「1984」ってのは関連あるのかな?わしも読んでみようっと。
最近は課題図書がいっぱいあって24時間じゃ全然足りな過ぎる!テレビも漫画も絵も見たいし!
が、スピーチは興味深く読みました。
正直なところイスラエルとパレスチナの問題は自分が考えているより複雑で、考えても理解できないほど難しいのかもしれないと思っています。
外から見ている自分としてはそれなりに、強く思うことはありますが、自分以外の人間に対しそれを声に出して表現するのはかなりの勇気が必要です。
そういう意味においては村上春樹は勇気があるとも言えますね。
ただ、自分としては、ノーベル賞を拒否したサルトルやフィールズ賞を拒否したグレゴリー・ペレマンなどに魅力を感じてしまいます。
ノーベル賞つながりで、、、ロシア政府からノーベル賞拒否を強要されたパステルナークの原作の映画「ドクトル・ジバゴ」はお勧めです。
この映画は映画館で観るのが最高ですが、今ではそうはいきませんものね。DVDで出ています。
むか~し映画館で観た記憶では確か、映画の途中で画面が広くなり、それに伴ってスクリーンの両端にあるカーテンがス~~~ッと静かに引かれていき画面が広がった様に思います。
静かな感動でした!
美しい風景やシーンもあり、音楽も胸に染み渡ります。
若い時に観たのでその時は理解出来ない部分も多くありましたが、歳を経ていくごとにその内容の深さを知ることになりました。
それくらい、素晴らしい作品です。
余談ですが、ちょっと前にミニ・ロシア語講座を受けたのですが、ロシア語は美しいけれど非常に難しかったです。
講師は女性で好感の持てる人柄でした。
私はバラライカを持ち独身女性限定(ロシアでは)の飾りがいっぱい付いた帽子を被らせてもらい写真を撮りました(笑)
グリゴリー・ペレルマンにとって、現世的な名誉なんて何の価値もないんでしょうね。彼の死生観、聞いてみたい!いろんな思惑にまみれた賞よりも、ホントノコトを追求したいだけだし、よりよく生きることに興味あるんでしょうね。そんな後姿はかっこいい!
ドクトル・ジバゴ・・Amazonの感想見てると更に興味深くなっちゃいましたんで、今度機会あるとき見てみますねー。
ロシア文学って、なかなか特殊なの多いですよね。自分的に、トルストイとドストエフスキーはなんとなく全部読まないといけない気がしてたんで、部屋に買っておいてあります。自分の中でロシア週間が来たら一気に読んでしまおうと思ってます。
ロシアのキリスト教も、ロシア正教会で結構特殊だし、格闘技も強いし(PRIDEのヒョードルとか)、相当に深遠な国ですよねー。自分の中では未知の国です。
卵の周りには本当に色んな材質で、色んな高さで、色んな色や模様のある壁のような気がして。もう、それこそ上から見たら、幾重にも重なる迷路が出来上がっているかもしれないですね。時に壁を倒したり、壊したり、時に壁は壁としてあるまま、ドアを作って道が出来たり・・・でもあまりにも重なりすぎてしまって、どうにもこうにも出口が見えなくなっているかもしれません。Shin.Kさんがブログで言われていたように、(http://blog.livedoor.jp/memo_door/archives/51468448.html)『システムに食いものにされないように』するには、『壁』というものが、必ずしもシンプルに「イイもの」なだけの存在ではないし、逆に「ワルイもの」なだけでもないし、その両面を包括したものなのだという認識をもって、壁に向かって問いを発信し続けるのが大事なのでしょうね。
そういえば、ビル・クリントン氏の昔のスピーチに、こういう一節がありました。
I believe we’re moving into a world where our interdependence with one another will be critical in maintaining our independence as nations and as individuals.
「我々は、国として、個人としての独立を維持するために互いに相互依存の関係でいなくてはいけない時代に(=21世紀)向かっていると思う。」これって、なかなか興味深いなと思って、考えていました。「互いの国レベル、個人レベルで独立や自由を守るために、相互依存が存在する。」壁の存在を認めながら、壁にドアを作って行き来できるようにしているようにも見える。興味深いです。何も壁を壊すという発想に必ずしもいかなくて良いわけですものね。
Isさんが書かれていた「卵パック」↓の発想、とても好きです!(完全にカンリ人さんのブログで、いなばさんブログの内容とクロス&シンクロしてコメントしていますが、)色んな卵パックが作れそうですね。私は英語×日本語の卵パック作りたいですね。素材も色々、色も色々。壁が幾重にも重なっているなら、こちらも色んな卵パックを作ればいいですね!素敵です。色んな卵パックで自分達の存在を温かく守っていけるのは、幸せに感じます。
文字数オーバーで・・・こっちにもどした後で、編集せず。これは一体化で!
「いまさら」は大歓迎!わしが書いていることも、言っていることも、99.99%が「いまさら」ですし。
「そんなの昔の人も言ってたよー。いまさら~。」って突っ込まれるのがほとんど!
何度も引用しているけど、糸井さんの<いまさらの権化。>っていう文章はイイ!
http://www.1101.com/darling_column/2008-11-24.html
==========================
(一部引用)
先にやっていたことに意味があるとすれば、
先にはじめた分だけ、謙虚になっている場合だけだろうよ。
==========================
他ならぬ「わたし」にとって新鮮ならば、
「あたし」にとって動機があるなら、
「ぼく」にはやりたいことなのならば、
気持ちよくはじめてみたらいいんだよなぁ。
==========================
その道の専門家のような顔をしている人だって、
顔や態度ばっかり専門家ってのが多いんだよ。
自分がたいしたものだと思うと、
「いまさら」ができなくなっちゃうんだと思うのよ。
わかってるつもりのことばかりになっちゃうと、
もう風化していくばかりなんだ。
==========================
とまあ、こんな感じで、ここのブログでは「いまさら」大奨励!
今後も、わしも「いまさら」なことで感じたり考えたことを勝手に書き続けて行きますよ。
ともこさんも、「いまさら」昔のTopicとかにコメントくれると嬉しい!
『卵の周りには本当に色んな材質で、色んな高さで、色んな色や模様のある壁のような気がして』
→村上春樹が言うところの「壁」=「システム」ってのは、本当にともこさんが言うように迷路のように、迷宮のように周囲を張り巡らされている!!
もう、システムなしでこの世は何一つ存在していないんじゃなかろうかというほど、蜘蛛の巣のように張り巡らされている。
ふと自意識に気付いた時からそんな生活なものだから、色んな規模のシステム(壁)に囲まれて生きてるなんて、まず想像さえしない。だから、壁の存在に気付くのが第一歩なんでしょうね。
村上春樹は、2歩目として僕らの心の存在にも気付き、壁に対する弱い卵であれと、ひとつの立ち位置を示してくれているように思えますね。
ともこさんが引用していた、ビル・クリントンが『独立を維持するための相互依存の関係性』というのは興味深いですね。その二つは言語的には矛盾しているように聞こえるけど、現実問題としては全然矛盾しないし両立しうる。この辺は言語の限界なのかも。
『何も壁を壊すという発想に必ずしもいかなくて良いわけですものね。』
→これは本当にその通り!
昔の考えってのは、「ぶっ壊せ!」「革命だ!」「旧体制を破壊すれば新しいものが創造されるはずだ!」みたいな発想が多い。それは、ほとんどが最終的には暴力と結びつくことばかり。
その過去を反省すると、今後は「今あるものをそっくりそのまま利用しながら、その関係性やつなげ方で新しいものを模索する」というものであるべきだと思いますね。
適材適所とか、物事や人の組み合わせや配置。そんなのを少し入れ替えるだけで、180度方向性が変わることって多い。これは本当に不思議だと思う。
『私は英語×日本語の卵パック作りたいですね。』
→
弱い存在である卵。その卵をどういう形で結びつけ、関係性を作っていくかということ、それがIs氏の言う卵パックの比喩。
ともこさんが英語とかの言語を利用した卵パック。
Is氏は建築・町つくりのような卵パック。
わしは何かなー。健康とか福祉とか死生観とかの卵パックかなー。
そうやって、各々が違う専門性を生かしながら、相互に呼応していける関係性ってイイよねー。
わしも、自分の専門って、医学の狭い専門の中で閉じることが目的じゃない。正直、医学界での内輪ウケみたいなのは少し飽きてきたところ。専門家だけで自己満足しているだけで、患者さんから遠いなー、実世界から遠いなーって思っちゃうことはよくある。
専門が、その専門の中で閉じずに、それぞれ別の専門の人たちに世界を開いていって、越境していきたいです。そんな、放浪の旅は、きっとお互いに面白いと思う!