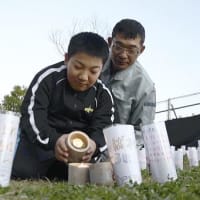栗東市蜂屋の下鈎(しもまがり)東・蜂屋遺跡で、馬を模した土の焼き物「土馬(どば)」(奈良時代、8世紀)が出土し、市教委が23日、発表した。脚などが欠損しているが、馬の表情や手綱などが精巧に表現されていた。土馬は雨乞いなどの祭祀(さいし)で使われたとされ、県内では奈良~平安時代の約90点が見つかっているが、市教委は「同時代の土馬の造形はデフォルメされる例が多く、今回のように写実性に富み、リアルなものは珍しい」としている。造成工事に伴い、昨年6月~今年7月に約9300平方メートルを発掘調査したところ、河川(幅約4メートル、深さ約30センチ)跡の底で見つかった。全長約17センチ、高さは約9センチ。他の土馬に多い低温の素焼きではなく、窯でしっかり焼く製法で、首や腹には焼成時の破裂を防ぐ小穴も空いていた。目や鼻には粘土の粒を貼り付け、馬の頭にかける組みひも「面繋(おもがい)」も表現するなど、丁寧に作られていた。
一方、前脚2本と後ろ脚1本は欠損し、人為的に折られたとみられる。馬は古来、雨乞いなどの際にいけにえとして神にささげられたが、次第に土馬や絵馬で代用されたといい、市教委は「大切な脚を折ることで、神に馬を献じる意図を込めたのだろう」とみている。
出土地点の50~100メートルには、寺院(7世紀後半~8世紀初め)や役所(8世紀半ば)の跡もあることから、発掘を担当した市体育協会文化財調査課の佐伯英樹主幹は「寺や役所が主導し、優れた工人に精巧な土馬を作らせて雨乞いをしたのでは」と話す。
土馬は栗東歴史民俗博物館(小野)で9月14日~10月27日に開く特集展示「馬のまち栗東」で公開する。問い合わせは同館(077・554・2733)。
小笠原好彦・滋賀大名誉教授(考古学)の話「高温で焼いて作られた土馬は全国的にも少ない。今回は丁寧に表現している点で非常に貴重だ」
【写真】顔や馬具が巧みに作られる一方、脚が欠損していた土馬(栗東市の栗東歴史民俗博物館で)