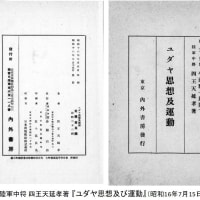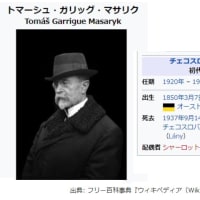大川周明
時 事 論 集
〔解説〕
一、維新の大業に一念発起してからその生涯の幕を閉ちるまで約40年間、機に臨み時に応じて発表した小論文を、本全集各巻との重複を避けて編輯し「時事論集」とした。便宜上時代を追って「第ニ維新の発祥期」「行地社時代」「神武会時代」「大東亜戦争以後」の4期に分けたが、特に満洲事変及び支那事変中のものは全集第ニ巻に収め、大東亜戦争中のものは同じ第二巻の「新亜細亜小論」に収録した。
一、『月刊日本』第70号(昭和6年1月号)の巻頭言に博士自ら「吾等が第二維新の覚悟を抱き始めたのは、実に大正7年(1918)米騒動の前後であり、一顧して長望すれば星霜すでに13年を経た。云々』と云われたとおり、象牙の塔に籠って思索の内に学問的要求を満たすことに堪え切れなくなって、敢然として現実の改造運動に拮据するに至ったのは、大正8年、『猶存社』を創立した当時からである。
猶存社は機関紙『雄叫び』を発行して、沈淪頽廃せる風潮の真っ只中に挑んで行ったが、『雄叫び』は第3号を以て官辺の圧迫に屈した。
一、猶存社解散の後、博士は満鉄東亜経済調査局、旧本丸内の社会教育研究所のちの大学寮を本拠として同志との往来を繁くしたが、大正14年(1925)『行地社』を結成し、機関紙『月刊日本』を発行した。『月刊日本』は同年4月に創刊号を発刊して爾後営々7年に亘り、昭和7年4月85号を以て終った。本書には月刊日本のなかから『道義国家の原則』ほか16の論文と適当なる巻頭言を抜萃した。
一、博士は組織布陣の運動を進一歩して昭和7年2月、行地社から『神武会』に移行して、行地社の機関紙をそのまま継承したが、形は新聞タブロイド版とし、昭和10年4月神武会解散まで満3年継統した。但し博士はこの間殆んど囚桎の生活を送られた為に機関紙掲載の論文の数はすくないが、この獄中にあった期間は専ら『近世欧羅巴植民史』に没頭していた。
一、戦後の圧巻は正しく『コーラン』の原典和訳であるが、他巻との重複を懸念して数篇を載せるに止めた。
第一篇 第二維新の発祥期
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一、 ここに取録する『第二維新に面せる日本』『世界戦と日本』『世界史を経緯しつつある二問題』は、大正10年著『日本文明史』(写真)の結論部分をなす第26章・第27章・第28章である。
一、尚ほ『日本文明史』が、博士の日本歴史研究四著書のうちの最初の著作であることは、本全集第一巻「国史概論」の解説(409頁)に既述したところである。
(『日本文明史』大正10年10月版406頁 大鐙閣刊)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一 第二維新に面せる日本
勤王倒幕を標語とせる治維新は、憲法発布を以て一段落を告げた。而して明治維新の革命的運動を大観すれば、そは『幕府』即ち一切の封建的制度を根本より倒壊することによりて、不当なる武力の圧迫より吾等の『君』を救ひ参らせたものである。
之を今日より回顧すれば、明治維新の建設的一面は『勤王』の標語が最も簡潔明晰に表明する如く、皇室をして真個国家の中心となし奉るの一点に集注せられ、而して此の目的は、幾多有名無名の元勳の粉骨砕身によりて、最も見事に成就された。
国民は頼朝の覇権確立以来700年、否な藤氏専権以来実に千年にして、初めて明朗なる天日を仰ぐことを得た。この大業の遂行にして、我等日本国民は、子々孫々に至るまで、満腔の感謝を維新革命の志士に献げねばならぬ。
然るに『幕府』倒れてより50年、憲政布かれてより30年、日本国民は曩日『勤王』志士の心を紹いで、而して之を徹底せしむる為に、更に『興民』の志士として、第二維新の大業に拮据せねばならぬ時となった。この第二維新を成就することに由て、日本は始めて其の国体の精華を発揮し、真に君民一体の実を挙け、天地と共に無窮なりとの森厳雄渾なる建国の精神を実現して、真個世界の救拯者たるを得るであらう。
何故に我等は第二維新の必要を高調する乎。日く日本は君臣一体の国なるが故である。『君』は第一維新によりて之を武力の圧迫より救ひ参らせた。されど『民』は今や金力の圧迫に呻吟しつつある。故に之を黄金の不当なる支配より解放することは、君民一体の実を挙ぐる唯一無二の途である明治維新の破壊的一面は『討幕』の一語に尽き、其の建設的一面は『勤王』の一語に尽きた。
大正維新に於ては倒さる可きものは黄金を中心勢力とする閥であり、興さる可きものは国民其ものである。即ち大正維新の標語は『興民討閥』でなければならぬ。
然らば如何にして第二維新を必要とする国状を招徠せしめたか。
第一には日清日露の両役以後に於ける人心の弛緩論である。日露戦争が勝利を以て終局する迄は溌剌進取の生命が、尚ほ日本の国家に躍動して居た。日本を世界の強国と伍せしめずば止まずとする雄健剛毅の精神が、尚ほ国民の精神を支配して居た。
然るに一たび露国と戦ひ勝ちて、皮相外面ではあり乍ら、世界一等国の班に入ると同時に、明洽日本の理想は﨡に其の外形だけは実現せられ、之と共に従来張りつめし心弛み、且つ国民を鼓舞すべき新たなる具体的理想が遂に樹立せられざりしが故に、頽廃の風潮が驚くべき急速に一世に漲るに至った。
試みに日露戦役を中心として以前及び以後に於ける人心の激変を見よ。
若し眼光よく此の無形の変化に徹する能はざるものは、日清日露の両役の間に人となれる今日30代の青年又は壮年者と、日露戦仗以後に初等の教育を受けて人となれる20代の青年者との思想道念を彼此対照せよ。真個に驚くべき変化であり且つ相違でないか。
固より明治日本の教育は、日露戦役を一期として前後其の根本義を改めた訳ではない。而も生を両役の当時に享け集し敏感なる青少年の心は、国家非常の秋なりし対外戦の間に育ちて、国家の内面に躍如たりし無形の精神に陶冶せら明れしが故に、能く堅実なる国家観念を把持し、真個日本精神を長養するを得た。
然るに日露戦役以後に人となれる青年は、学校の修身に於て如何なる事を教え込まれたにせよ、自然主義、享楽主義、而して功利主義横行の時代に呼吸せるが故に、若千少数の例外を除けば国家に奉公するの精神なく、偶々之れ有れば日本本来の国体と相容れざる国家観念を奉じて、其の実現を図らんとするの状態であり、之を全般より言へば著しく不健全なる思想道念の所有者である。
而して青年の心は、要するに総体としての国民精神の反映である。青年をして茲に至らしめたのは、取も直さず日露戦役を段落として、国民の心に昔日の壮快敢為なく、剛健進取なく、好学知新なく、而して苟安自負の心、早くも其頭を擡けたるが故に外ならぬ。
第二には政府当局者の責である。
西南戦役によって明治維新の大業、略々成就せらる、と共に、勤王志士の壮厳なる精神、慚く其光を薄くし、身を以て君国に奉ずる大公無私の政治家次第に減じ、朝に在りては閥族相率ゐ野に在りては朋党比周するの風を助長し、国民をして、政治家の無誠意を憤らしめ、官民の阻隔を招ぐに至った。
殊に歴代の政府が、国民生活に対して殆ど全く自由放任の政策を採れることと、種々なる関係より権力階級・富豪階級を保護するの政策に出でたることとは、互に相扶けて一般国民を圧迫するに至り、国家的生活によりて何等積極的幸福を享有せずと感ずるに至って、必然忠君愛国の思想が衰へた。
而して第三に如上の形勢を助長し激成せしめたものは、
言ふ迄もなく世界大戦である。世界大戦による経済的変動、急激に所謂成金者を生んだ。而して此等の成金者が敢てせる奢侈と、政治家の之に迎合阿附せる態度とは、深刻に人心を険悪ならしめた。
かくして世界大戦は、一面に於て急激に貧富の懸隔を甚だしくしたと同時に、他面に於て戦争に伴へる物価の昻騰は、殆ど底止するを知らざる勢を以て進み、国民の生活を俄然として不安に陥らしめた。加ふるに米食の激増より来れる内地の産米不足は、最も直接に国民生活を不安ならしめ、遂に重大なる暴動を惹起するに至っこ。
かくして生活問題より来る貧民と富豪との敵視、資本家と労働者との確執は、急転直下の勢を以て進み、所謂温情主義の如きを以てしては、最早断じて解決を不可能とする状態となった。
第四に之を思想の方面より観るに、
欧米思潮の応声虫にして其魂を西洋に売れる学者操觚者のデモクラシー鼓次が吾等の前に述べたる20代の青年を駆りて、益々不健全又は抽象的なる国家観念を抱くに至らしめた。而して一方には幕末攘夷の精神を今日まで引摺り来れる極端なる保守主義者が、之に対抗して伊勢の神風的言論を高調し、共極は国体擁護運動となりて彼我入り乱れての論戦となり、更に世人の神経を鋭敏ならした。
第五には外患である。
明治維新の有力なる契機も、実に黒船襲来であった。今や『黒船』は、英米の亜細亜侵略主義の相を取りて、刻々に吾等を脅威しつつある。近く150隻の大繿隊を東海に派遣することによりて、米国は再び維新激成者の役割を勤むべく上帝の選抜を蒙むったのかも知れぬ。
世界大戦以前に於て、英米の発展には独逸と云ふ強大なる牽制者があった。アングロ・サキソンとゲルマンとの対抗は、亜衵亜を掃蕩せんとする白人潮流の一大防波堤であった。
然るに今や此の防波堤は、無残に破壊せられて、急潮は何の支ふるものもなく、矢の如く、疾く押寄せる。西南よりは英国が、亜刺比亜・波斯・亜富汗斯坦・印度・西蔵と頂々に洗ひ尽して、今や波浪ヒタヒタと中華民国の岸を打って東北よりは米国が、アラスカより北氷洋を超え、西比利亜より満洲に出で、満洲より支那に進み嵜る。
独逸の次には日本と云ふのが、最早消さんとしても消し切れぬほど、深く鮮かに刻み込まれたアングロ・サキソンの外交的心理でないか。若し日本にして其の伝統的外交を根本より改めて、亜細亜を味方として彼等に対抗せざる限り、此の国難を切抜ける道があるか。而して此の国難襲来に対する不安と憂慮とが、人心動揺の一因となって居ることも、拒み難き事実である。
さて斯くの如く考、来れば、最早尋常一様の手段を以てしては、到底国家を富嶽の安きに置くことが出来なくなった。然り、第二維新の機運は熟して来た。日本国を目睫に迫れる内憂外息より救ひ、進んで明治元動の遺業を大成し真個君民一体の国家を実現して、その世界的使命を遂行するために、吾等は結束して起たねばならぬ。明治維新の実行者は実に白面の青年であった。第二維新も、亦吾等青年によって成就されるであらう。