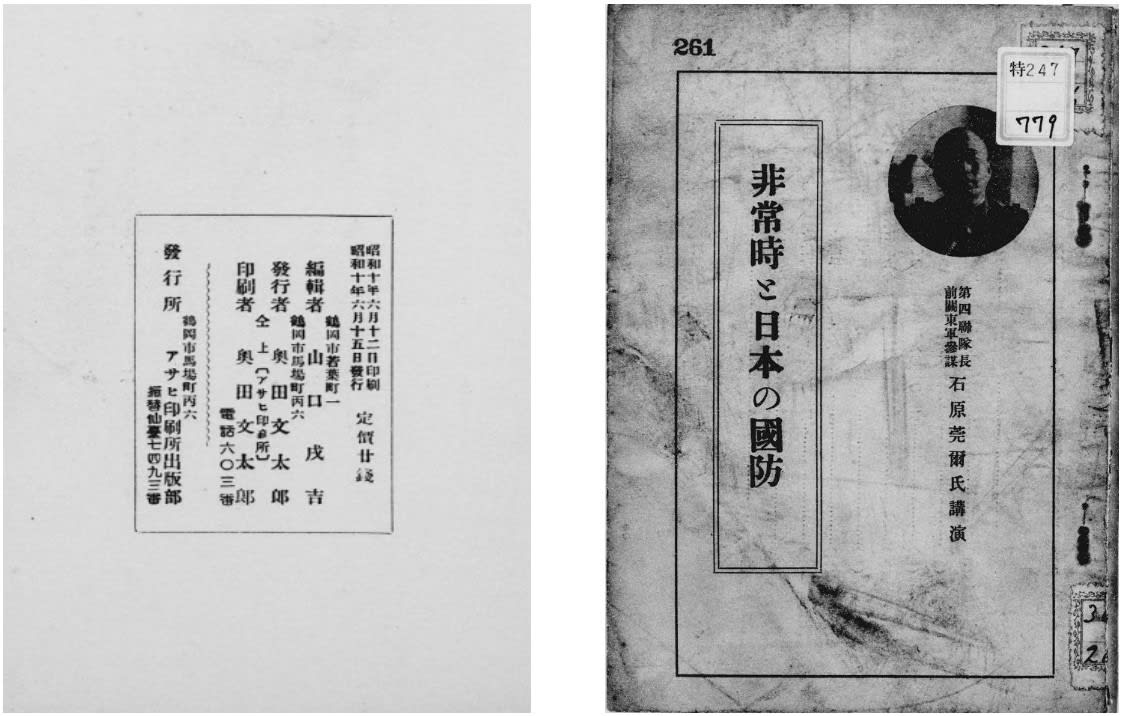石原莞爾『戦争史大観』
第三篇 戦争史大観の説明
第四章 戦闘方法の進歩
第一節 隊形
古代の戦闘隊形は衝力を利用する密集集団方式であった。
中世騎士の時代となって各個戦闘となり、戦術は紊みだれて軍事的にも暗黒時代となった。
ルネッサンスは軍事的にも大革命を招来した。
火薬の使用は武勇優れた武士も素町人の一撃に打負かさるる事となって歩兵の出現となり、
再び戦術の進歩を見るに至ったのである。
火薬の効力は自然に古いにしえの集団を横広の隊形に変化せしめて横隊戦術の発達を見た。
横隊戦術の不自然な停頓と、
フランス革命による散兵戦術への革新については詳しく述べたから省略する。
一概に散兵戦術と云うも最初は散兵はむしろ補助で縦隊の突撃力が重点であった。
それが火薬の進歩とともに散兵に重点が移って行った。
それでもなおモルトケ時代は散兵の火力と密集隊の突撃力との併用が大体戦術の方式であった。
それが更に進んで
「散兵をもって戦闘を開始し散兵をもって突撃する」時代にすすみ、
散兵戦術の発展の最後的段階に達したのがシュリーフェン時代から欧州大戦までの歴史である。
第一次欧州大戦で決戦戦争から持久戦争へ変転をしたのであるが、
戦術もまた散兵から戦闘群に進歩した。
フランス革命当時は、先ず戦術的に横隊戦術から散兵戦術に進歩し、
戦争性質変化の動機ともなったのであるが、
今度は先ず戦争の性質が変化し、
戦術の進歩はむしろそれに遅れて行なわれた。
最初戦線の正面は堅固で突破が出来ず、
持久戦争への方向をとるに至ったのであるが、
その後砲兵力の集中により案外容易に突破が可能となった。
しかし戦前逐次間隔を大きくしていた散兵の間隔は損害を避けるため更に大きくなり、
これは見方に依っては第一線を突破せらるる一理由ともなるが、
その反面第一線兵力の節約となり、
また全体としての国軍兵力の増加は、
限定せられた正面に対し使用し得る兵力の増大となり、
かくて兵力を数線に配置して敵の突破を防ぐ事となった。
いわゆる数線陣地である。
しかし数線陣地の考えは兵力の逐次使用となって各個撃破を受くる事となるから、
自然に今日の面の戦法に進展したのである。
欧州大戦に於ける詳しい戦術発展の研究をした事がないから断定をはばかるが、
私の気持では真に正しく面の戦法を意識的に大成したのは
大戦終了後のソ連邦ではないだろうか。
大正3年8月の偕行社記事の附録に「兵力節約案」というものが出ている。
曽田中将の執筆でないか、と想像する。
それは主として警戒等の目的である。
一個小隊ないし一分隊の兵力を距離間隔600メートルを間して鱗形に配置し、
各独立閉鎖堡とする。
火力の相互援助協力に依り防禦力を発揮せんとするもので、
面の戦法の精神を遺憾なく発揮しているものであり、
これが世界に於ける恐らく最初の意見ではないだろうか。
果して然りとせば
今日までほとんど独創的意見を見ない
我が軍事界のため一つの誇りと言うべきである。
古代の密集集団は点と見る事が出来、
横隊は実線と見、
散兵は点線即ち両戦術は線の戦法であり、
今日の戦闘群戦術は面の戦法である。
而してこの戦法もまた近く体の戦法に進展するであろう。
否、今日既に体の戦法に移りつつある。
第二次欧州大戦でも依然決戦は地上で行なわれ、
空中戦はなお補助戦法の域を脱し得ないが、
体の戦法への進展過程であることは疑いを容れない。
線の戦法の時でも砲兵の採用は既に面の戦法への進展である。
総ての革新変化は決して突如起るものではない。
もちろんある時は大変化が起り「革命」と称せられるけれども、
その時でさえよく観察すれば
人の意識しない間に底流は常に大きな動きを為しているのである。
ソ連邦革命は人類歴史上未曽有の事が多い。
特にマルクスの理論が百年近くも多数の学者によって研究発展し、
その理論は階級闘争として無数の犠牲を払いながら実験せられ、
革命の原理、方法間然するところ無きまでに細部の計画成立した後、
第一次欧州大戦を利用してツアー帝国を崩壊せしめ、
後に天才レーニンを指導者として実演したのである。
第一線決戦主義の真に徹底せる模範と言わねばならぬ。
しかし人智は儚はかないいものである。
あれだけの準備計画があっても、やって見ると容易に思うように行かない。
詳しい事は研究した事もないから私には判らないが、
列国が放任して置いたらあの革命も不成功に終ったのではなかろうか。
少なくもその恐れはあったろうと想像せられる。
資本主義諸列強の攻撃がレーニンを救ったとも見る事が出来るのではないか。
資本主義国家の圧迫が、
レーニンをしていわゆる「国防国家建設」への明確な目標を与え大衆を掌握せしめた。
もちろん「無産者独裁」が大衆を動かし得たる事は勿論であるが、
大衆生活の改善は簡単にうまく行かず、
大なる危機が幾度か襲来した事と思う。
それを乗越え得たのは「祖国の急」に対する大衆の本能的衝動であった。
マルクス主義の理論が
自由主義の次に来たるべき全体主義の方向に合するものであり、
殊に民度の低いロシヤ民族には相当適合している事が
ソ連革命の一因をなしている事を否定するのではないが、
列強の圧迫とあらゆる困難矛盾に対し、
臨機応変の処理を断行した
レーニン、スターリンの政治的能力が今日のソ連を築き上げた現実の力である。
第一線決戦主義で堂々開始せられた革命建設も結局第二線決戦的になったと見るべきである。
ナチス革命は明瞭な第二線決戦主義である。
ヒットラーの見当は偉い。
しかしヒットラーの直感は革命の根本方向を狙っただけで、
詳細な計画があったのではない。
大目標を睨みながら大建設を強行して行くところに古き矛盾は解消されつつ進展した。
もちろん平時的な変革ではない。
たしかにナチス革命であるが大した破壊、犠牲無くして大きな変革が行なわれた。
大観すればナチス革命はソ連革命に比し遥かに能率的であったと言える。
この点は日本国民は見究めねばならない。
第二次欧州大戦特に仏国の屈伏後はやや空気が変ったが、
国民が第一線決戦主義に対する憧憬余りに強くソ連の革命的方式を正しいものと信じ、
多くの革新論者はナチス革命は反動と称していたではないか。
この気持が今日も依然清算し切れず
新体制運動を動ややもすれば観念的論議に停頓せしめる原因となっている。
日米関係の切迫がなくば新体制の進展は困難かも知れない。
蓋し、困難が国民を統一する最良の方法である。
今日ルーズベルトが全体主義国の西大陸攻撃(とんでもない事だが)を餌として
国民を動員せんとしつつあるもその一例。
リンドバーグ大佐がドイツより本土攻撃せられる恐れなしと証言せるは余りに当然の事、
これが特に重視せらるるは滑稽である。
第二節 指揮単位
「世界最終戦論」には方陣の指揮単位は大隊、
横隊は中隊、
散兵は小隊、
戦闘群は分隊と記してある。
理屈はこの通りであり大勢はその線に沿って進歩して来たが、
現実の問題としてそう正確には行っていない。
横隊戦術の実際の指揮は恐らく中隊長に重点があったのであろう。
横隊では大隊を大隊長の号令で
一斉に進退せしむる事はほとんど不可能とも言うべきである。
しかし当時の単位は依然として大隊であり、
傭兵の性格上極力大隊長の号令下にある動作を要求したのである。
散兵戦の射撃はなかなか喧噪なもので、
その指揮すなわち前進や射撃の号令は中隊では先ず不可能と言って良い。
特に散兵の間隔が増大し部隊の戦闘正面が拡大するにつれてその傾向はますます甚だしくなる。
だから散兵戦術の指揮単位は小隊と云うのは正しい。
しかしナポレオン時代は散兵よりも戦闘の決は縦隊突撃にあったのだから、
実際には未だ指揮単位は大隊であった。
横隊戦術よりも正確に大隊の指揮号令が可能である。
散兵の価値進むに従い戦闘の重点が散兵に移り、
密集部隊も戦闘に加入するものは大隊の密集でなく中隊位となった。
モルトケの欄(121頁付表第2)に、
散兵の下に「中隊縦隊」と記し、
指揮単位を「中隊」としたのはこの辺の事情を現わしたのである。
日露戦争当時は既に散兵戦術の最後的段階に入りつつあり、
小隊を指揮の単位とした。
しかるに戦後の操典には射撃、運動の指揮を中隊長に回収したのであった。
その理由は、
日露戦争の経験に依れば、
一年志願兵の将校では召集直後到底小隊の射撃等を正しく指揮する事困難であると云うのであった。
若し真に日本軍が散兵戦闘を小隊長に委せかねるというならば、
日本民族はもう散兵戦術の時代には落伍者であると言う事を示すものといわねばならぬ。
もちろんそんな事はないのであるから、
この改革は日本人の心配性をあらわす一例と見る事が出来る。
更に正確にいえば、
ドイツ模倣の一年志願兵制度が日本社会の実情に合しない結果であったのである。
欧州大戦前のドイツで
中学校ギムナジュウムに入学するものは右翼または有産者即ち支配階級の子供であり、
小学校卒業者は中学校に転校の制度はなかったのである。
即ち中学校以上の卒業者は自他ともに特権階級としていたので、
悪く言えば高慢、良く言えば剛健、
自ら指導者たるべき鍛錬に努力するとともに
平民出身の一般兵と同列に取扱わるる事を欲しないのである。
そこに特権制度として一年志願兵制度が発達し、しかもその価値を発揮したのである。
しかるに明治維新以後の日本社会は真に四民平等である。
また近時自由主義思想は
高等教育を受けた人々に力強く作用して軍事を軽視する事甚だしかった。
かくの如き状態に於て中学校以上を卒業したとて一般の兵は二年または三年在営するに対し、
僅か一年の在営期間で指揮官たるべき力量を得ないのは当然である。
本次事変初期に於ても
一年志願兵出身の小隊長特に分隊長が指揮掌握に充分なる自信なく、
兵の統率にやや欠くる場合ありしを耳にしたのである。
これはその人の罪にあらずして制度の罪である。
この経験とドイツ丸呑みよりの覚醒が自然今日の幹部候補生の制度となり、
面目を一新したのは喜びに堪えない。
しかし未だ真に徹底したとは称し難い。
学校教練終了を幹部候補生資格の条件とするのは主義として賛同出来ぬ。
「文事ある者は必ず武備がある」のは特に日本国民たるの義務である。
親の脛をかじりつつ、同年輩の青年が既に職業戦線に活躍しある間、
学問を為し得る青年は一旦緩急ある際一般青年に比し
遥かに大なる奉公の実を挙ぐるため武道教練に精進すべきは当然であり、
国防国家の今日、旧時代の残滓とも見るべきかくの如き特権は速やかに撤廃すべきである。
中等学校以上に入らざる青年にも、
青年学校の進歩等に依り優れたる指揮能力を有する者が尠すくなくない。
また軍隊教育は平等教育を一抛し、
各兵の天分を充分に発揮せしめ、
特に優秀者の能力を最高度に発展せしむる事が必要であり、
これによって多数の指揮官を養成せねばならぬ。
在営期間も最も有利に活用すべく、
幹部候補生の特別教育は極めて合理的であるが、
猥みだりに将校に任命するのは同意し難い。
除隊当時の能力に応ずる階級を附与すべきである。
序ついでに現役将校の養成制度について一言する。
幼年学校生徒や士官候補生に特別の軍服を着せ、
士官候補生を別室に収容して兵と離隔し身の廻りを当番兵に為さしむる等も
貴族的教育の模倣の遺風である。
速やかに一抛、兵と苦楽をともにせしめねばならぬ。
率先垂範の美風は兵と全く同一生活の体験の中から生まれ出るべき筈である。
将校を任命する時に将校団の銓衡会議と言うのがある。
あれもドイツの制度の直訳である。
ドイツでは昔その歴史に基づき将校団員は将校団で自ら補充したのである。
その後時勢の進歩に従い士官候補生を募集試験により採用しなければならないようになったため、
ややもすれば将校団員の気に入らない身分の低い者が入隊する恐れがある。
それを排斥する自衛的手段として、
将校団銓衡会議を採用したものと信ずる。
日本では全く空文で唯形式的に行なわるるに過ぎない。
私は更に徹底して幹部を総て兵より採用する制度に至らしめたい。
かくして現役、在郷を通じて一貫せる制度となるのである。
世の中が自由主義であった時代、
幼年学校は陸軍として最も意味ある制度であったと言える。
しかし今日以後全体主義の時代には、
国民教育、青年教育総て陸軍の幼年学校教育と軌を同じゅうするに至るべきである。
即ち陸軍が幼年学校の必要を感じない時代の一日も速やかに到来する事を祈らねばならぬ。
それが国防国家完成の時とも言える。
そこで軍人を志すものは総て兵役につく。
能力により現役幹部志願者は先ず下士官に任命せられる。
これがため必要な学校はもちろん排斥しない。
下士官中、将校たるべき者を適時選抜、士官学校に入校せしめて将校を任命する。
今日「面」の戦闘に於ては指揮単位は分隊である。
しかしてこの分隊の戦闘に於ては分隊が同時に単一な行動をなすのではない。
ある組は射撃を主とし、
ある組はむしろ白兵突撃まで無益の損害を避けるため
地形を利用して潜入する等の動作を有利とする。
操典は既に分隊を二分するを認めており、「組」が単位となる傾向にある。
この趨勢から見て次の「体」の戦法ではいよいよ個人となるものと想像せられる。
「体」の戦法とは戦闘法の大飛躍であり、
戦闘の中心が地上特に歩兵の戦闘から空中戦への革命であろう。
空中戦としては作戦の目標は当然敵の首都、工業地帯等となる。
そして爆撃機が戦闘力の中心となるものと判断せられ、
飛行機は大きくなる一方であり、
その編隊戦法の進歩と速度の増加により
戦闘機の将来を疑問視する傾向が一時相当有力であったのである。
しかるに支那事変以来の経験によって戦闘機の価値は依然大なる事が判明した。
今日の飛行機は莫大の燃料を要し、
その持つ量のため戦闘機の行動半径は大制限を受けるのだが、
将来動力の大革命に依り、
戦闘機の行動半径も大飛躍し、
敵目標に潰滅的打撃を与うるものは爆撃機であるが、
空中戦の優劣が戦争の運命を左右し、
依然戦闘機が空中戦の花として最も重要な位置を占むるのではないだろうか。
第三節 戦闘指導精神
横隊戦術の指導精神は当時の社会統制の原理であった「専制」である。
専制君主の傭兵が横隊戦術に停頓せしめたのである。
号令をかける時刀を抜き、
敬礼する時刀を前方に投出すのはこの時代の遺風と信ずる。
精神上から言ってもまた実戦の必要から言っても、
号令をかける場合刀を抜く事は速やかに廃止する事を切望する。
みだりに刀を抜き敵に狙撃せられた例が少なくない。
そうすれば指揮刀なるものは自然必要なくなる。
日本軍人が指揮刀を腰にするのはどうも私の気に入らない。
今日刀を抜いて指揮するため危険予防上指揮刀を必要とするのである。
フランス革命により本式に採用せらるるに至った散兵戦術の指導精神は、
フランス革命以来社会の指導原理となった「自由」である。
横隊の窮屈なのに反し、散兵は自由に行動して各兵の最大能力を発揮する。
各兵は大体自分に向った敵に対し自由に戦闘するのである。
部隊の指揮単位に於てなるべく各隊長の自由を尊重するのである。
大隊戦闘の本旨は「大隊の攻撃目標を示し、
第一線中隊をして共同動作」せしむるに在った。
そうして大隊長はなるべく干渉を避けるのである。
戦闘群の戦術となると形勢は更に変化して来た。
敵は散兵の如く大体我に向き合ったものが我に対抗するのではない。
広く分散している敵は互に相側防し合うように巧みに火網を構成しているから、
とんでもない方から射撃せられる。
散兵戦術のように大体我に向い合った敵を自由に攻撃さしたなら大変な混乱に陥る恐れがある。
そこで否が応でも「統制」の必要が生じて来た。
即ち指揮官ははっきり自分の意志を決定する。
その目的に応じて、各隊に明確な任務を与え各隊間共同の基準をも明らかにする。
しかも戦況の千変万化に応じ、適時適切にその意図を決定して明確な命令を下さねばならない。
自由放任は断じてならぬ。
昭和15年改正前の我が歩兵操典に大隊の指揮に対し、
大隊長の指揮につき
「大隊戦闘の本旨は諸般の戦況に応じ大隊長の的確かつ軽快なる指揮と
各隊の適切なる協同とに依り大隊の戦闘力を遺憾なく統合発揮するにあり」と述べ(第480)
更に「……戦況の推移を洞察して適時各隊に新なる任務を附与し
……自己の意図の如く積極的に戦闘を指導す」(第504)と
指示している。
この統制の戦術のためには次の事が必要である。
1、指揮官の優秀、およびそれを補佐する指揮機関の整備。
2、命令、報告、通報を迅速的確にする通信連絡機関。
3、各部隊、各兵の独断能力。
3に示す如く、統制では各隊の独断は自由主義時代より更に必要である。
いかに指揮官が優秀でも、千変万化の状況は全く散兵戦術時代とは比較にならぬ結果、
いちいち指揮官の指揮を待つ暇なく、また驚くべき有利な機会を捉うる可能性が高い。
各兵も散兵に比しては正に数十倍の自由活動の余地があるのである。
一兵まで戦術の根本義を解せねばならぬ。
今日の訓練は単なる体力気力の鍛錬のみでなく、
兵の正しき理解の増進が一大問題である。
我らの中少尉時代には戦術は将校の独占であった。
第一次欧州大戦後は下士官に戦術の教育を要求せられたが、
今日は兵まで戦術を教うべきである。
統制は各兵、各部隊に明確なる任務を与え、
かつその自由活動を容易かつ可能ならしむるため
無益の混乱を避けるため必要最少限の制限を与うる事である。
即ち専制と自由を綜合開顕した高度の指導精神であらねばならぬ。
近時のいわゆる統制は専制への後退ではないか。
何か暴力的に画一的に命令する事が統制と心得ている人も少なくないようである。
衆が迷っており、
かつ事急で理解を与える余裕のない場合は躊躇なく強制的に命令せねばならない。
それ以外の場合は指導者は常に衆心の向うところを察し、
大勢を達観して方針を確立して大衆に明確な目標を与え、
それを理解感激せしめた上に各自の任務を明確にし、
その任務達成のためには広汎な自由裁断が許され、
感激して自主的に活動せしめねばならない。
恐れ戦き、遅疑、躊躇逡巡し、
消極的となり感激を失うならば自由主義に劣る結果となる。
社会が全体主義へ革新せらるる秋とき、軍隊また大いに反省すべきものがある。
軍隊は反自由主義的な存在である。
ために自由主義の時代は全く社会と遊離した存在となった。
殊に集団生活、社会生活の経験に乏しい日本国民のため、
西洋流の兵営生活は驚くべき生活変化である。
即ち全く生活様式の変った慣習の裡うちに叩き込まれ、
兵はその個性を失って軍隊の強烈な統制中の人となったのである。
陸軍の先輩は非常にこの点に頭を悩まし、
明治41年12月軍隊内務書改正の折、
その綱領に
「服従は下級者の忠実なる義務心と崇高なる徳義心により、
軍紀の必要を覚知したる観念に基づき、
上官の正当なる命令、周到なる監督、およびその感化力と相俟って能くその目的を達し、
衷心より出で形体に現われ、
遂に弾丸雨飛の間に於て甘んじて身体を上官に致し、
一意その指揮に従うものとす」
と示したのである。
これ真に達見ではないか。
全体主義社会統制の重要道徳たる服従の真義を捉えたのである。
しかし軍隊は依然として旧態を脱し切れないで今日に及んでいる。
今や社会は超スピードをもって全体主義へ目醒めつつある。
青年学校特に青少年義勇軍の生活は軍隊生活に先行せんとしつつある。
社会は軍隊と接近しつつある。
軍隊はこの時代に於て軍隊生活の意義を正確に把握して
「国民生活訓練の道場」たる実を挙げねばならぬ。
殊に隊内に私的制裁の行なわれているのは遺憾に堪えない。
しかも単に形式的防圧ではならぬ。
時代の精神に見覚め全体主義のために
如何に弱者をいたわることの重大なるかを痛感する
新鮮なる道義心に依らねばならぬ。
東亜連盟結成の根本は民族問題にあり。
民族協和は人を尊敬し弱者をいたわる道義心によって成立する。
朝鮮、満州国、支那に於ける日本の困難は皆この道義心微かすかなる結果である。
軍隊が正しき理解の下に私的制裁を消滅せしむる事は
日本民族昭和維新の新道徳確立の基礎作業ともなるのである。
【続く】石原莞爾 『戦争史大観』 第三篇 戦争史大観の説明 第五章 戦争参加兵力の増加と国軍編制(軍制)